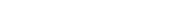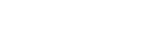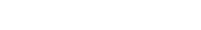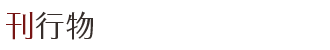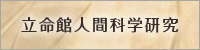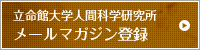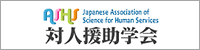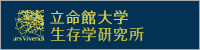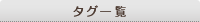『立命館人間科学研究』No.11 [通巻27号](2006年3月発行)
| ■目次 | ||
| ■研究論文 | ||
| 「科学」に依存しない知識の可能性と物語りのリスク
─「知識生産」を「フィードバック」から再考する─ |
荒川 歩 | (1) |
| チーム医療のマネジメントと情報共有
─イギリスの3病院の脳卒中病棟から─ |
村田 京子 | (11) |
| 社会的相互作用の導入と比例概念に対する子どもの理解の深化 | 吉田 甫 平山 十四郎 |
(25) |
| パノラマ写真における広視界感と側方距離知覚との間の異質性 | 大中 悠起子 松田 隆夫 |
(35) |
| 幼児期における行動調整機能の発達的研究
─go/no-go課題における分化反応の分析─ |
前田 明日香 | (45) |
| ■研究ノート | ||
| The Center-of-gravity Model of Chromostereopsis |
KITAOKA Akiyoshi
KURIKI Ichiro ASHIDA Hiroshi |
(59) |
| 基準の多様化の視点からのヒューマンエラー再考 | 尾田 政臣 | (65) |
| 幼児期前半における象徴の理解とふり行動の獲得 | 井上 洋平 | (75) |
| ■実践報告 | ||
| 知的障害のあるろう者における携帯メール入力支援の試み
─文字入力に及ぼすひらがな表カードの効果─ |
太田 隆士 飯田 智子 藤井 克美 望月 昭 |
(85) |
| 知的障害のあるろう者における携帯電話のテレビ電話機能を用いた
非音声複数モードによる機能的言語行動の訓練 |
飯田 智子 太田 隆士 藤井 克美 望月 昭 |
(93) |
| ■特集 | ||
| 「対人援助学としての臨床社会学の展開にむけて」 | 中村 正 | (105) |
| 血のつながりのない家族関係を築くということ
─非配偶者間人工授精を試み,その後,養子縁組で子どもをもった女性の語りから─ |
安田 裕子 | (107) |
| 今日における子どもをもつ意味変容
─イギリスにおけるParenting Educationの台頭─ |
斎藤 真緒 | (125) |
| 家族ケアを構成する二つの資源
─知的障害者家族におけるケアの特性から─ |
中根 成寿 | (137) |
| 出産の医療化と「いいお産」
─個別化される出産体験と身体の社会的統制─ |
松島 京 | (147) |
| ■執筆者紹介・奥付 | ||