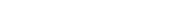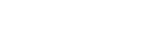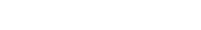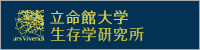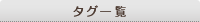低出生体重児支援と職種連携戦前・戦中期日本の未熟児医療——誰が未熟児の救命を担うのか?
産科と小児科の狭間
今日では未熟児の出生など、新生児になんらかの問題が生じたら、その新生児は産科医から小児科医の手に移され、NICU(新生児集中治療室)などで治療を受けます。しかし、昔からそのような仕組みができていたわけではありません。
日本に近代医学が導入された明治期の時点で、産科学のテキスト、小児科学のテキストともに未熟児の介助方法に関するトピックが掲載されていました。しかし、双方とも保育器を用いた保温が紹介され、母乳による栄養法が推奨される程度で、割かれる分量は他のトピックに比べて少ないものでした。このことについて、当時、未熟児医療をはじめとする新生児医療が産科と小児科の狭間に置かれたため、研究が進んでいなかったと指摘されています。
助産師の時代
さて、内容自体は相違ないのですが、産科学テキストと小児科学テキストの未熟児をめぐる記述には、一つの違いがありました。それは、小児科学テキストが「疾病」と捉えるのに対し、産科学テキストは「看護」と捉えていたことです。ここで、産科領域で看護を担う専門職、すなわち助産師(戦前、戦中期の用法では産婆/助産婦)に着目する必要が出てきます。
当時の助産学テキストでも未熟児の看護のトピックが取上げられており、後に東京帝国大学(現在の東京大学)の産婦人科学教授となる白木正博の『白木助産学 前編』第15版(1932年、南山堂書店)でも、医師の監督の下でと留保されながらも、「(未熟:筆者注記)児の生死は一に懸りて看護者の掌中にあり」とされていました。また、1920年代にある富裕層宅で産科医、小児科医、助産師の立会のもと、出産が行われ、未熟児が出生したのですが、このとき勝手のわからない医師をよそに新生児の介助を行っていたのは助産師でした(『周産期医学』12(5)、1982年)。
産科医と小児科医の共同から小児科医の時代へ
1930年ごろになると、未熟児の救命の様相が少しずつ変わってきます。1940年には、本邦初の新生児医学専門書、『新産児病学』(南江堂)が刊行されます。ここでは、従来の小児科学/産科学テキストに比べ、未熟児に関するトピックが詳細に語られていました。著者の小南吉男は産科医でしたが、彼は京都市児童院という施設に勤めていました。この施設は、低所得者向けに設立された施設で、産科医と小児科医が常駐していました。つまり小南は未熟児医療をはじめとする新生児医療の研究を行うにあたり、容易に小児科医と連携できる立場にあったといえます。
この時期、京都市児童院を同じ条件を備え、かつ、未熟児医療を積極的に進めていた施設が東京に存在しました。それが日本赤十字社本部産院です。ここで、産科医の久慈直太朗は、1930年代から小児科医の砂田惠一らと共同して、カテーテルを口から挿入してミルクを与える方法など、未熟児医療研究の成果を積極的に発表するようになります。
このように、徐々に医師が未熟児の救命の中心を担うようになっていきます。戦後になると、この傾向はますます強まり、慶應義塾大学の産婦人科学教授であった安藤画一の「産科学 下巻」(1948年、鳳鳴堂)では、未熟児のトピックが「看護」ではなく新生児の「異常」と捉えられていき、こうした現象は他の産科学テキストにもみられました。つまり、産科学テキストでは未熟児の救命が徐々に「看護」から切り離されていったのです。そして、戦後の未熟児医療研究は、徐々に産科医の手からも離れていき、小児科医がその中心を担うようになっていきます。