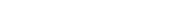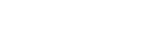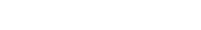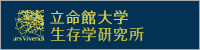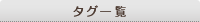「インクルーシブ社会に向けた支援の<学=実>連環型研究」プロジェクトそれは社会問題であるという定義−「問題視することの問題」
社会病理・社会問題現象は何らかの紛争や葛藤なので、関係性の修復や回復が課題となる。しかしことはそう単純ではない。「問題」とは何か、「解決」とは何かが難儀だからである。たとえば不登校が「問題」であり、再登校が「解決」だとは言い切れない。違法薬物使用は「問題」であり、それは法的な処分(処罰)へと至ることが「解決」だとは思えない。依存症という「問題」の定義も可能であり、そうすると処罰ではなく回復が「解決」となる。ひきこもりはいかなる意味で「問題」と定義でき、家を出ることが「解決」だとは必ずしもいえない。あるいはまた、「問題」をひっくり返されることがある。たとえば不登校の生徒が通うフリースクールで調査をしている本チームの院生がいる。どうして学校に行かなくなったのか(あるいは行けなくなったのか)を調べたいと思っていた。ところが逆に生徒に聞かれた。「お兄さんはどうして学校に行っていたのか(行くことができたのか)」と。調査の「問い」がはらむ前提が問われた。「不登校を問題視するあなたは誰か」と。調査者の立ち位置(ポジショナリティ)を問う「問い返し」である。
社会病理・社会問題を対象にする場合、この「問題」と「解決」の定義や「問い返し」の存在を意識していくことが欠落すると研究と実践と政策は揺れる。たとえば日本映画学校の卒業作品として制作された映画「home」はそのことを意識していた。弟がひきこもりの兄を映した。兄は地に足つかない、外の世界に出ることの恐怖を「三センチ上の世界」と表現し、ひきこもっていた 7 年間の記録を日記として紹介している。日記は饒舌だ。回顧的な後からの意味づけでなく、渦中にある時のリアルな声が新鮮である。ひきこもりと称されているけれども、無為な時間ではない。濃密な時間として記述されている。
映画のなかに映し出された兄の部屋にある膨大な映画のビデオテープが印象に残る。兄は映画が好きだということにこの「home」の核心のひとつがあると感じた。立命館大学で映画を上映し、映画を制作した弟とひきこもっていた兄を招いて話をきいた。兄が学生たちに訴えた。映画のラストでようやく家を出た兄に安堵した聴衆に向けた刃であった。「ひきこもりの主人公は車で家を飛び出た。しかし、その主人公はちっとも胸をなでおろしてなんかいないし、その結末に<ハッピーエンド>を読みとる観客に腹を立てている。・・ちゃんと観て欲しかった。あの空っぽのガレージを。これが、今現在、そして、これからも続く私の不安と恐怖なんだ」、「『ひきこもり』 当事者とその周囲の人々の間には、ある絶望的な意識の差がある。そして、その意識の差異の提示はあらゆる場面で行われうるべきだ」と。この弟のまわすカメラに対して、「ひきこもりのリアルを伝える。手法はあっぱれだ。映像好きの私は『いいものとってくれるなら』という心の隙間があった。学生映画特有の予定調和のものなら握りつぶしていたところだ。」と「home」のパンフレット(ボックスオフィス発行)で兄が語っている。映画制作のためにカメラを向け、カメラにむけて語ることでリアルが構成され、いやがおうにもひきこもりをなんとかしたいという弟の書いたシナリオが実行されていく。
「映画のなかの映画」のようにして兄の主人公性がひきだされている。兄は「表現欲」について語る。「映画に対する憧れ」があったと。そうなるとこの映画を完結させるためにその主人公は家を出ることを余儀なくされる。「映画のなかの映画」の主人公を演じきったのだ。カメラの力である。それは兄の欲望をよく理解していたからできたこと。
ドキュメントとはいえ、それは映画としての虚構性をもつ。弟はこの兄の表現欲に棹を差しながら、うまい具合に(もちろん予定調和ではなく)、家族関係再編に向けた変化へのカーブを描いた。しかし兄は厳しい。兄はトークのなかで「共犯関係」という言葉を用いて観る者の視線と感情のポジショナリティを問うたのだ。兄がひきこもりから家をでてハッピーエンドを感じ、それに安堵したあなたこそがひきこもりへと人を追い立てる者である、だからそのことは感情的に共犯性を帯びているのだと。その感情の持ち方自体を変えるべきだという。
ドキュメンタリーの起爆力
思い出したのが原一男氏の「ドキュメンタリー論」。プライバシーへの侵入としての記録映画の意義について語るくだりである。「プライバシーって、個々人の価値観とか感性とかいうふうに言うけれど、そういう個々人がもっている感じ方、感性をよく見ていくと、自己矛盾的にその中に制度的なものが非常に入っているというふうに思ってしまう。だからこちらがその制度的なものに対して、キャメラを持って打って出ようとするときに、ターゲットはやっぱり個人の感じ方の世界へどうしても向かっていく」、それで、「ことの結果というか必然として、プライバシーの領域にどうしても踏み込まざるを得ない」、「プライバシーって言っている部分の中に、僕らが抱えている矛盾みたいなものがかなり含まれているんじゃないかと思う」、「やっぱり生身の人間の中で見つけ出して引きずり出したい」、「僕らがキャメラを持って他人の中に踏み込んでいったとき、被写体のほうも自分で予測もしていなかったようなものが出ちゃったりして、その人が積み上げてきた、今日まで平和でやってきたものがガラガラと崩れるんじゃないかと思われるかもしれない。しかし、残念ながらそう簡単には崩れない。・・・それほどにやっぱり積み上げてきたものは強烈なはずなんです」(原一男『踏み越えるキャメラ―わが方法、アクションドキュメンタリー―』フィルムアート社)と語る。起爆力を秘めた私的領域のエネルギーである。
そこで対人援助について考える。臨床はプライベートな領域に踏み込む。聞く側はそうしたことをしている。ドキュメンタリーやカメラとよく似た機能を有している。プライバシー、私的なこと、秘密にしておきたいこと、語りたくないこと、苦悩や苦痛や悩み方等、すべてに社会が入り込んでいる。それを開くとみたくないものまでみえてくる。聞く者の責任もあるし、観る者の見方も問われる。プライベートなことは奥まったところで起爆性を秘めているからだ。芸術の多くはそれらをあるフレームのなかで表現する。臨床や援助もまた同じように取り出していく。調査をすれば聞いた者の責任が発生する。臨床や支援は個別性が肝心。それをとおして社会のもつ課題へと応答させなければならない責任が臨床家にはある。守秘義務と別の次元の義務だ。これらはだから「対人援助と民主主義」という主題を成していると思う。心理化し、個別化しては閉じていくばかり。
問い返しに応答する
学校に通っていたことの意味について、その「問い返し」をされた院生は不登校という言い方の妥当性も再考する。私が彼に問うたことは、不登校の「校」とは何か、何からの不登校なのか、不登校を微分し、そのように観念され、総称されている事態を解体していくべきことを。概念としての不登校があまりにも肥大化しているし、それに寄りかかっていては見えないものがあることをこそ調べるべきだと。不登校の子ども自身も社会のもつ、既製の物語に染まっているかもしれない。そうすると世間の持つ自立の物語に即して回復を描くことになる。自己を責めることもある。自尊心も低下する。せっかくの不登校経験を活かすことがないと「負の経験」として物語られていくだけだ。既存の物語に回収されてしまう。
この「問い返し」をした生徒はすでに不登校の生徒ではない。とはいえ学校への再登校をしているのでもなく、それだけを目標にしてはいない。大切なことは、学習を持続させていることである。学習者として存在している。学びの場やかたちが異なるだけだ。他にも、ひきこもりのままできる仕事があればそれは在宅ワークとして徐々に日常生活の外出ができるようになればいい。脱不登校や脱ひきこもりは何から何へ変容なのかと問い続けなければならない。社会問題の研究ではその内包と外延が不明確なものが多い。くだんの院生の研究の隠れたテーマは「さよなら不登校!」ではないかと提案している。臨床や支援に関心が集まる時代や社会だからこそ問うべき課題は、その内容よりも、「問題の定義」と「解決の意味」であることを重視した共同研究を、実践の仕方の工夫や制度・政策の提案も試みながら展開している。