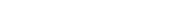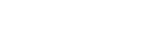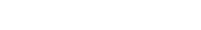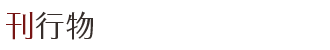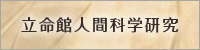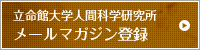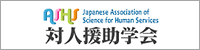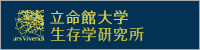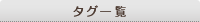『立命館人間科学研究』No.21 [通巻37号](2010年7月発行)
| ■表紙 | ||
| ■目次 | ||
| ■研究論文 | ||
| 高齢者を対象としたSRC課題における復帰抑制(2)
─不適合条件を中心とした検討─ |
孫 琴 吉田 甫 土田 宣明 大川 一郎 |
(1) |
| 社会的予測における人物情報と状況情報の機能的同異 | 織田 涼
八木 保樹 |
(9) |
| 分離教育か共生共育かという対立を越えて
─「発達」概念の再検討─ |
野崎 泰伸 | (25) |
| 婚外恋愛継続時における男性の恋愛関係安定化意味付け作業
─グランデッド・セオリー・アプローチによる理論生成─ |
松本 健輔 | (43) |
| 音韻情報の記憶が高齢者における順序の短期記憶に及ぼす影響 | 都賀 美有紀 毛留 幸代 星野 祐司 |
(57) |
| 幼児の不器用さについての保育者の印象
─M-ABCとの関連から─ |
渋谷 郁子 | (67) |
| 中国帰国者の支援制度からみるコミュニティ通訳の現状と課題
─通訳者の役割考察─ |
飯田 奈美子 | (75) |
| 注意の持続における行動調整機能の発達と言語の役割
─左右両手同時緊張把握課題を用いて─ |
前田 明日香 | (89) |
| 現代フランスにおける「生命のない子どもの証明書」
─医学および民事身分上の「生存可能性」をめぐって─ |
山本 由美子 | (103) |
| 明治・大正期における公衆浴場をめぐる言説の変容
─衛生・社会事業の観点から─ |
川端 美季 | (119) |
| 日本のリハビリテーション学におけるQOL概念の生成と変容 | 田島 明子 | (133) |
| ■実践報告 | ||
| 家庭において親は「ひきこもり」本人に対してどう対応すればいいのか
─「ファーストステップ・ジョブグループ『対応を学ぶ』」講座の効果に関する検討─ |
上田 陽子 | (147) |
| ■研究ノート | ||
| 幼児のふり遊びの共有における協約性と言語発達の検討 | 片山 伸子 高田 薫 渋谷 郁子 吉本 朋子 川那部 隆司 高木 和子 |
(163) |
| 東金女児遺棄事件に関するブログ記事の分析 | 上村 晃弘 サトウタツヤ |
(173) |
| ■編集規定 | ||
| ■執筆者 | ||
| ■編集委員 | ||
| ■奥付 | ||