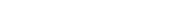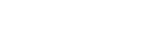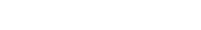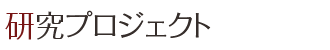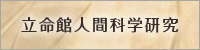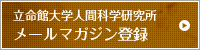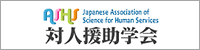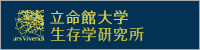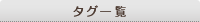司法面接記録の評価に関する実証研究とチャットによる司法面接の効果(司法面接記録の評価と技術展開)
背景と目的
司法面接とは、子どもや障がい者等の供述弱者から、精神的負担に配慮しながら暗示や誘導なく事実を聴取する方法であり、聴取内容は映像で記録される。司法面接は、海外で開発された面接技法だが、供述弱者への聴取時の配慮の重要性から、国内においても児童福祉法が定める18歳未満の子どもを対象に、検察、警察、児童相談所が連携して司法面接を実施している。近年では、聴取対象者の範囲を拡大し、18歳以上であっても障害を持つ性犯罪被害者に対して、精神的負担の軽減および供述の信用性確保の観点から司法面接が行われる場合もある。
司法面接が普及したことで、2023年に刑事訴訟法321条の3が新設され、司法面接が想定される事案の被害者の聴取記録媒体(司法面接記録)が一定の条件下で証拠として認められるようになった。すでに司法面接記録が主要な証拠として判決が下される事案が増えており、司法面接記録を証拠とした判例が、今後さらに増加すると見込まれる。したがって、司法面接で得られた情報の真実性や信頼性の判断基準を明確化し、その適正な活用方法に関する知見を提供することが求められる。
一方で、研究領域においては、記憶の正確な再生を支援する面接手法として特にチャット形式でのAI実装を想定した研究が進展している。現在、国内では、アバターを活用した面接訓練システムの導入など、司法面接技法のICT化が進められているが、チャット形式による司法面接に関する実証的な検討はほとんど行われておらず、その有効性や課題については明らかになっていない。
そこで本研究では、補助物の使用、認知バイアスが司法面接記録に関する真実性や信頼性の判断への影響について検討する。また、チャット形式の司法面接の有効性を検討する。
参加研究者
- 武田悠衣 (OIC総合研究機構・専門研究員)
- 田口琳 (人間科学研究科・博士課程前期課程)
- 秋野光城 (人間科学研究科・博士課程前期課程)
主な研究資金
2025年度 人間科学研究所 萌芽的プロジェクト研究助成プログラム