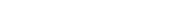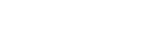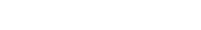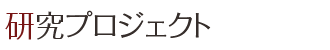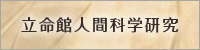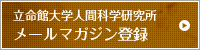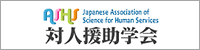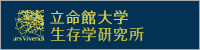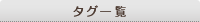一般人の犯罪に対する認識についての多角的調査(市民の犯罪認識・意識調査プロジェクト)
背景
犯罪種別と市民の認識の違い
犯罪に対する一般市民の意識は、犯罪種別によって大きく異なることが指摘されている(Adriaenssen et al.,2020)。一般に、殺人や強盗、痴漢など直接的な身体的・心理的被害を伴う暴力犯罪は、財産犯罪や被害者のいない犯罪に比べて著しく深刻なものとして認識されやすい。実際、先行研究によれば、人々は暴力的な犯罪に対してより否定的な態度を示し、殺人やレイプなどに対しては、ホワイトカラー犯罪(詐欺や汚職など)や被害者なき犯罪に比べ厳しい処罰を求める傾向が高い。
一方、自動車事故や交通違反のように過失や日常性を伴う違反行為は、意図的な犯罪よりも道徳的非難が弱まることがあり、深刻さの認識も状況に応じて変化する。また、近年問題視されるようになったカスタマーハラスメント(顧客による悪質な嫌がらせ)は法律上明確な犯罪とはみなされない場合もあるが、社会的には労働者への心理的暴力として強い非難を招く。
このように、犯罪種別ごとに公衆の感情的反応や道徳的評価が異なり、どの行為をどれほど「深刻な犯罪」とみなすかについて市民間に一定程度の共通認識が存在する(Adriaenssen et al.,2020)。
顕在的態度と潜在的態度の測定
人々が犯罪に対して抱く態度には、顕在的(意識的)態度と潜在的(無意識的)態度の二側面が存在する。顕在的態度とは、質問紙調査やインタビューで本人が自覚して報告する評価であり、社会規範やその場の状況に左右されやすい。一方、潜在的態度は本人も自覚していない自動的な感情反応や連想であり、直接的に尋ねても得られにくい。心理学研究では、両者が必ずしも一致しないことが知られており、時に顕在的報告では否定される偏見や好悪感情が潜在的水準では残存している場合がある(Wilson, Lindsey, & Schooler, 2000; Nosek, Banaji, & Greenwald ,2002)。これは社会的望ましさバイアス(自分を良く見せようとする回答バイアス)などにより、差別的・否定的な本音が表に現れにくいことに起因すると考えられる(Crowne & Marlowe, 1960; Tourangeau & Yan, 2007)。
顕在的測定(アンケート)と潜在的測定による結果の差異は、社会心理学的に大きな意味を持つ。一般に、これら2つの指標の相関は中程度以下であることが多く、そこには潜在的バイアスや回答上の遠慮が表れていると解釈される(Andersen et al., 2025)。実際、Andersen et al.(2025)の研究では、差別的態度に関する顕在・潜在指標を比較したところ、両者の相関は弱~中程度であり、これは社会的望ましさによる回答の歪みが一因であると示唆されている。
本研究でも、アンケートによる犯罪意識の明示的評価とAMPによる暗黙的評価を比較することで、例えば「表向きは重く見ていないが無意識には強い嫌悪感を抱いている犯罪」やその逆のパターンを検出できると期待される。これにより、意識と無意識の乖離が犯罪種別ごとに存在するかどうか、存在するならどのような傾向かを明らかにする。
ウェブコメントと世論
また従来の意識調査とは別に、インターネット上に人々が自発的に残すコメントや投稿も、世論の一側面を表す貴重なデータである。調査(2)では、YouTube上の犯罪関連映像に対する一般市民のコメントを分析し、各犯罪に対する自然な感情反応や意見の傾向を測定する。ソーシャルメディア上の反応は、アンケートに比べて率直である一方、感情的に過激な意見も含まれる可能性がある。これは匿名性や対面ではないコミュニケーションによる「オンライン脱抑制効果」によるものだと考えられる(Suler, 2004)。人々はインターネット上では現実世界で言えないようなことも安全だと感じ、匿名で発言できるため、潜在的な本音や強い感情が表出しやすくなる(Suler, 2004)。その結果、コメント欄には犯罪への怒りや恐怖、被害者への同情、あるいは加害者への厳罰要求といった、生の反応が現れると期待される。
もっとも、ソーシャルメディア上の意見が直ちに一般市民全体の意見を代表するとは限らないことに注意が必要である。例えば、YouTubeのコメントを書く人々はユーザー全体の一部であり、意見の強い層が積極的に発言する傾向がある(Zhang, Chen, & Zhou, 2019)。Zhangらの指摘するように、「ソーシャルメディア上の世論は、調査によって測られる一般世論から二重に乖離している」(Zhang, Chen, & Zhou, 2019)。すなわち、まずソーシャルメディア自体を利用しない人が一定数存在し、さらに利用者の中でも実際に意見表明をする人は限られており、その多くは自らの見解を強く主張する傾向がある(Zhang, Chen, & Zhou, 2019)。
したがって、今回のYouTubeコメント分析でも、そこで観察される反応は積極的な意見保持者の声として解釈する必要がある。ただし、そのような積極的な意見は社会の潜在意識や感情の動向を示すバロメーターともなり得る。特に、匿名空間で噴出する怒りや偏見の表現は、日常の対面場面では抑制される感情を明らかにするため、顕在的調査結果との比較により世論の持つバイアスや隠れた懸念を浮き彫りにできる。
法的規定との乖離と司法制度への影響
犯罪に対する市民の意識と刑法上の犯罪類型や量刑が大きく乖離している場合、司法制度への信頼や遵法意識が低下する可能性がある。Sunshine & Tyler (2003)によれば、法が市民の道徳感覚と一致するほど、その正当性を認めやすく、結果として法に従いやすくなるとされる。逆に、処罰の厳しさや犯罪の扱いが社会常識とずれていると、人々はその法を「不公平」と感じ、遵守意欲を失うことが報告されている(Murphy & Tyler, 2008)。したがって本研究では、各犯罪種別に対する意識と現行法の設定を比較し、司法制度の正当性維持や刑事政策の見直しへの示唆を得ることを目的とする。
目的
以上より、本研究では犯罪に対する一般市民の意識について、犯罪種別に複数の手法により、法的な規定との差異を明らかにすることを目的とする。
そのために(1)ウェブ調査による犯罪に対する顕在的・潜在的意識の調査、および(2)犯罪に関するウェブ動画へのコメントによる犯罪に対する意識調査、の2つの調査を実施する。
本研究の調査(1)では、ウェブアンケートによる犯罪に対する意識の自己報告とAffect Misattribution Procedure(AMP; Payne, Cheng, Govorun, & Stewart, 2005)を組み合わせて用いる。AMPは、被験者の意識的制御を受けにくい手法であり、直前に提示された犯罪関連刺激(例:「殺人」「詐欺」)が無意味図形への好悪評価に与える影響を測定する(Payne et al., 2005)。自己報告(顕在的態度)とAMP(潜在的態度)を併用することで、両者の乖離を明らかにできる(Fazio & Olson, 2003)。
参加研究者
- 中田友貴 (総合心理学部・准教授)
- 高橋典寿 (理工学部数理科学科・助教)
- 杉本菜月 (人間科学研究科・博士課程後期課程)
- 中野紗希 (人間科学研究科・博士課程後期課程)
- 辻絢加 (人間科学研究科・博士課程前期課程)
主な研究資金
2025年度 人間科学研究所 萌芽的プロジェクト研究助成プログラム