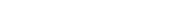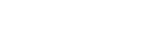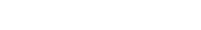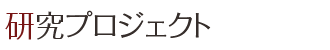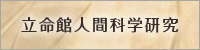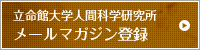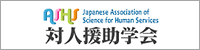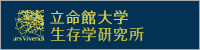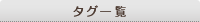神経発達症のある子どもを育てる養育者におけるピアサポートの実態解明および体制構築に関する研究(養育者同士のピアサポート研究)
子どもに神経発達症があると、親の養育ストレスが高まり、精神的健康の問題が顕在化してくることが指摘されている(Yorke et al., 2018)。また、子どもに神経発達症があることは被虐待のハイリスク要因の一つであることも繰り返し示されている(吉川、2020)。そのため近年、神経発達症のある子ども本人に対する支援と同時に、その養育者に対する支援の重要性がうたわれ、その実態解明や体制構築などが強く求められるようになっている。
養育者支援と関わって、昨今ピアサポートの役割に注目が集まってきている。養育者の支援にあたっては、「専門家はかならずしも適任でない」(吉川、2020)。同じような障害や特徴のある子どもを育てた経験のある者同士が仲間として、あるいは先輩として他の養育者と支え合うピアサポートは、周囲の人間関係の捉え方や将来の見通し等にポジティブな変化が生じることや(松井他、2016)、親の精神的健康が改善されること(野上他、2023;野上他、2025)が示唆されている。しかし、親同士のインフォーマルな支援の効果についてはいまだ解明されていないことが多い(原口他、2015)。わが国において神経発達症の子どもを診療する医療機関や専門医が依然として不足しており、自治体としての支援体制づくりもまだ試行錯誤の段階である(新美・本田、2020)という現状を踏まえると、神経発達症のある子どもを育てる養育者同士のピアサポートの機序を明らかにし、専門家による支援とともにピアサポートによる支援の役割とその可能性を検討していくことは意義のあることである。また、専門家による支援と、非専門家(養育者など)による支援とが相補的に作用することができれば、神経発達症のある子どもを育てる養育者はより一層、包括的で的確な支援を受けられることになるであろう。
立命館大学人間科学研究所では、2003年度より「療育プログラム開発プロジェクト」として自閉スペクトラム症児を対象に療育プログラム開発に取り組んできた(通称「あひるくらぶ」)。子どもたちの成長に伴い、メンバーが入れ替わったり、衣笠キャンパスから大阪いばらきキャンパスへ活動拠点が移転されたり、活動日が変更されたりといった変遷を経つつ、現在も3家庭9名(小学生6名、幼児3名)の子どもたちとその養育者が2か月に一度集っている。参加児たちが大学生や大学院生のボランティア・スタッフと一緒に個別に計画された遊びをしている間、その養育者たちは「親の会」と称して日ごろの悩みを語り合い、我が子に対する関わり方をともに考え、子育てに関わる諸問題を共有している。
そこで本研究では、この「親の会」を調査のフィールドとし、「親の会」に参加する養育者たちの互いに向けられた語りを質的に分析する。具体的には、「親の会」で養育者が何を語るのか、そしてそれは回を重ねる中でどのように変容するのかを検討し、養育者たちが「親の会」の活動から何を得ようとしていて、どのような意義を感じているかについて明らかにする。本研究により、神経発達症のある子どもを育てる養育者によるピアサポートの一つの様相を詳らかにすることができると考える(実態解明)。
また、現在、わが国では適切なピアサポートが得られるかどうかについて、居住地域による差異が生じており、適切なピアサポートをいかにグループ活動や地域に根付かせるかが課題となっている(幸・竹澤、2018)。さらには、ピアサポートを組み込んだ支援体制を整えるためには専門機関や行政機関との連携が必要となる(上地・松浦、2021)。本研究で対象とする「親の会」は、神経発達症のある子どもを育てる養育者の他、専門家数名が参加している。専門家らは、基本的には養育者同士の話の流れを見守ることとしているが、適宜必要に応じてファシリテートしたり助言をしたり、情報提供を行ったりしている。本研究では、「親の会」における養育者同士の関係の中に専門家がどのように介入しているかについてもあわせて検討することで、安定的なピアサポート体制をどのように構築し、維持していくか(体制構築)の示唆を得ることも目的としたい。
参加研究者
- 荒木穂積 (名誉教授・客員協力研究員)
- 安陪梨沙 (人間科学研究科・博士後期課程)
- 瀧澤健太朗人間科学研究科・博士後期課程)
- 近藤優羽 (人間科学研究科・博士前期課程)
- 高坂めぐみ (人間科学研究科・博士前期課程)
- 岩本章美 (人間科学研究科・博士前期課程)
- 徳留ゆり (総合心理学部・学部生)
- 奥田千琴 (総合心理学部・学部生)
主な研究資金
2025年度 人間科学研究所 萌芽的プロジェクト研究助成プログラム