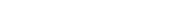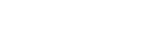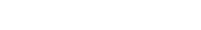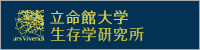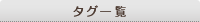応用社会心理学の様々なかたち心理学と社会の接点
2013年度読売新聞「心」のページ
この4月から、読売新聞夕刊「心」のページで第一月曜のみの月イチ連載をしている。かつて朝日新聞で週イチ連載をしていたことがあり、その時は毎週締め切りがくるという普段の生活では味わえない、恐ろしい経験をした。
それに比べれば楽だろうと思って引き受けたが、今度は、月イチ締め切りだと果たして連載として成り立っているのだろうか、という疑問がわかないでもない。
「心」のページはややもすると死生観などと関係することが多く、重いテーマが多くなりがちなので、気楽な話を書いて欲しい、というのが編集子の依頼であった。
「心」のページと応用社会心理学
心理学には様々な分野があるが、筆者の専門は社会心理学である。社会心理学の中でも応用社会心理学ということになっている。これは、社会で実際におきている事象について心理学的な観点から検討していくものである。
「緊張しないために」「北極星的展望をもて」「法心理・司法臨床」「相談と発散」「福島のことを忘れないで」「記憶の不思議」という話題を紡いできた。
法心理・司法臨床は、応用社会心理学の一環として取り組んできたものである。2012年度から稲葉光行教授をリーダーに立命館グローバルイノベーション研究機構のプロジェクトに採択され、日本で唯一、世界で有数、のセンターを目指して研究と社会実装実践を積み重ねてきている。若手研究者の育成も順調にすすみ若林宏輔・滑田明暢の両氏(いずれも立命館大学文学部からの大学院進学者)が2013年度の博士号を取得するに至った。
読売新聞の7月連載では、情状心理鑑定をとりあげて、裁判員裁判時代においては、罪を認めている被告人が、なぜ殺人などを犯すに至ったのかについて説明しなければ、一般市民は納得しない、ということに注意を喚起した。本学・廣井亮一教授の研究成果でもある。
福島・フクシマ・ふくしま
読売新聞の8月連載では、「福島のことを忘れないで」という記事を書いたのだが、それは、私が立命館大学に来る前に福島大学助教授であったことと無縁ではない。
筆者は2013年6月、元同僚である鈴木典夫福島大学教授の協力をえて、福島県浪江町を訪問することができた。この時点において町の大部分が「帰還困難区域」に指定されている地域であり、旧住民の方が一時的に訪問することだけが許されている。したがって、旧住民の方に同行するという形で浪江町を訪問することができたのである。

この写真は車中からの写真である。通行許可証がなければ通ることもままならない。かつての住み処に帰る道にゲートがあり、検問されるのである。誰が悪いかを今は問うまい。しかし、原発の事故がこうした事態を引き起こしたという事実を住民以外の方も知らずには済ませられないのではないか。ついでに言えば、全国各地の原発もひとたび事故がおきればこうしたことが起きることを考える必要がある。


そして、左の写真はお墓である。津波が襲い、墓石がくずれたまま、2年半が過ぎている。遠くに見えるのは漁船である。これも2年半このままである。次の右の写真の船が同じ船であるかどうかは分からないが、近くで撮影するとこんな感じである。とにかく、時間がたってもこのままなのである。
もちろん被災地の復興は全体として進んでいるのである。放射線量の問題の無い地域では。しかし、廃炉まで40年かけるという福島第一原発の周りでは、何も動いていない。そして、一般的な損害賠償請求の期限は3年であるという。未来を見通せない中で何を損害として確定して賠償請求すれば良いのだろうか。こうした問題についてもR-GIRO法心理・司法臨床センターは取り組んでいく。
なお、R-GIRO研究員の木戸彩恵博士は、福島の問題が「フクシマ」とカタカナ書きされていることに注目している。そして、現時点においてひらがな書きの「ふくしま」が用いられていることを指摘し(たとえば、ふくしまからはじめよう、というプロジェクト名)、何事もなかった時のように福島と表記される時こそが、復興の終わったときではないかと考えている。この考えは外国人研究者の興味をひくものであり、一日も早くそうした日が来て欲しいと筆者も願う。
応用社会心理学の様々なかたち
応用社会心理学のプロジェクトであるから、社会に関することであれば、何でも検討していきたい。フクシマの問題はもし大地震がなければ取り組むことも無かっただろうが、一方で、こうした事態になった以上、誰かが取り組まねばならない問題でもある。
私たちのプロジェクトの利点であり欠点でもあるのは、柔軟性である。そして、その柔軟性を下から支えているのは、文化心理学であり、その方法論としての複線径路等至性アプローチである。このことは読売新聞5月の連載で紹介した。
複線径路等至性アプローチとは、自分の描く目標に至るまでには複数の道(径路)があるということを組み込んだ発達・成長の考え方である。会社に入ってからでも、再度大学や大学院に入ることができる、こういう考え方が複線径路的な発想となる。もし目指す目標に対して道が一つしか無ければ、その道が閉ざされた時に挫折してしまうだろうが、径路が複線であれば、一つの挫折があっても他の道を考えようということになるのである。
こうした認識論は2004年に立命館大学で誕生した。当時・アメリカ・クラーク大学教授だったJaan・Valsiner教授(現在はデンマーク・オールボー大学教授)との知的コラボレーションの成果である。私たちのプロジェクトではこの新しい認識論をフラッグシップ(旗艦)にして、応用社会心理学の様々なあり方が、若手研究者の柔軟な発想と共鳴しながら、立命館大学らしい研究を発展させていっている。このことは、日本国内だけではなく世界の研究者からも認められていることである。
この機会に、私たちの元を訪問してくれた海外研究者の紹介サイトを下記に紹介しておく。立命館大学人間科学研究所は大きな世界的ネットワークのハブにもなっているのである。
参考URL
- 立命館大学・立命館グローバル・イノベーション研究機構 (R-GIRO)
『法心理・司法臨床センター』
(https://sites.google.com/site/rgiro2lawpsyc/home) - サトゼミ 研究者来訪記 ver.1 (2004〜2011)
(https://sites.google.com/site/satozemiguest/) - サトゼミ 研究者来訪記 ver.2 (2012〜)
(https://sites.google.com/site/satozemiguest2/home) - 複線径路・等至性モデル
(http://www.k2.dion.ne.jp/~kokoro/TEM/index.html)