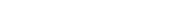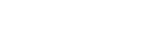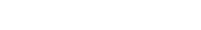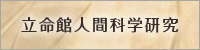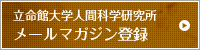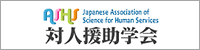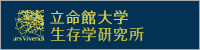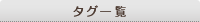ケアという語の氾濫・希望としてのケア
崎山 治男准教授 (写真:右)
「ケア」・「感情労働」・「対人援助」というコトバが語られだし、研究の対象となってきたのは、ごくごく近年のことであり、振り返ってみるならば私の研究史と重なり合うものであった。
これらのコトバ・領域と私との出会いは、大学院のゼミで感情社会学の論文が取り上げられた、という些細なきっかけに過ぎないが、当時、修士論文・博士論文構想会で、ケアや感情労働という概念・コトバを取り上げた際に、出身研究室で、良くも悪くも「流行語大賞」といった様相を呈したことを覚えている。ケアや感情労働のある要素は、程度の差はあれ日常生活の中で誰でもが行っていることであるからだろう。若年の私が申すのもはばかられるが、隔世の感がある。
それ以来、私の頭の中には、なぜ・どうして、人々が「ケア」や「感情労働」といったコトバを語ろうとするのか?そこに希望を託したり困難を見ようとするのか?といったことが、底流としてある。ケアや感情労働が語られない・存在しない社会よりは、語られたり・存在した方がマシではあるだろう。だが、一方で、これほどまでに語られたり、強調される今の社会とは一体何なのだろうか?
社会学的に見るならば、高齢化にともなう介護の問題の増大、液状化する社会における連帯の原理等々、さまざまな語り口は思いつく。いわば、希望なき時代における希望として、あるいはアクチャルな問題として語りが氾濫しているのは確かだろう。
だが、「本当に」ケアや感情労働を必要とする人々の希望や困難の仮託に応えられているのだろうか。「分析」を重ねれば重ねるほど遠ざかり、かといって、それをおこなわざるをえない立場に立ち続けるしかないのだろうか。