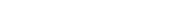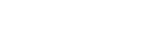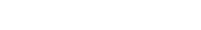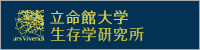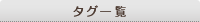ラジオの思い出
文学部教授 東山 篤規
これは、わたしが保育園に通っていたころのはなしです。そのころの我が家では、まだラジオが健在でした。高さは30cm、奥行きは25cm、横幅は40cmもあったでしょうか、直径4cmくらいのダイヤルを回して、電源を入れたり、周波数を合わせたり、音量の調節をしたりできるようになっていました。スピーカのある前面には銀糸の織り込まれたベージュ色の布が貼られていて、音声が柔らかく流れるようになっていました。その裏には、手は入れられないものの、何箇所かに穴の開いた板がはめられていて、真空管によって出された熱を発散させていました。
わたしは、ラジオの中には、小さな人々の住む世界があると固く信じていました。ラジオの中で、かれらは入れ替わり立ち代り、話をしたり歌をうたったりしている。ラジオから流れてくる動物の声や風や水などの音は、小箱の住人が、模倣をしたり、楽器のような道具を使ったりして出している。ラジオの大きさを考えれば、小箱の住人は、たぶん親指くらいの大きさしかない。この小箱の中には、5人からせいぜい10人までの人がいる。そんなふうに考えていたのです。
ラジオの中の人々は、いつも協力し合って我が家のリクエストに答えてくれました。かれらは、きっと、たいそうな働き者で、いつも大忙しです。かれらは、朗読でも、音楽でも、ドラマでも、ほとんど何でもこなす、たいそう親切で能力のある人たちです。今のラジオと違って、当時のラジオは電源を入れても、しばらく沈黙の間があって、その後におもむろに声が聞こえてきました。これは、電源を入れて呼びかけても、別の仕事をしていて、すぐに返事ができないからと思っていました。
あるとき、わたしは、一度ラジオの人々に出会ってみたいと思いました。ラジオの前面は、布とダイヤルと周波数の表示板で覆われているので内部が見えません。そこで背板の穴からのぞきこんで、ラジオの住人が現れるのを待ちました。真空管やさまざまな基盤や配線のうしろから人影が現れることを期待しながらじっと待っていましたが、見つけることはできません。ちょっと目をそらしているあいだに、通り過ぎたのだろうか、10人もいれば一人くらい見つかってもよさそうなのに、・・・たぶん仕事中だから、出て来られないのだろう、電源を切れば休めるから、そのときは僕の前にきっと現れてくるだろう、などと考えながら、スイッチを入れたり切ったりもしてみました。でも、現れる気配すらありません。・・・そうだ、きっとラジオの住人は頑固な「恥ずかしがり屋」さんなのだ。かれらの性格に思いが及んだとき、わたしは、もうかれらに面会を求めるのは止そうと思いました。それでなくてもかれらは、わたしたち家族の要求によく応えてきたのだから。
わたしは、のちに、ラジオの仕組みと真空管のはたらきを中学の「技術家庭」の時間に学びました。その結果、ラジオから流れてくる豊かな音楽や会話や朗読の背後に無機質的な営みがあることに気づかされましたが、幼時のじぶんの思いが、稚拙だとか不合理だというふうには思いませんでした。わたしの見ていた世界を評して、成長とともに忘れ去られるメルヘンの世界と言われれば、そのとおりと答えざるを得ないのですが、その世界は、物理電気の世界とは違う論理と構造をもっていました。
あれから数十年、いまは心理学で糧を得ていますが、幼いころのこの種の空想力が、自身の研究の中に生かされればと思っています。心理学は、人の意識や行動を、記述したり説明したり制御したりすることを目的としますが、適切にこころの説明をおこなうためには、見えないものを感じる力とそうやって感じ取られた世界を洗練させる力が研究者には必要と思っています。