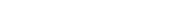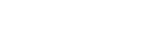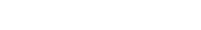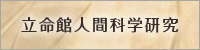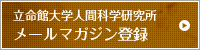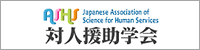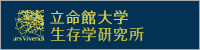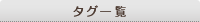シドニー大学にて1 オリンピックの年に
アテネへと聖火リレーがシドニーを出発した時は、町をあげての声援だった。在外研究をしていた04年はオリンピックの年だった。4年前のマラソンコースとなったノースシドニーから市の西部にある競技場までの道路にはその軌跡を示す青いマークがまだ残っている。高橋尚子選手が女子マラソンで優勝したことに思いを馳せながら、自宅から大学まで、シドニー湾にかかるハーバーブリッジを渡り、その青いマークの上を通った。私が通っていたのは市内中心部にあるシドニー大学である。Social Work and Public Policyという大きなカレッジのなかにある Faculty of Educationだ。
オーストラリアを選んだのは、子どもの教育のこと(Sydney Japanese Schoolという日本人学校があること)と連れあいの仕事のこと(日本語教育学を学び、そして教えている)ももちろんある。しかしそれ以上に、オーストラリアへのトポロジー的関心 topologyがあった。それは家庭内暴力の加害者への対応に関心をもつ私が、かねてより気になっていたオーストラリア社会のアボリジニ問題であり、和解 reconciliation という言葉をシンボルにして語られる一連の社会的な取り組みのことである。だからそのブリッジを渡るたびにシドニーオリンピックがアボリジニ問題を意識した大会であったことが思い起こされた。オリンピックのロゴマークにはブーメランが意匠されていた。そして開会式のクライマックスはアボリジニと白人との和解を象徴していた。それはアボリジニの代表としての女子アスリート、フリーマンの勇姿だった。彼女は陸上女子四百メートル決勝で優勝した。オリンピック発祥の地ギリシャに戻るための聖火リレー国際ルートの最初の走者は彼女だった。