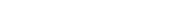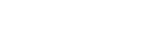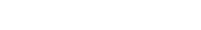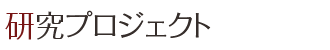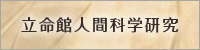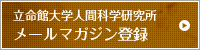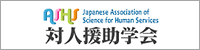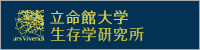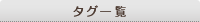視覚障がい者に対する支援実践の検討ー情報支援に着目してー(視覚障がい者に対する支援実践の検討)
背景
視覚障害者は全国で約31万人(厚生労働省, 2008)と言われるが、2009年の眼科医会研究班の報告によれば、およそ164万人の視覚障害者が存在する。さらに、2030年に200万人に増加されると予想され、その多くはロービジョンと呼ばれる全盲ではないが日常生活に支障のある障害である。
視覚障害者に対する支援は医学的な治療によって終了するものではない。特に障害が固定化して見えない状態が続く場合や、徐々に視力が低下する疾患では視覚障害を負った後に日常生活を安全かつwell-beingに過ごせるよう、支援が継続される。障害者への支援でも、特に視覚情報を得づらくなる障害においてはなんらかの具体的な支援を得るまでの仲介となる情報支援は必須である。
福祉制度や福祉ツールは国内でも一定の選択肢がある。しかし、そうした実際に利用する支援制度やツールの存在を知ることが視覚障害を負った場合に難しい。たとえば、視覚障害者が白杖をどこで買ったらよいのかわからなかったということも珍しくない状況にある。そのため、生活に必要な福祉サービスや、社会参加を促進するための地域資源(当事者グループなど)などを仲介することは、社会資源を活用するための基礎的な支援であるといえる。
具体的な支援へ繋げる情報支援実践は、障害の程度、障害受容の程度、本人のもつ資源の程度、ニーズなどを考慮してアウトリーチするものである。この過程は障害者本人の個別性の高さや、関係性の構築など不確定な要素がありマニュアル化しづらいものである。しかし、その実践が成り立っている事実は、何らかの可視化されていない現場の専門知や暗黙知があると考えられる。このような支援は専門性が高いと予想されるものの学術的な評価がされておらず、医療と福祉の仲介を行う視覚障がい者への情報支援現場における調査が必要とされている。
目的
本研究はロービジョンケアや社会接続の機会提供などの支援における実践の構造を捉え、情報支援のあり方を明らかとするものである。具体的に着目するのは、視覚障がい者へ情報支援を提供する人物や組織がどのような実践を行い、支援資源へ繋げているのかである。
本研究の目的が達成されることによって、視覚障がいを持つ人への支援の構造が明らかとなり、課題や改善点が明確になるだろう。また、現場で暗黙知として行われている実践が明確になることで、その専門知が広く利用されることも期待できる。
参加研究者
- 宮﨑浩一 (OIC総合研究機構・専門研究員)