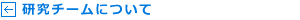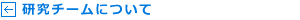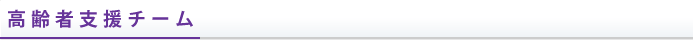
リーダー:土田 宣明(文学部教授)
ヴィゴツキーは「高次精神機能は社会性の中で形成される」と述べています。この言葉を借りるならば、高齢者の高いレベルの認知機能も、社会性の中で維持・発展されるはずです。高齢者支援チームの取り組みにおいては、参加者が「社会性を維持」し、相互に社会的評価が得られる「場」にはどのような構造と機能を必要とするのかを検討しています。そして「今できる」役割の創造に向けた過不足のない支援のありかたについて、できるだけ多角的に分析したいと考えています。
このような目標のもと、取り組みの大きな柱は、従来から実践してきている音読計算活動を行う学習療法の取り組みです。大学を地域資源として、地域高齢者に公開した、学習療法の取り組みを4年間継続的に実施しています(5年目に入ります)。この取り組みそのものの有効性は京都新聞、NHKニュースでも取り上げられています。さらに、大学周辺の学区からの要請で、大将軍、衣笠、楽只、紫明、中川、小野郷、雲ヶ畑の6学区にまでその活動の範囲を拡大しています。地域からの要請に応えての、サポーターの育成、定期的な勉強会や実践報告会の活動などを日本老年行動科学会京都支部と連携して行っているところです。
| チーム参加メンバー |
所 属 ・ 職 名 |
専 門 |
| 土田 宣明 |
文学部・教授 |
発達心理学、老化、行動調節、認知機能 |
| 吉田 甫 |
文学部・教授 |
学習心理学、発達心理学、教育心理学 |
| 大川一郎 |
筑波大学大学院人間総合科学研究科・教授 |
|
2010年度活動報告
| チーム参加メンバー |
所 属 ・ 職 名 |
専 門 |
| 土田 宣明 |
文学部・教授 |
発達心理学、老化、行動調節、認知機能 |
| 吉田 甫 |
文学部・教授 |
学習心理学、発達心理学、教育心理学 |
| 大川一郎 |
筑波大学大学院人間総合科学研究科・教授 |
|

リーダー:竹内 謙彰(産業社会学部教授)
発達支援チームは、人間の発達上の様々な困難に関わって、その実態と支援のあり方を、広い意味での「発達支援」という視点からとらえることを共通のテーマとして発足したプロジェクト・チームです。フィールドは、学校、家庭、地域、専門機関などに及び、子どもだけではなく、大人の発達も視野に入れた調査・研究を進めています。現在は、五つのサブ・プロジェクトのもとで、それぞれ以下のテーマを掲げて研究を継続しています。各サブ・プロジェクトのテーマは以下の通りです。
(1)「不登校・引きこもりへの包括的支援」、(2)「様々な困難を抱えた人への発達支援」、(3)「成人初期の多重役割への適応」、(4)「発達の基盤形成を担う場としての幼児期のなかま遊びの成立の解析」、(5)「関わりに難しさを抱える子どもへの発達支援」。
それぞれのサブ・プロジェクトは、独立した研究・実践活動を行いつつ、発達支援という共通のテーマで連携・協力しあいながら、研究活動を進めていきます。
| チーム参加メンバー |
所 属 ・ 職 名 |
専 門 |
| 高垣 忠一郎 |
応用人間科学研究科・特任教授 |
|
| 春日井敏之 |
文学部・教授 |
臨床教育学、自己変容、相互性 |
| 山本耕平 |
産業社会学部・教授 |
精神保健福祉、青年期、侵入的できごと |
| 櫻谷眞理子 |
産業社会学部・教授 |
生涯発達心理学・児童福祉臨床、社会学 |
| 宇都宮博 |
文学部・准教授 |
生涯発達、ライフコース、結婚・夫婦、家族システム |
| 高木和子 |
文学部・名誉教授 |
|
| 荒木穂積 |
産業社会学部・教授 |
発達心理学 |
| 竹内謙彰 |
産業社会学部・教授 |
自閉症スペクトラム、発達障害 |

リーダー:望月 昭(文学部教授)
「はたらく」ということは、消費者であることと同様に、社会参加を具体的に示すひとつの重要な行為である。しかしながら、昨今の経済事情とも相俟って、さまざまな意味での「障害」や少数派であるがゆえに「今、働くこと」が困難な個人やグループが存在する。
当チームは、大学という地域資源を積極的に利用して「就労可能な社会」を先取りした模擬空間の中で、個別の個人が継続的就労を実現するために必要な包括的で連携的な支援内容について実証的に検討する。大学を模擬空間とすることで、地域店舗では受け入れの難しい「障害」のある個人に対して、構造的で系統的な物理的・人的資源の配置を試み、「援助つき就労」のそれぞれの形を可視化し、そうした支援内容を社会実装していくことを目指す。
対象となるのは、知的な「障害」のある生徒、少数派外国人を含めたコミュニケーションのバリアを被っている個人、そして長期にひきこもりの成人などである。
大学を拠点として、学生ジョブコーチ、ファーストステップ・ジョブグループ、デイジーシステム、デジタル情報バンクなどの新しい資源を活用し、シームレスなキャリア支援の方法を探る。
| チーム参加メンバー |
所 属 ・ 職 名 |
専 門 |
| 望月 昭 |
文学部・教授 |
対人援助学、応用行動分析、障害児教育、障害者就労支援 |
| 小澤 亘 |
産業社会学部・教授 |
文化社会学・思想研究、 文化論政治思想 |
| 八木 保樹 |
文学部・教授 |
心理学 |

リーダー:東山 篤規(文学部教授)
ヒトの心的機能を考えたとき、高齢者・障害者と健常者との間には、明確な境界が認められるものもあれば、境界がはっきりせずに段階的に移行するものもあるが、後者の事例は、かなり広い範囲にわたって認められ、それゆえに日常的に重要な現象と考える。たとえば、若いときに比べて、徐々に視力や視覚記憶が落ちてきたとか(知覚)、転びやすくなったとか(行動)、若い人の早い会話についていけなくなったとか、早とちりが多くなったとか(記憶と理解)、年を経るにしたがって感動することが減ったけれども涙もろくなった(感情)というようなことをよく聞く。こういう現象が、どういう機制によって生じているのかを明らかにし、正しい理解を深めることは、人間の本生を知る作業であるとどうじに、自覚的に豊かな老後を過ごすために有益なことである。
このチームでは、重篤な事例に限らず、この種の軽微な障害(バリアー)を含めて、知覚、記憶、推理、行動の各分野において、我々が直面している心的機能の変調について考察する。知覚の分野では、視覚パターンや平衡感覚の研究を行い、記憶の分野では、援助者が与える指示の理解や行為の適切性の研究を行い、推理の分野では、常識的推理を逸した事例を含めた推論過程の統合的研究をおこない、行動の分野では、体重のコントロールや不器用児の機器(はさみ)の操作、電子的ネットワークの利用に関する研究を行う。
| チーム参加メンバー |
所 属 ・ 職 名 |
専 門 |
| 尾田 政臣 |
文学部・教授 |
ヒューマンインターフェース、認知科学 |
| 北岡 明佳 |
文学部・教授 |
知覚心理学、実験心理学、神経生理学、アート&デザイン、幾何学的錯視 |
| 服部 雅史 |
文学部・教授 |
認知心理学、思考心理学 |
| 東山 篤規 |
文学部・教授 |
実験心理学、知覚 |
| 藤 健一 |
文学部・教授 |
動物における実験的行動分析 |
| 星野 祐司 |
文学部・教授 |
認知心理学 |