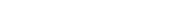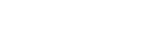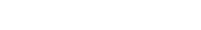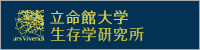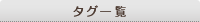山女の呪い
文学部 廣井 亮一 教授
新潟の山育ちの私にとって、遊びといえば、夏は川で魚獲り、冬はスキーをやるだけの毎日であった。魚獲りは、ヤスという長い柄の先端にとがった鉄先を取り付けた漁具で、水中の魚を突いて捕るのである。アユは川の中で上流に顔を向けると数メートル先が見えないほどウヨウヨいるのであるが、泳いでいる魚は突くことができない。さりとて、イワナやヤマメなどの渓流魚は俊敏で見つけることもできない。小学生の相手になってくれる魚は、ハヤとかカジカくらいなものであった。 そのような中で、今でも鮮明に覚えている魚突きの場面がある。小学4年の夏、友達とはぐれてしまい一人で川をのぞいていると、大きな岩陰に一匹の魚の尾びれが見え隠れしていた。今まで経験したこともない深みに息を詰めて潜り、岩陰を正面から見据えると、度でかいヤマメ(山女)であった。ハヤやカジカでは見たこともない、妖艶な輝きを放ち急流の中で魚体を優雅にくねらせていた。初めての「山女」との出会いであった。 もちろん田舎の小学生は“妖艶”などという言葉を知るはずもないのだが、その時のリアルな感覚を今、表現する言葉はそれしかない。見てはいけないものを見てしまったと思いながら、何度息継ぎをして潜っていただろうか。 と、不意にその山女と目が合い、「しまった」と思うやいなや、私は鋭いヤスを山女に突き立てていた。ヤスに射抜かれた山女はすぐに輝きを失い、河原で血を垂らしながら大きな魚体を横たえていた。山並みにはすでに夕暮れが迫っていた。
山女にとり憑かれたのは、それからである。
私が殺した山女に再会することが弔いになるかのように、毎年渓流をさまよっている。学生時代を過ごした新潟では、北陸、東北一帯の山々をくまなくめぐった。家裁調査官として赴任した関西と九州ではヤマメと同種のアマゴ(ヤマメに朱の斑点を散りばめた渓魚)を追い求めた。 釣行は、その山女との出会いの夏と同じように一人でと決めている。日帰りのときは、夜に車を走らせ、深夜の3時ころに山に分け入る。まだ暗い渓流を上流に向かって、釣り地点まで2、3時間ただ遡行するのだが、夜が明ける前の山の中はとにかくいつも恐ろしい。視線を感じて振り向くと、猿や鹿や狸だったりするのだが、いつ「山の女」と目が合うかもしれないとビクビクしている。 昨年の夏に訪れた下北半島の恐山での釣行では、水子供養の風車のカラカラという音色が響くような宇曽利湖の湖畔で深夜車を走らせただけで身震いがしてきて、入山は夜明けを待った。数年前に川辺川ダムに埋没する予定と聞いてその前に訪れた、熊本五木の球磨川上流では狭い谷を転げ落ちて急流の滝に危うく流されそうになった。南紀の古座川上流の崖をよじ登っているときはマムシをつかみそうになったりと、毎度、恐怖と危険にさらされながら、山女の弔いを続けている。 そしてついに、今年6月の関西の某渓流でのことである。その日は梅雨で特にじめじめとしていたが、山女の娘たちが今までにないほど驚くほどたくさん出迎えてくれた。ほくほくしながら、大木の下で一匹づつゆっくりと腹わたを割いて魚籠に収めていると、急に身体のあちこちがチクチクとしてきたのである。腕や胸をさすると上着の下から血のりが浮かび出てくるではないか。「山女の呪いだ!小4の時はお許ください」などと拝んでいると、なんと大木の上からまるで雨だれのように無数の山女ならぬ、山ヒルが降りかかってきたのである。足元にもワサワサと大群が押し寄せていた。すでに、首筋、背中、腹、太ももには、私の血を吸ってぱんぱんに膨れ上がった山ヒルが何十匹もへばりついていたのであった。