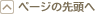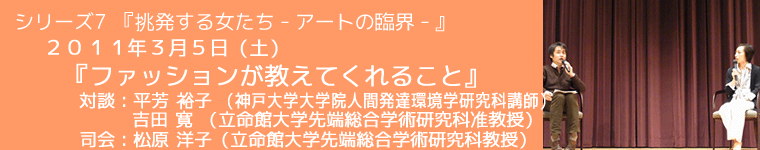
 司会
今日は『ファッションが教えてくれること』を見ましたが、これから平芳さんと吉田さんに対談をしていただき、この映画の理解から出発して、アートやファッションについていっそう理解を深めることができればと考えています。ご紹介をいたしますと、神戸大学の平芳裕子さんは、ファッション文化論、表象文化論をご専攻です。一方、立命館大学の吉田寛さんは、感性学、芸術学がご専門です。それではよろしくお願いします。
司会
今日は『ファッションが教えてくれること』を見ましたが、これから平芳さんと吉田さんに対談をしていただき、この映画の理解から出発して、アートやファッションについていっそう理解を深めることができればと考えています。ご紹介をいたしますと、神戸大学の平芳裕子さんは、ファッション文化論、表象文化論をご専攻です。一方、立命館大学の吉田寛さんは、感性学、芸術学がご専門です。それではよろしくお願いします。吉田 今回のシリーズでは「マリア・カラス」と「草間彌生」の回に続いて、三度目の登壇となります、立命館大学大学院先端総合学術研究科の吉田寛です。よろしくお願いします。私は立命館で美学・芸術学を教えていますが、今回の映画の主題であるファッションに関してはまったくの素人ですので、本日はゲストとして神戸大学の平芳さんにお越しいただきました。平芳さんにはこの映画についての解説やコメントをお願いしたいのに加えまして、ご専門が「ファッション文化論」ということですので、ご自身のご活動についてもお話しいただけたらと思っています。神戸大学でどのような研究・教育活動を展開されておられるでしょうか。また神戸という街──京都の人は東京や大阪には負けないと思っていても神戸には憧れている、とよく聞きます──では、ファッションと大学、あるいはミュージアム(美術館)は現在どういった関係にあるのか。そうしたことからまずお話しいただけますでしょうか。
平芳 ご紹介いただきました神戸大学大学院人間発達環境研究科の平芳裕子です。私はファッション文化論、表象文化論を専門としておりますが、大学及び大学院で授業として担当しているのはファッション文化論です。服飾史という授業科目は女子大学や家政系の大学にもありますが、ファッションというカタカナ名称のついた授業のある大学は、特に国立大学では珍しいのではないかと思います。神戸は明治の開国以来、洋服産業が盛んでした。そして神戸市は1973年にファッション都市宣言を行っており、都市としてファッション産業を盛り立ていくことに意欲的な街です。産業だけではなく文化的な機関として、ファッションをテーマに掲げる全国でも珍しい公立の美術館、神戸ファッション美術館もあります。また、教育機関においてもファッションデザイン学科を備えている大学などが多数あります。そのような都市環境のもとで、産業的側面だけではなく、文化的な側面からファッションを探求することの要請も見受けられます。私も神戸という都市に支えられて神戸大学で教鞭をとっているわけですが、授業では単に服飾の歴史を扱うのではなく、ファッションというものが、ある文化においてどのように受け取られ、成立していったのか、文化的・社会的な側面を読み解きながら歴史の授業を行っています。
吉田 今日のために平芳さんが書かれたご著書やご論文を幾つか拝見しました。その中で私が面白いなと思ったのは、「ファッション文化論」という研究分野の広がりです。例えば日本では「家政学」という学問が伝統的に存在していて、衣服の歴史やスタイルなどはそこで研究されてきたわけですね。ところが「ファッション文化論」というのは「文化」としてファッションを捉える、考える、ということで、われわれの日常により密着したものになってくる、広がりを持ってくる、と思うのですね。平芳さんはご研究の中で、衣服そのものだけでなく、ファッションの雑誌や広告(写真)に注目していますが、今日の映画からも分かるように、まさに『ヴォーグ』のような雑誌やそこでの広告を通じて、ファッションは一気にわれわれの身近な存在になるわけです。また一口に「ファッションの専門家」といっても、服を作る人はもちろん、着る人(モデルも一般の消費者も)、論じる人、また今回のアナ・ウィンター(1949-)のように雑誌を編集・出版する人など、様々な立場があるわけです。それはまさにファッションを取り巻く「文化」といえると思いますが、そうした広がりを捉える「文化論」としてのファッション研究が最近、少しずつ出てきている、という認識でいいのでしょうか?
平芳 そうですね。学問にも流行がありますが、ファッションや服飾は従来の学術分野でも研究対象として扱われてきました。日本では女子大学の家政学部、美術系大学のファッショデザイン学科の中で歴史研究としての服飾研究がありました。またファッションを同時代的な流行現象としてとらえた研究が、総合大学の社会学部系で行われてきました。服飾史的研究と社会学的研究の二つのジャンルがファッション研究の主たる分野だったのですが、90年代以降、欧米でカルチュラル・スタディーズが脚光を浴びてから、デザイナーのクリエイティビティに溢れた作品としてのファッションや、ファッションのサブカルチャー的な側面、あるいは受容の問題などにも注目が集まり、ファッションを多角的な視点から考察しようとする動きが起こります。
ファッションの多様性が注目されるなかで、日本では服飾史以外の学術分野でファッションを取り上げる研究者が増えてきました。衣服と身体の関係を機軸にして哲学的な側面からファッションを考察する鷲田清一氏や、フランス文学研究から文化史的にファッションを捉える山田登代子氏、実際の服飾資料の収集を美術史的な研究に結びつける深井晃子氏など、様々な研究者がファッションに対する多様な見方を提案してこられたわけです。そしてファッションの多様性が浮き彫りになる中で、研究機関においても国立大学では家政学部が解体され、たとえば生活科学という名のもとに新しくファッションや服飾史が位置づけられるなどの動向が見られました。
吉田 今回のシリーズでは「アートの臨界」という副題を付けて三本の映画を選んだのですが、その中でもファッションは独特な位置にありますよね。というのもファッション(衣服)はまさに「アート」、つまりハイカルチャーであると同時に、日常的な必需品でもあるわけです。今日の映画でも「着られなくては、ダメ」という発言がありましたが。つまりファッションというのは、まさに「アート」と「アートでないもの」の境界の上に、作る人(デザイナー)がそこに込めた創造性・アイディアと、着る人の日常性とのバランスの上に成り立っている、と思います。そしてファッションの重要性はそれだけではありません。鷲田清一さんのご研究はファッションを入口にして、私たちの身体やアイデンティティの問題、現代社会における生き方の問題にまで進んでいきます。つまりファッション文化論は、衣服というものを手掛かりにして、現代文化と社会そのものを読み解こうとするものです。その中に、男性と女性の問題、世代の問題、それぞれの国の文化のあり方、また日本と西洋といった諸文化間の関係といったテーマがたくさんある。広すぎる、といってもいいくらいの広がりを持つ研究分野ですね。
さて本日の映画の元々の(英語の)タイトルは「セプテンバー・イシュー」で、『ヴォーグ』というファッション雑誌の「九月号」の製作過程に密着したドキュメンタリーでした。「イシュー」という英語には「号」の他にも「問題、厄介なこと」という意味もありますから、九月号はいつもこんなに大変なんですよ、というメッセージも含まれていると思います。私は『ヴォーグ』という雑誌について、日本語版も出ている、という程度のことしか知りませんので、まずはこの雑誌がどういうものかを教えて下さい。あわせて九月という月がファッション雑誌にとって、どういう意味を持っているかも。「ファッションの世界では九月は新年(一月)のようなものだ」というセリフもありましたが。
平芳 映画のなかで「ヴォーグ」は114年の歴史を持つという説明がありました。一般的にはあまり知られていませんが、「ヴォーグ」は19世紀末の1892年に創刊された雑誌で、古くからヨーロッパのデザイナーのファッションを紹介していました。映画の最後にコンデナスト社の会長が出てきていましたが、1909年にコンデ・ナストが雑誌を引き継いで以来、ヨーロッパからやってきた上流階級やアメリカに住んでいる裕福な中流階級・上流階級に向けて、ヨーロッパの上流階級のライフスタイルやファッションを紹介する雑誌という明確なヴィジョンを持って刊行されてきました。その方針が成功し、1910年代半ばから各国版が出版されるようになります。特にイギリス版とフランス版が成功し、その他の国に広がっていっていき、現在では日本版もあります。長い歴史を持つ雑誌ですが、特に60年代以降には才能ある編集長が雑誌を率いていきました。その一人が今日の映画に出できたアナ・ウィンターです。60年代にはダイアナ・ヴリーランドという著名な編集者がいましたが、彼女は「ヴォーグ」以前にはライバル誌の「ハーパース・バザー」に勤めていました。「ハーパース・バザー」は「ヴォーグ」よりもさらに古く1867年に創刊された雑誌ですが、そこで長く編集者をしていた彼女が「ヴォーグ」に移り60年代の編集長になったわけです。彼女は「ヴォーグ」を辞めた後、ニューヨークのメトロポリタン美術館の衣装部門で展覧会企画の仕事に関わります。20世紀のファッションデザイナーの作品を展示する、つまりファッションの文化的な意義を高めることに貢献したわけです。そして70〜80年代にかけてはグレース・ミラベラがいます。ヴリーランドはオートクチュールのデザイン、ハイファッションに対する理解はありましたが、70〜80年代にかけて市場は高級仕立服から高級既製服へとシフトしていきます。
吉田 既製服というのは量産される服という意味でしょうか。
平芳 ここでいう高級既製服とは大量生産の服とは違います。デザイナーがデザインする高級ラインの服ですが、仕立服ではなく既製服だということです。ミラベラはオートクチュールのような職人仕事ではなく、現実に着られる服を「ヴォーグ」で取り上げ部数を伸ばした人といわれています。そして「ヴォーグ」を辞めた後も「ミラベラ」という自分の名前を冠した雑誌を出版しました。その後に「着られる服」というミラベラが打ち出した路線を踏襲する形で、アナ・ウィンターという編集長がいるわけです。今、オートクチュールとプレタポルテの話をしましたが、映画の中で「九月号はファッションにおける新年だ」という話がありました。日本では何月号にあたるのかということですが、日本はクリスマスが終わるとツリーが途端になくなってお正月飾りになります。アメリカは新年になってもツリーは飾られたままで、ホリデーシーズンは続きます。また日本では新春特大号が一年の始まりを盛り立てるような号になっていますが、四月号になると学校も会社も新年度を迎えるという感じがありますよね。
吉田 それは日本版の『ヴォーグ』の話ですね。
平芳 はい、二つの号を合体したような感じではないでしょうか。
吉田 映画の中でもウィンターの自宅にカメラが入り、部屋の本棚が映るシーンありました。『ヴォーグ』のバックナンバーがずらりと並んでいるわけですが、九月号だけがずば抜けて分厚かった。アメリカの『ヴォーグ』は毎年九月号に非常に力を入れている、というわけですね。
平芳 そうですね。九月号が出てから、10月にかけて世界でプレタポルテのコレクションが行われますし。
吉田 ファッション界の重要なイベントと関係して九月号が重要になるということですか?
平芳 九月号が出てから新しい一年が始まって、9月から10月にかけてニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリは最後を飾るという形でコレクションが開催されます。そしてオートクチュールのコレクションが1月にあり、また2月から3月にかけてプレタポルテのコレクションのシーズンとなります。コレクションで服が発表されると、その話題が雑誌にも掲載されます。
吉田 今回の映画にも個性的な人たちがたくさん出てきましたよね。ドキュメンタリーではなくて、役を演じているのではないのか、と思ってしまうくらいです。アナ・ウィンターの右腕でライバルでもあるグレイス・コディントン(1941-)や、若いデザイナーのタクーン・パニクガル(1974-)。またブランド品で固めた巨体を揺すってテニスをやっていた、アンドレ・レオン・タリー(1949-)もそうですね。そういう類い稀な才能を持った人たちが集まって作っている雑誌『ヴォーグ』は、ファッション界においてどのような役割、意味を持っているのでしょうか。『ヴォーグ』の編集部が頻繁にカメラに映っていましたが、各ブランドから届けられた服が所狭しと並んでいて、誌面の企画を練ったり写真を撮ったりするために、それらを引っ張り出したり、入れ替えたり、また終ったり繰り返ししていました。その様子は、私たちが普通にイメージする「雑誌の編集部」とはだいぶ違ったものです。最新のファッションそのものがそこに集まってくるわけです。あれは服の会社(ブランド)が、是非『ヴォーグ』で取り上げて紹介してくれ、と送ってくるわけですよね。そのとき、服を作るデザイナーとその会社に対して、また実際のその服を買って着る人に対して、ファッション雑誌やその編集者はどのような影響を与えていると考えればいいのでしょうか。
平芳 ファッションには、服をつくる人と、それを雑誌で取り上げる人と、実際に着る人とさまざまな人が関わっています。あるデザイナーのアイディアが実際に<服>に作り上げられたとしても、服の存在そのものが知られなければ<ファッション>とはなりえません。「服を作りました」ということだけで終わってしまう。ある服を「今の気分」を示す流行だと教えてくれる人がいないと一般的には認知されない。その時に雑誌の役割は大きなものになってきます。雑誌のなかには「ちょっとこの服は私には派手すぎて着られないかな」という服も掲載されています。巷で着るに少々派手すぎるようなデザイナーのクリエーションもありますが、ブランド側も売れなければ意味がありません。雑誌も同じです。産業とアート、ファッションにおけるこの二つの側面を見極め、バランス感覚を保ちながら製品をつくっていく。雑誌もそれを見極めながらつくっているわけです。「ヴォーグ」のような雑誌はそれでも大衆向けのファッション雑誌、メーカーの服や一般に受け入れられやすい大量生産の服をたくさん載せている雑誌とは違って、売れる服であることを前提にしつつもブランドやデザイナーのクリエイビリティを拾い上げて、いかにそれをファッション雑誌の紙面で消費者に魅力あるものとして提示していくかに重きをおいているのです。映画のなかでも、これでもかというくらいファッション写真に執着している場面がたくさんありましたよね。
吉田 雑誌としての誇り(プライド)がどうなっているか、という点にも非常に興味がありますね。私の知人でも化粧品業界で仕事をしている人がいますが、その人の話によると、毎シーズンごとの化粧品の色の流行もいわば「トップダウン」で決まっている、ということです。各化粧品会社と雑誌の編集部が結託・連携して翌シーズンに「流行させたい色」を決め、百貨店の化粧品コーナーのような小売りの現場に「次はこういう色を流行らせたいのでよろしく」という指示を下ろしていく。その話をきいて私は、なるほどファッション雑誌なんてその程度のものか、と思ったのですね。それは化粧品の例ですが、スポンサー(広告主)でもあるメーカーの都合で、あからさまに消費者を誘導するための誌面作りをするわけです。ところが今回の映画ではそういう描き方ではなく、アナ・ウィンターもその右腕でライバルでもあるグレイスも、頑固なまでに自分の美的感性を押し通している。自分の美的判断を優先し、誰からも邪魔はされないぞ、という撮り方をしていたと思うのです。実際にはどろどろした部分もあるのだろうと推測はしますが、それくらいのプライド、気概を持って、そしてアーティストばりの感性と判断力を持って、編集者として「勝負」しているわけですよね。いかがでしょうか。『ヴォーグ』はとりわけ高いプライドを持った雑誌だと言っていいのでしょうか。
平芳 アナ・ウィンターは「ヴォーグ」の辣腕編集長、流行を見定める鋭い鑑識眼を持った編集長であると認識されています。そしてアナ自身がセレブリティとして他の雑誌で頻繁に取り上げられています。でも映画を見てみると、彼女が「ヴォーグ」という雑誌を率いることができるのは、実はグレイスというアーティスティックで才能豊かな編集者がいるからなのだと思えてきます。アナ・ウィンターは雑誌における全体のバランスを常に見ています。グレイスが「これはアーティスティック、20年代そのものだわ」というような写真を撮って、確かに写真単体ではファッション写真としてすばらしいかもしれない。でも新年の始まりの特大号の中でその写真がどう機能するかとなると、アナは一言、「トゥーマッチだわ」といって退けてしまう。ビジネスが常にアナ・ウィンターの頭の中にはある。けれどもファッションというものは、ビジネスだけを考えているとつまらないものになってしまいます。人間の身体を覆うために、ファッションデザイナーたちが一枚の布にアイディアを託して服に仕立てていきます。そして雑誌は服の魅力だけでなく、服を着た女性の姿も伝えます。私たちは映画に出てくるモデルのように八頭身ではないけれども、そのモデルを見ると一瞬、自分がそのシチュエーションにいるかのような錯覚を起こします。その世界観のようなものを共有し、誌面に同一化するような気分を味わうことができるのです。ファッション雑誌は服の宣伝もしますが、それだけではなく、女性たちに理想像や理想のライフスタイル、服を取り巻く世界観を提案していく文化的な仕組みなのです。その際に映画の中ではアナ・ウィンターとグレイスの力関係がうまく働いていて、絶妙なバランスで雑誌がつくられていることがわかります。ファッションにおける産業的な側面と芸術的な側面の力関係、そのバランスがうまく成立しているということですね。
吉田 なるほど。ファッションの世界には、服を作る人と着る人だけではなく、大きな領域としてジャーナリズム、メディアがあるということですね。ところで『ヴォーグ』はアメリカで創刊された雑誌ですが、ファッションの中心地は何世紀も前からずっと変わらずパリですよね。平芳さんはご研究の中で、アメリカの雑誌に注目することでファッション文化論を読み解こうとしているわけですが、その中で見えてくるのは一体どのようなことですか。ファッション(服)を生み出す中心地はフランスであるが、人々のファッションの捉え方、われわれのファッション観に強い影響を及ぼす、ジャーナリズムの中心地は『ヴォーグ』を筆頭としてアメリカにある、ということですか。ファッション雑誌から何が見えてくるのでしょうか。
平芳 ファッション研究において雑誌を資料として取り上げる方法自体は新しいものではありません。服飾史でも雑誌に掲載されたファッション写真やファッションプレートを扱います。
吉田 ファッションプレートとはどのようなものですか?
平芳 新しい流行のファッションを身にまとってポーズをとる女性が描かれたイラストです。19世紀の女性誌にはよくつけられたのですが、服を見せることが主目的ですから、二人組の女性が一人は前面、一人は背面を見せるというような姿で形式的に描かれたものが多いです。このファッションプレートも含めて、服飾史は絵画や版画などの資料に描かれた衣服、あるいは現存する衣服から、過去の様式の変遷、形式の変化を実証的に再構成していきます。それが服飾史の基本的な姿勢です。私は同じように20世紀のファッション雑誌の写真や文章、19世紀に遡ってファッションプレートや記事のコメントを資料として研究していますが、19世紀のファッションプレートを扱うからといって、それがその時代の社会の<現実の鏡>、現実がそこに反映されていると読む立場にはありません。
吉田 確かに現代のファッション雑誌も、現代のファッションの〈現実の姿〉を反映しているわけではないですからね。それと同じで、過去の歴史を考える場合も、勘違いしてはいけない、と。
平芳 衣服も含めて図像として、言葉として立ち現れるファッション、そこに西洋文化の諸前提や暗黙の了解事項、文化的なイデオロギーを明らかにしようとする立場で研究をしています。19世紀のファッションプレートにはさまざまな人が関わっています。スタイル画を描く人、版画を彫る人、刷る人、雑誌に採り上げる編集者などです。しかしそこで終わりではなく、読者からの手紙が掲載されていることもあります。編集者の意図と読者の期待と社会の要望と、さまざまな人の思惑や欲望が、そこに凝縮されている。ファッションプレートは<現実の鏡>というより、その時代の理想像であるとか、文化的な<イデオロギーの鏡>であるといえるでしょう。ファッションプレートが成立させられている仕組み、その文化的な枠組みを明らかにしていこうという目的のもとに、実際の衣服よりも、ファッションを取り巻く言葉とイメージを対象として研究をしています。
吉田 ここで大事な点は二つあると思います。まずファッションの歴史」とは何かということ。もう一つはそもそも「ファッション」とは何なのか、ということです。服そのものは残らないことが多い。ですから、ファッションの歴史を研究する場合には、文字史料や絵画、写真など図像史料に頼らなくてはならない。服を扱う美術館・資料館なども無くはないと思いますが、50年前、100年前の〈現実〉となると、どこにもないわけですか。
平芳 服というのは実際に着られていますので、汚れと汗で繊維が磨滅してしまってなくなることもあります。50年前、100年前ですと、京都服飾文化研究財団や神戸ファッション美術館などが企画する展覧会では古い時代の衣装が展示されています。
吉田 新聞や雑誌、写真など「服そのもの」以外の史料を参照しないと、ファッション研究はなかなか難しいと思いますが、そこで重要なのは、ファッション雑誌が一体何を意味しているのか、ファッション写真、ファッションプレートは一体その時代の何なのか、ということです。今のファッション雑誌を考えてみても、今の街中の人々のファッションとは明らかに違うわけです。ところが、100年後、200年後の人々が、今のわれわれの時代のファッションを調べようとするとき──プライベートな写真等を除けば──今のファッション雑誌を見るしかない。それをそのまま受け取られたら困ってしまいます。ファッション雑誌は、その時代の〈現実〉を表現しているわけではなく、その時代の人々の〈未来の欲望〉、つまりこれからどういう服を着たいかという欲求を表現している、ことになるのでしょうか?
平芳 そうですね。理想像や憧れのライフスタイルが、視覚的なイメージとして表象されている。「ヴォーグ」はファッション雑誌の権威ですが、しかし皆が最先端のファッションデザイナーたちの仕事に憧れるわけでもありません。そういうファッションは関心がないけれど、もっと一般の女性たちを対象にしたファッションブランドの服を積極的に掲載している雑誌もあるわけです。雑誌は購読者層があって、女性が職業についているかいないか、働いているとすればどのような職種か。日本の読者層はとても細分化されていて、それぞれの雑誌が理想的な女性像を描き出しています。書店で同じ年代を対象とした複数のファッション雑誌を見ていただくと、たとえば専業主婦の<ママたち>にぴったりのバッグを載せている雑誌があると思えば、一方でバリバリ働く<キャリアウーマン>のためのバックとして同じ商品を紹介している雑誌もあります。そのスタイリングの技量は雑誌のスタイリストや編集者によるかもしれませんが、市場にある商品を、ある雑誌の提案する理想的なイメージにしたがって視覚化していくわけです。
吉田 一般に商品の広告とはそういうものだと言われていますよね。ものを売るのではなく、その前に、ライフスタイルのイメージを売るのだと。服の広告は、とりわけそうした傾向が強いのではないかという印象を私は持ちましたが、いかがですか。
平芳 ファッションは自分の身体にまといます。どんなにすばらしいファッションであっても、それを着る勇気があるかどうかは、その人にかかっていますね。バッグも身体の延長線上という意味でいえばファッションではありますが、服の場合は身体の上に直接まとうのです。現代では衣服は自己表現であるといわれたりもしますから、奇抜な服を着たら何か主張があるのかもしれないと思われることもあり得ます。主張があると思われたい人は率先して着ればよいのですが、もしもそうでないなら、自分とは違う何者かと受け取られるかもしれないという不安が生まれます。ファッションというのは商品ではありますが、一般のデザイン商品とは少し性質が異なると思いますね。
吉田 服は「第二の皮膚」とも言いますものね。つまり服には体(裸体、皮膚)を「隠す」と同時に自分を人に見せる、自己主張をする、という両面性があるわけです。社会や他人に対する「窓」のようなもの、といってもいいかもしれません。ある人と初対面で話したときなどに、第一印象として記憶に残るのは、その人の顔や身振り以上に服であることが多い。とくに言葉を交わさずとも、服を見るだけで、その人の自己表現や主張、好み、こだわりが伝わってきますからね。とくに強い自己主張を持っている人ほど、服に気をつかう傾向があるのではないでしょうか。私などはまるで気にしないわけですが。
平芳 ファッションには、まさに身体を際立たせるという機能があります。ある身体にファッションをまとわせることによって、社会的な視線のもとにおく機能があるのです。これは「ファッションとは何か」という問題ともつながってきます。ファッションって、一般的には<流行のスタイル>ととらえられていますが、言葉の歴史を辿ってみると、昔は決して<流行のスタイル>というわけではないのです。15〜17世紀には<作法>や<習慣>という意味で用いられていたんです。
吉田 「モード」という言葉も、そうですね。
平芳 <作法>や<習慣>、言葉でいうのは簡単ですが、作法や習慣は簡単には変わらないものです。習慣にならえとか、作法にならってくださいというわけですよね。
吉田 むしろ「流行」にならないもの、その逆のもの、ということですね。
平芳 変わってはいけないのです。けれども18世紀以降、<流行>という意味合いが強くなってきます。都市や商品経済が発展していく過程で、ある地域の人々が守っていた作法や習慣が一時的なものでしかなくなっていきます。作法や習慣としてとらえられていたものの継続する時間的な長さが短いものとなり、言葉としても<一時的な風習>、<流行>という意味へと変化していきます。それでは作法としてとらえられていたファッションと、流行としてとらえられたファッションは、全く違うのか。言葉の上では違うように思えますが、言葉の概念に目を向けると、作法を自らの身体に取り入れて、ある集団から自分を差別化し、また別の集団に自分を同一化する。流行も、ある流行に倣うことによって、別のグループから自分を差別化して流行に敏感なグループに自分を同一化させる。他者との差別化、同一化に大きな役割を負っていることがわかります。その際に作法や流行というものを自分の身体に取り入れて、自分の身体を社会的な視線のもとにおく、ファッションにはそのような機能があるわけです。これまで、ファッションの歴史は衣服の様式がいかに変化してきたかということに着目して歴史記述がなされてきました。しかし、ファッションという言葉の概念から考えてみると、実は見える部分ではなく、見えないものの歴史こそ明らかにしなければならないのです。ある時代においてファッションはファッションとしていかに成立させられていたのか、文化的な仕組みの方に目を向けなければならないと、私は常々考えています。
吉田 「見えないもの」の歴史というのは、つまり「関係」の歴史ということですね。例えば、服と社会との関係などがそうでしょうが。
平芳 どのようにつくられてきたのか。残らないからこそ目が行かないのですが、実はそういった部分に光を当てなければいけないのです。
吉田 それでは会場の皆さんとのディスカッションに移ります。本日の映画についてでも、ファッション文化論全般についてでもかまいません。いかがでしょうか。
質問 映画の内容に関して。アナ・ウィンターが黒を避けているというのがあって、きれいな色のような立場に見えたんですが、お洒落を自負する人は黒い洋服を着ることが多いと思いますが。「ヴォーグ」がトップ雑誌であると同時に、黒でなく、色が好きであるというアナ・ウィンターがトップであるということの与えている意味を、お聞きしたいと思います。もう一つは東京にいた時に「オリーブ」という雑誌のスタイリストと知り合うことがあって「オリーブ」は流行りの森ガールっぽいファッションでしたが、ファッションとしてはある傾向に振れている雑誌でしたが、そういう仕事はしているけども、ブランドについての知識が多くて「私だったら何を着たらいいかしら?」何とかというブランドをポンといってくれたんですね。人間の個性とか人間性は、どんな時代もバラエティに富んでいると思うんです。「オリーブ」のスタイリストの人から見た私の個性は、あるブランドの服を着ると引き立つと。今のファッション雑誌は、春先だからストールの特集をしようとか。洋服を機能で考えているけど、各ブランドは各ブランドが考える人間像、浮き立たせたい個性があって、それをかなり誇示してラインを出しているけど、私たちにはそれが届いてなくて、小手先の組み合わせの洋服になっているけど、本当はブランドごとに主義主張とか、カラーがあって、どこかのブランドに委ねると自分の個性が、自分以上に出てくるのかなと思ったりしているんです。マナーとかファッションとか、各ブランドが自分のところのカラーとして持っているのかなと。
平芳 今日はあえて黒を避けたファッションでやってきました。1980年代に日本の前衛デザイナーたちが黒づくめのファッションを打ち出して世界的に流行しました。黒を着ていることがまさに最先端であるという時代があり、日本ではカラス族と呼ばれたものです。代表的なブランドでいうと川久保玲というデザイナーが率いる<コム・デ・ギャルソン>、「少年のように」という意味をもつブランド名で、長らく黒のファッションをリードしてきたブランドがありますが、ある時に突然、カラフルになったんです。ファッションとは、あるアイディアが打ち出されて、それが「ヴォーグ」の編集長やファッションに敏感な一部の人々に着られている間は最先端のファッションでありえます。けれども、巷にいる女性たちも皆、黒を着ている状況になると、それはもはや最先端のモードではありえない。「ヴォーグ」自体もかつては黒いファッションをたくさん取り上げてきたわけですが、これからスタイルを提案するという意味においては、黒は役目を終えたのです。アナ・ウィンターもカラフルな装いをしていますよね。彩り豊かな色彩の中で、どのような新しいデザインを打ち出していくかということが、今のファッションデザイナーの仕事ではないかと思います。ですから雑誌としても黒ではなくカラフルなものを取り上げる。カラフルなものを取り上げるから、逆に黒を特集するという編集の仕方もあるかと思います。
2点目ですが、ブランドがある女性像を打ち出す。これも90年代までは、そのような枠組みでとらえることができたと思います。たとえばコム・デ・ギャルソンの穴のあいたセーターを着て、西洋の伝統的な美しい女性像ではなく、強い少年のようなイメージを打ち出していく。しかし現在は、ブランドが打ち出す女性像を追い求めるというよりも、もっと自分の好みにあったスタイルを自分の感性でセレクトしたいという要望が強いように思います。ビームスやユナイテッドアローズといったセレクトショップが若い子たちにとても人気がありますが、セレクトショップの歴史自体は古く70年代に始まり、90年代に爆発的にブームとなります。セレクトショップは、好みの服を集めてきて編集して見せてくれます。いろいろなブランドから、ちょっといい感じの服をセレクトしてくれる。本来は雑誌がそれをやってきたはずなんです。いろいろなブランドの服を取り上げながら、あるシチュエーションで、ある女性の姿を提案するというわけです。消費者の好みが細分化してきている現代では、一つのブランドがある女性像を打ち出してリードしていくというよりも、流行に寄り添う形でセレクトショップが台頭してきているのではないでしょうか。
質問 文化論の立場で考えていくと、服をつくる人、雑誌をつくる人、着る人、抽象化すると作品論、これが服になりますし、読者論とか消費者とか、その間にメディア論の立場がある。雑誌が入っていく。こういうのは文化現象すべてにあてはまると。マンガとかも。マンガは同人誌とか消費者側かつくり手となって楽しめるという文化が、最近流行っていると思いますが、服飾について自分がつくって楽しむ、それを商品として売るという生産、消費はあるのかなと。
吉田 アニメやマンガの世界でよく言われる「二次創作」のようなものが、ファッションや服の世界でもあるのか、というご質問ですね。
平芳 今日この会場に、自分で布を切って縫って作った衣服を着てきた方はおそらくいらっしゃらないのではないかと思います。現代の衣服は高度に産業化されてしまっていて、自分で服を作る機会がない。服をほしいなと思ったらまず店に行ってみるか、ファッション雑誌でどういう服があるのかを確認するところから始まります。つまり、作るのではなく選択して購入する。そういう行動に限定されてしまっています。そこで、自分で布地を選んで形をデザインする、すなわち<作る>喜びが再発見されることはあると思います。そのなかで、ブランドが打ち出すファッションだけではなく、もっとこんなお洒落がほしいという一人の女の子のファッションへの思いをすくい上げるような試みが、今の日本のファッション界でも少しずつ起こっています。「ヴォーグ」が取り上げるのはパリコレクション、ミラノコクション、有名なファッションデザイナーがデザインする服です。そしてコレクション会場に入れるのは、上流の顧客かファッション雑誌の編集者といった一部の人です。しかし例えば神戸で十年ほど前から開催されるようになった神戸コレクションでは、モデルも読者モデルをしているような人たちを採用して、会場にもチケットを購入すれば誰でも入ることができます。そしてモデルの着ている「あの服いいな」と思ったら、実際に購入することができる。雑誌とタイアップもしています。ファッションデザイナーがつくりだすものを、そのまま購入するのではなく、自分の好みの服をもっと買いたい。そのような要望が高まった時代に出てくるのが、セレクトショップであったり、生地を選んで自分で服を作ることであったりするのでしょう。現代だからこそ、<服を作る> ことも創作行為として新たな価値づけをなされるのではないかと思います。
吉田 本日の映画は「ファッションが教えてくれること」という邦題だったわけですが、まさにファッションから実に色々なことを教わったように思います。どうもありがとうございました。
司会 本日の映画では最先端のファッションについて学びましたが、対談ではファッションの文化や歴史という視点から様々なことを教えていただいたと思います。平芳先生、吉田先生、どうもありがとうございました。
Copyright © 立命館大学 All rights reserved.