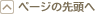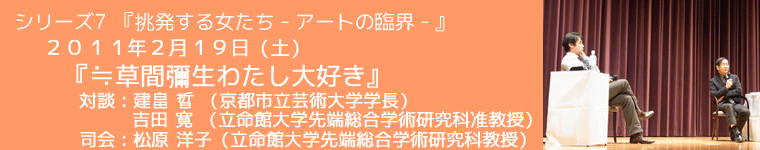
 司会
これから対談に移らせていただきます。講師のお二人をご紹介します。建畠晢さん。京都市立芸術大学学長でいらっしゃいます。吉田寛さん、立命館大学大学院先端総合研究科准教授でいらっしゃいます。これから今回の映画について。草間彌生の人と、作品、芸術家としての活動について存分にお話いただきたいと思います。最後に皆様方からの質問の時間をとっておりますので、よろしくお願いいたします。
司会
これから対談に移らせていただきます。講師のお二人をご紹介します。建畠晢さん。京都市立芸術大学学長でいらっしゃいます。吉田寛さん、立命館大学大学院先端総合研究科准教授でいらっしゃいます。これから今回の映画について。草間彌生の人と、作品、芸術家としての活動について存分にお話いただきたいと思います。最後に皆様方からの質問の時間をとっておりますので、よろしくお願いいたします。吉田 前回[マリア・カラスの上演時]に引き続きまして、登壇させていただきます、吉田寛です。今回は草間彌生がテーマということで、対談の相手役として、京都市立芸術大学学長の建畠晢さんにお越しいただきました。建畠さんと私が出会ったのはもう15年くらい前で、そのときは先生と生徒という関係でした。当時多摩美術大学の教授であった建畠さんが、私がいた東京大学の駒場キャンパスに講義に来ておられたのです。建畠さんは草間彌生というアーティストを語る上で、現在の日本でもっとも重要な人物であると私は考えておりますので、本日お呼びできたことはたいへん幸せなことだと思います。どうかよろしくお願いします。
まずは建畠さんから自己紹介をしていただきつつ、草間さんとの出会いやつながり、これまで一緒にやられてきたお仕事などについて教えていただけたらと思います。私的な一個人として、またキュレーター(学芸員)として、色々あろうかと思います。草間さんとの出会い、どのような企画の中でどのようにプロデュースをされてこられたのか、また人間としての草間彌生のことも、教えていただければ嬉しいです。
建畠 京都芸大に来たのはこの1月なんですが、国際美術館に勤めてる時に、草間彌生さんとの接点が生じたんですが、その後、大学院に出ていて、吉田さんとは東大で授業をする時に出会ったと思います。最初に草間さんを見たのは、彼女が16年間のアメリカ生活を終えて日本に帰ってきた時、銀座の小さな画廊でコラージュの個展を開いたんです。草間さんは名前を知っていました。ニューヨークのスキャンダルの女王として、いろんな赤新聞とかからニューヨークでの彼女のスキャンダラスなことが伝わってくる。半ば揶揄するような、顰蹙を買うような、ニューヨークで最後の頃、乱交パーティのイベントを開くんです。そういうことをやっているうちに飽きられてしまう。ニューヨークでも画廊がつかないし、帰ってきた時は、尾羽うち枯らして売れなくなった日本に逃げ帰ってくるような意地悪な報道がされていて、僕もその程度の知識しかなかったんです。小さな8畳くらいの画廊でコラージュの展覧会を見て、片隅に草間さんがいたと思うんですが、怖いから声をかけなかったんですね。
コラージュを見た時に、この作品は今、中心的な部分は松本の美術館と東京都現代美術館に収蔵されていますけど、それを見た時に驚愕したんですね。驚異的な天才だと確信しました。その後、私は美術館に移ったんですが、新聞報道も出ない、こっそりした展覧会だったんですが。学芸員になった時、20代後半の大阪の売れない学芸員ですから、そんなに影響力があるわけではないんですが、草間さんを正当に評価するのは私の責任だろうと、周りに草間さんのことをいろいろといていたんですね。草間さんはエキセントリックな作風で。グレイトじゃないよ。インタレストとグレイトがあるとしたら。なんでそんな大げさにわめくんだと。国際美術館で作品を購入したり、グループ展とかやったんですが、世間は振り向いてくれない。いくつかの画廊が注目してくれて、特にカステラー二画廊は草間さんの展覧会を継続的に開いてくれて。
草間さんをどのように位置づけるか。正当に紹介するということですが、僕がそんなことを実現する力がない20代の学芸員の時に、ヴェネツィア・ビエンナーレの日本の代表にしよう。もう一つは、ニューヨークの近代美術館で個展を開く。モマですね。僕がモマとは関係もなく、ヴェネツィア・ビエンナーレのコミッショナーを頼まれたわけでもない。面白いエピソードがいっぱいありましたね。草間さんの家のアトリエに作品を借りにいったんです。グループ展に1点だけ出そうと思って。都内の集荷するトラックを草間さんのアトリアに乗り付けて、ヤマト運輸の担当の人に、この作品を運んでほしいと電話をかけていたんですよ。15分くらい待っていたら、都内で10人くらいの人の作品を載せないといけないのに、草間さんの作品が一杯乗っているんです。1点だけ借りるはずだったのに草間さんが、全部持っていけと。自分のことしか頭にないから。いよいよ展示する。美術館では照明した時に草間さんか来たんです。「私の作品は私が照明するわ」というので、任せてアシスタントをつけて他の展示の照明にかかっていたんです。2、3個スポットをつければいいのを、20くらいつけている。回りから見ると草間さんの作品だけが、さん然と輝いている。「これではバランスとれないですよ」というと「まだ足りない」といってだめなのね。つけすぎちゃって、ライティングから煙が出始めたんです。そこまでやらないと止まんないのね。「草間さん、火事になりますよ、作品が燃えちゃいますよ」「そう」。でもさん然と輝いているような展示をしていました。奇妙なエピソード、一杯あるんですけど。
 吉田
1993年の第45 回ヴェネツィア・ビエンナーレ、これが一番大きな出来事ではなかったかと思います。日本代表として日本館で草間さんの個展をやるわけですよね。そのときのコミッショナーが建畠さんでした。
吉田
1993年の第45 回ヴェネツィア・ビエンナーレ、これが一番大きな出来事ではなかったかと思います。日本代表として日本館で草間さんの個展をやるわけですよね。そのときのコミッショナーが建畠さんでした。建畠 無名の学芸員のところに、どういうわけか、外務省からコミッショナーをやってくれと。やったぜと思って。その頃、ヴェネツィア・ビエンナーレでは日本館は個展をやっちゃいけないというルールだったの。個展じゃないと、できないですね、あの作品は。グループ展はありえない。1年目は諦めて、それでもすばらしい作品で、外務省や国際交流基金と交渉して個展をやるべきだと。草間さんの名前を出さないで。他のアメリカ館もフランス館やドイツ館も個展をやっているだろう。ようやく個展をやっていい、ということで、おずおずと草間さんの名前を出したら、「えっ、でも精神病院に住んでいるんでしょう?」と。偉大さを説いて草間さんと一回会ってみましょうと、講演会につれていったんです、草月会館があって。そしたら草間さんが、そこでニューヨークのセントラルパークでは裸のハプニングですね。ヒッピーの若者たちを裸にして、自分が先頭に立って警察官から逃げ回るということを延々と得意気に話すわけですよ。高級官僚の人が真っ青になって「こんな人をつれていくんですか?」「もう新聞発表終わっちゃったから、これを取り下げたらちもっとスキャンダルになりますよ」。持っていったんですね、草間さんを。それが幸いにして高く評価されて、一挙にニューヨークの近代美術館につながったという、そこで僕は初期の目標を達成したので、その後、いろんな人が興味持ってくれたから、僕一人が草間、草間ということもないだろうと。こういう機会で草間さんについて話すチャンスを与えていただくのは、うれしいことなんですけど。
吉田 草間彌生は1970年代にニューヨークから逃げるように帰ってきたわけです。しかし当時の日本でも、草間と言えば乱交パーティをやるようなスキャンダルの女王、という一面的な報道がされていました。その草間さんが、アーティストして世間にきちんと認知されるようになったきっかけ、言い換えれば、今日の映画のような視点が可能になったきっかけが、ヴェネツィア・ビエンナーレであると私は考えていますし、またすでにそのように言われているとも思います。その意味では建畠さんが彼女を見出した、アーティストとして舞台にのせた、そう言ってもいいかなと思います。
さて、そのあたりの経緯を、別の角度から、多少核心に迫りつつ、お伺いしましょう。草間彌生の創作のキーワードとしてしばしば言われる三つ(プラス一つ)の言葉があります。第一が「オブセッション」つまり脅迫(観念)。第二が「アキュムレーション」。これは「集積」あるいは「積み上げる」という意味です。映画の中には文字通り「集積」というタイトルの作品(『集積 No.1』、1962年)も出ていましたね。ソフト・スカルプチャー(柔らかい彫刻)の一シリーズとして作られた、白いペニス状の詰め物で覆い尽くした椅子に、そういうタイトルが付いていました。そして第三が「レペティション」つまり反復です。そしてこれら三つ(脅迫/集積/反復)の上になりたつものとして、「オブリタテーション」、つまり「自己消去」があります。これは際限なく網の目や水玉を描き、反復することで、その(行為の)中に自己を消し去ってしまう、そういう契機・過程です。これら三つ(四つ)を草間彌生のスタイルを説明する基本的キーワードとしてまず確認したいと思います。その上での問いです。ミニマル・アートがその典型ですが、モダン・アートの中では「反復」や「集積」は比較的よく見受けられるスタイルですよね。他方で、「脅迫(観念)」は草間さんのオリジナルなスタイルと言えるかもしれません。もちろんこれは、草間さん自身の精神的な病、幻視経験や幻聴経験といった体験の問題とも関係してくると思いますが。建畠さんは、草間彌生の創作をその他の現代芸術作品一般から分けるものは何であるとお考えでしょうか?
建畠 よく天才と狂気は紙一重というふうにいいますけど、草間さんの精神的な障害が何であるか、彼女の抱えていらっしゃる精神科の先生がヴェネツィア・ビエンナーレについていらしたので、聞いたんです。「私、言わない」と。「どうしてですか?」「病名をつけて安心してしまってはいけない。類型化してはいけない」と。医者は現象学の発祥の学問と言われていますから対象を観察して、類型化してそれに治療の方法を結び付けると思ったんだけど、障害のパターンにあてはめることをしないといったで、オブセッションが、どこから来るのか、幼児の時の経験によるのか、もって生まれた気質なのか。よくわかりませんけども。脅迫と集積と反復は一つに結びついて、オブセッシブな内的な恐怖感があって、それを解消するために情動反復の方法をとる。簡単にいうと、水玉の女王といわれるように、ネットドット、水玉と編み目が重なっていますから、その方法で、小学校の時のドローイングから今日まで一貫しているんですね。編み目の水玉の反復の方法だけで、これだけ立体から映像から、絵画に至るまでの芳醇で、バリエーションが生まれるのは信じがたい気がするんですが、単純さが豊かなバリエーアョンに結びついていく。オブセッションというのは内部に抱えた情動が繰り返しを生むんだけど、それがなぜ自己消滅に結びつくのかということは、本人の言葉だと、子どもの頃からファルシネーション・幻覚の恐怖に襲われて、今でも絵画療法に取り入れられていますけど、恐怖の中核のイメージを自分自身で絵というものに可視化することによって恐怖の核心に飛び込むことによって心理的抑圧を解消していくという。これは多分、精神医学の世界では一般的に認められている方法だと思うんですが、普通は逆に怖いイメージから目を背ける、思い出さないようにするんですが、彼女は恐怖の中心に飛び込んでいって、それを夥しく反復し、その恐怖のイメージを花柄で増殖していくのは、子どもの頃に自分に襲いかかってくるものとしてあったので、それを埋めつくして、その中に自分自身を解消していく。消滅していくことによって恐怖から逃れるということのようですね。本人が語っているので。草間さんはナルシシズムの強い人で、自己顕示欲の強い人で、自己主張も強い。草間さんの場合は有名になる、皆から注目される。あくなき監視。世間が、どう評価しているか。天才というのは、一種の聖性を帯びているんだけど、聖なるものと俗なるものは紙一重ではなく、一つの紙の両面なんです。これは、個人的に知っている草間さん以外に、ピカソとか、俗臭ふんぷんたるところ、限りなく純粋な無垢な二面性がある。それが一つに結びついている。草間さんはその典型ですね。
吉田 そうですね。草間さんの中には、自己消滅・自己否定という側面とナルシスト的側面──今日の映画のタイトルである「わたし大好き」に象徴されます──があって、それらは通常は矛盾するような気がしますが、どうやら両面性として共存しているようです。この両面性を理解する上で重要だと思われる言葉が彼女の自伝(『無限の網──草間弥生自伝』、作品社、2002年)の中にあります。私はペニス(男根)をかたどったソフト・スカルプチャー(柔らかい彫刻)をたくさん作ってきたし、ニューヨークでは派手に乱交パーティなどもやってきた。だから、私はとてもセックス(男根)が好きな女だと世間から思われているが、実はそうではないんだ、自分はむしろセックス(男根)が怖いんだ、と告白しているのです。
「普通、芸術家は自分のコムプレックスをそのまま表現することはしないのだが、私はコムプレックス、恐怖感を表現の対象にしていく。ファルスみたいなあんな長くて醜いものが入ってくるなんて、考えただけで怖い。だから、男根をいっぱい作る。(…)作って、作って、その表現の中に埋没していく。それが私のいうオブリタレイト、つまり「消滅」ということなのである。」(同書、42頁)
ここから分かるのは、草間彌生にとっての創作が、恐怖を癒すこと、ある種の「治癒」の過程である、ということです。彼女はこうも言っています。
「とにかくセックスが、男根が恐怖だった。(…)それだからこそ、その形をいっぱい、いっぱい作り出すわけ。たくさん作り出して、その恐怖のただ中にいて、自分の心の傷を治していく。少しずつ恐怖から脱していく。私にとって怖いフォルムを、何千、何万と、毎日作りつづけていく。そのことで恐怖心が親近感へと変わっていくのだ。」(同書、40頁)
自分が怖いと感じる、恐怖の対象を避けたり隠したりするのではなく、むしろ、どんどん、たくさん作っていく。反復して作り出していくことで、その恐怖を克服していくと。これは通常言われるような「自己表現」としてのアートとは根本的に違う、「自己肯定」としてのアート、つまり自分が自分であるために、怖さを克服するために、作っていくしかない、そういうタイプの創作なのかなと思いますね。
建畠さんは先ほど「ナルシシズム」と言われましたが、彼女は本当に「自分が大好き」で、映画の中でも、世間から注目・評価されて嬉しい、大きな賞をもらって嬉しい、とあけすけに語っていましたね。自分の絵は素晴らしい、詩も素晴らしい、こんなすごい詩は今まで読んだことはない、とまるで子どものような自己称賛の言葉がたくさん出てきました。とにかく他人の目を気にする。浮き沈みが激しかった人として、自分を大好きにならざるをえなかった部分がある。それは徹底的に「俗」な部分ともいえます。しかし一方で、彼女にとって創作は自分の生を肯定する作業なのです。それはゼロからプラスに持っていく作業というより、マイナスをゼロに近づけるための努力、つまり自身の生存にとって不可欠な過程であると、そういうイメージで私は理解しています。「自分が大好き」という言葉だけを捉えたら、単に「ナルシスト」かもしれませんが、通常の意味のナルシストではなく、作らないと、作り続けないと、生きていけない、という意味で、もう少し「生存」に関わるような、マイナスをゼロに持っていくためのナルシシズムです。その点で草間さんの創作活動は「普遍性」を持っている、さらに言うなら、あるいは──「俗」とは対極にある──「聖」のイメージを帯びてくる。
建畠 それはね、彼女の制作の出発点は、ほとんどお母さんに捨てられてしまったんだけど、アメリカに行く時に。いくつかドローイングが残っています。お母さんの肖像画を大量に描いていたんですね。禁じられながら、こっそり描いていたんですけど、それは恐怖から逃れるためのオブセッションにかられて、オブセッションが、かもしだす恐怖を解消するために、やむにやまれず大量に1日中、絵ばかり描いてたいというほど大量に描いたんですね。明らかに自分を解放するためであって、自己表現として自己を主張していくこととは違ったモチベーションだと思うんですよ。それは50枚のドローイング、今、100点のドローイングをつくっていますけど、それを腱鞘炎になりながらあくなく、つくり続けていくというのは、一般的な人の自己表現、表現衝動ではなく、そうせざるをえない、心理的な負荷を解消するためには。それがたまたま絵画であった。アートに結びつかない表現であれば貧乏ゆすりかもしれない。それがアートというのは我々にとって幸いだったけども。 そういう衝動を抱えた人、狂気と天才は分けて考えているんですけど、たまたまそういう人物が反復の対象を美術に向け、たまたま天才であり、たまたまおそらくは知能指数をはかってはいませんが、驚異的な知能指数に恵まれていた。それは我々にとって幸いだったんですが、彼女自身はマイナスから解放されるために、やむをえず情動反復的に同じことを繰り返していく、それは多分、小学校から今日まで変わらない。
性的な問題ですが、ファルス、男根のクッションを彼女はつくり続けてもいるわけですけども、映像の中にもありましたが、クッションの入ったソファの上に彼女が全裸で横たわっていることがあって、これはフェミニストの人が、よく解釈するんですね。女性を支配する男根を自らの手につくりだして、その上に裸体で横たわることで男性原理に仕返しするということをいったり、京都の近代美術館に所蔵されている、これは傑作ですが、「ラダー」という梯子があって、梯子のステップに男根が一杯入っているんですよ。それにハイヒールが二つおいてある。これも女性の上昇志向のステップの上にそれぞれに男性が支配している。それを先の尖った鋭いハイヒールで踏み潰しながら登っていくプロセスだと、フェミニストたちは解釈する。彼女ははっきり「フェミニストは敵だ。フェミニストほど自分を苦しめてきたものはいない」といっていて。それはお母さんとの微妙な関係もあったようですが。よく見るとペニスを踏み潰しながら、ステッフのラダーを上昇していくハイヒールは、よく見るとステッフから外れ、半ば落ちかけていて、しかも横に捩じれていたり、威勢のいいハイヒールじゃないんですね。ファルスの問題というのはフェミスト的に男性原理に対する女のヒロインというのはちょっと疑問がありますね。それを読むと、きれいに、草間彌生さんの作品は読めてしまうんです。ただね、彼女は、いくつかのオブセッションがあるんですが、食物のオブセッションとか、性的なオブセッションとか。セックスに対する恐怖感があって、乱交パーティのイベントでは自分はセックスをしなかったと。
吉田 食に対するオブセッションについてはいかがでしょうか。「セックス・フード・オブセッション」をテーマにしたインスタレーション(1964年)がありましたよね。フード・オブセッションは、パスタやマカロニのかたちの反復・集積なのですが、草間さんの創作においては、セックスと食(フード)に対する恐怖・強迫観念がしばしばセットで登場します。セックスにしても食(フード)にしても、食べたり、戻したり、つまり体内に入れたり出したりする行為、しかも身体的な快楽と苦痛を同時に味わうような行為ですよね。
建畠 食べることとセックスすることは人類の生存の条件といえば、動物的な根源にあるものといえなくはないですが、ただね、そこは疑問ですね。きれいに解釈されてしまいすぎるんで、彼女はポップ・アートへの転換点を用意した、ニューヨークで。時代的にも文脈的にも、ミニマル・アートからポップ・アートへの時期、ほとんど同じ時期に発生しているんですね。ミニマル・アート、機械的な反復、システマティックペインティング、その方法と日常的なオブジェとして使うことの中に、椅子があったり、梯子があったり、女性の化粧台があったり。その中で我々にとって卑俗的なものでありながら、大きな意味のあるということの中でのマカロニだったと思うので、フードオブセッションというのを、生存の条件ということに、かこつけるのは、どうも。
吉田 日常的なものを素材にするポップ・アートの文脈だろうということですね。
建畠 聖なる芸術にマカロニがいっぱい張りつけせけてあると、笑いますよね。そういうふうな思いつきではなかったと思います。
吉田 「自己肯定」のための創作、「治癒」としてのアート、という話に戻しますが、最近「アウトサイダー・アート」(精神疾患者や幻視者など、正規の美術教育を受けていない人たちが作った芸術作品)に注目が集まっていますよね。草間さんの作品もすでにアメリカに渡る以前に、式場隆三郎や西丸四方といった精神医学者から注目されていました。式場は山下清の才能を発掘して、プロデュースした人物として知られています。当時は、日本の精神医学者が、精神病患者が作るアートに独自の価値を見出し始めた時期だったのです。ところが、その後、日本のアウトサイダー・アートは「教育」「福祉」の方向に向かってしまい、アウトサイダー・アートの作品を「アート」として正当に評価する気風が薄れてしまった、とよく指摘されています。しかしその間、草間さんはいわばアメリカに逃げていて、アメリカでモダン・アートの正統的作家として活動できた。もっとも、本格的なアウトサイダー・アートの展覧会として日本で最初に開催された「パラレル・ヴィジョン」展(世田谷美術館、1993年)では草間さんの作品も出展されましたので、今ではアウトサイダー・アートとしての評価も可能なのかもしれませんが、少なくともアメリカの評価はそうしたものではなかった。そして、それは草間さんにとってとてもいいことだったのではないか、と私は思うのです。つまり、そのまま日本にいたら、アウトサイダー・アート──福祉や障害者支援、心のケアのためのアート──の文脈で(のみ)評価されていたかもしれない草間さんが、ニューヨークで活動したことで、モダン・アートの中心に位置づけられ、抽象表現主義からミニアル・アートへの歴史的転換に寄与した、ということです。ここには日本とアメリカの風土の違いもあるのでしょうか。
建畠 もちろんアメリカのニューヨークはアウトサイダー・アートを評価する意味でも先駆的なまちで、アウトサイダー・アートの専門店があるんですね。かなりの値段で商品として流通もしているんですよ。草間さんは日本ではアウトサイダーとして幼少で評価されてニューヨークに移ったんですけど、ニューヨークではアウトサイダーという文脈での評価ではなかった。最初からネットペインティングが、ミニアル・アートの表現主義的な方法を引き受けつつ、無機的な表現に向かう時代の流れの中に位置づけられたので、モダニズム・オートロックスというんですけど、アウトサイダーという位置づけの中で出てきたわけではない。パラレル・ヴィジョン、ロサンゼルスのカウウンティ美術館でタックマンという人かキュレーションして立ち上げて巡回したんですが、タックマンは「天才と狂気というのはつながっている」と言うんですね。それを証明するような展覧会なんです。多くの賢妻たちが、シュールレアリストたちがヨーロッパでは精神病院に通うんですね。精神病患者たちの作品のコレクションを見たり、そこで制作したりする。そういう中で多くのシュールレリストたちは狂気が持っている表現の富を手にして、そして日常に帰ってくるというんだけど、実際には帰ってこられない。多くの悲劇、自殺、離婚とかになる。
その文脈で考えると、草間さんの狂気というのは、精神病理というのは、彼女の天才そのものであるということになるんでしょうが、そうであるとすれば、僕は違う考えを持っていて、確かにアウトサイダーの作品は面白いんです。3歳、4歳の子どもが描く絵は劇的に面白いんですよ。そういう天才たちは、5、7歳になるとマンガのような、目から星が出ているような類型的なパターンに陥ってしまって、先生も親も、がっかりして「もっと自由に描きなさい」と。それはむりなんですよ。成長の過程で、必ず類型化していく。そこを踏まえないと、その先の自由もないという。子どもの絵も精神障害者の絵も、1000年前の絵も、今日の絵も、同じように面白い。時代が、そこに反映していない。それはすばらしいことは認めますよ。すばらしいんだけど、美術史の現象の展開の埒外にある。草間さんとかゴッホとか、狂気をはらんだ天才は、美術史の転換点の中で先導的な役割を果たすし、それまでの美術史を全部引き受けていく。単に独創的なだけではなく。草間さんがニューヨークに行こうというのも、そうなんですよ。
吉田 モダニスト(近代主義者)ということですね。
建畠 天才は、いるべきところを知っているんですよ。日本に、そのままいたら、だめだ。ニューヨークのモダニズムの現象が最も機能しているまちのど真ん中に飛び込んでいって、彼女はエンパイアステートビルの上から周りを見回して「私はこのまちを支配する」といったんですね。明らかに歴史の中にいる自分を意識した発言です。その意味では僕は狂気そのものが天才であるという文脈で草間さんを解釈するのは、ちょっと片手落ちだという気がしますね。
吉田 それではフロアとの質疑応答に移りますが、皆さんいかがでしょうか。
質問 作家は自己実現と創作意欲のために絵を描くわけですね。草間さんが自己実現のために絵を描いておられるのか、表現ということで描いておられるのか。
建畠 おびただしい量の作品を今日まで制作され続けていて、その意味では多作の作家なんですね。それは、一つは自己実現というより、自己解放だと思いますね。襲いくるオブセッションから解放されるため描いていたし、「絵を描いてないと心が落ちつかない」といっていましたね。精神の安定を得るために、つくり続けないといけない。当然、多作になっていくだろう。それは、ある人にとっての自己実現であり、社会的な評価をえることもあると思いますが、彼女の中にも、そういうことに対する関心は強いですけど、でも、あの多作なものを動かしている情動は、自分自身のやむにやまれぬ、そうでないと精神的な負荷が解消しなということが第一だと思います。
質問 草間彌生の作品は、21世紀を越えてでも残る作品だと思われますか?
建畠 僕が、ですか? 草間さんの、60年前後につくられたネットペインティングとアキュムレーションシリーズの数点、今、ワシントンのナショナルギャラリーに収蔵されている数点の作品に関しては、20世紀の永遠のモニュメントだと思いますね。あれに匹敵する絵画は、僕は、マークロスコ、バーネット・ニューマンの数点があるだけで、そのクオリティに到達しているものは、ポロックですら草間のクオリティに到達していない。その前に立つとわかりますが、居住まいをただすという、粛然たる思いにさせられます。今残っているものは、そんな数多くない。3、4点の作品において草間さんはモダニズムの最もトップに属する画家として残っていくだろうと思います。今の作品、ドローイングのシリーズも含めて、すばらしいと思うし、今なおクオリティの高い作品をつくっていますが、1959〜61年の間のネットペインティングはモダニズムの金字塔であると僕は思っています。
質問 映画の中で草間さんが死と生についての作品をつくられていたと思いますが、それは一貫して人生の中でつくられてきたものなのか。草間さんは自殺を幼少の頃、考えていたと。死への恐怖を作品の中て表していたということでしょうか?
建畠 草間さんが死を恐怖していたかどうかは、よくわかりませんが、自殺衝動はずっとあって、最近でも未遂事件を何回か起こしていらっしゃるんですが、実際に逞しく生きていて、自殺衝動はどういうものなのか、ほんとに実行して病院に運び込まれていますから、死への恐怖心と自殺衝動は彼女の中に蟠っていると思いますが、性と死というのは、もう一つは彼女はビジオネール、幻視者であって、アナザーワールド、異界のイメージ、宇宙のイメージだったり、死後のイメージだったり、異界のイメージを求める、そういう幻視者としての、異界としての死は作品の中に出ているように思います。個別にみないとわかりませんが、死というものが、すべての終焉であったり、沈黙であったり、暗黒であったりということより、その先に開かれているアナザーワールドへの想像力として彼女の死というのは、あるのではないかという気がしますね。それは正直なところ、彼女にとって自殺衝動が、どのようものかは、はかりしることはできませんので、彼女に、なりかわってお答えすることはできるわけはないんですが、異界への同定というのが、彼女の創造力のような気がします。
質問 高齢化に伴って生とか死への作品が増えたというのではなく、一貫して草間さんの作品に死と生について作品があったということですか?
建畠 ドットの中に自分を証明していくというのは、すでに小学校の頃、描かれているわけですから、自己消滅も一種の生と死にかかわる問題であるとすれば一貫していると思いますね。
吉田 先ほど「聖」と「俗」という話が出ましたが、死を含めた「異界」という点からも、草間さんの存在はやはり巫女や聖女といった宗教的なイメージと重なって見えてきますね。
質問 ダイレクトに真っ白紙の上に、いきなり全部というのは、ずっとああいうスタイルで描かれているんでしょうか。初歩的な質問ですが。
建畠 グッドクエェションです。天才は、身近にいないですね。身近にいないから天才というのでね。歴史上、天才は何人もいますけと、天才を目の当たりにしているわけです。生きている天才を。天才は秀才の延長上にいない。秀才がいますよね。100人に一人くらい。1万人に一人、大秀才とか。その延長線上に天才がいるんじゃないんですよ、天才というのはね、現象なんです。地続きにいない。どういうものを天才というか。つくづくとわかるは、「語るピカソ」、ブサッサイという写真家が書いています、天才の条件があって、ケチとか、家庭的に希薄とか。美術家としての条件は、現象面でいえば習作がない。エスキースとか、習作がない。
吉田 練習のために作ることがない、ということですね。
建畠 試行錯誤かない。どんな新しいことをやっても。ピカソにもいえますけど。ドローイングは残されていますけど。一挙に本質ができちゃう。逡巡したり、試行錯誤したりしない。横で見ているといい加減に思えるくらいです。思いつきで、やっちゃう。もっと真剣に考えてくれといいたくなるくらい。下書きをせずに直接描く。逡巡がないんです。これは天才に共通している。大秀才で試行錯誤し、10年も20年も見つめていって偉大な仕事をするのは天才ではない。天才は試行錯誤がない。思いつき、恣意性、オブリタリティがある。恣意的なもの、勝手気儘に思いついた、いい加減な発想みたいなものが、宇宙的な絶対の必然性になる。恣意性が必然性に一挙に結びつくのを目の当たりにするのは驚愕ですよ。ドローウングもすばらしいです。すごく成功したものと、そうでないものはない。だけど逡巡がない。一挙にそこに入っちゃう。廃棄する作品がない。ごみ屑の山になることがない。彼女は廃棄する作品がない。50枚のドローイングも、50枚のキャンバスを用意して50枚できちゃう。それは全部、共通している。逡巡することなく一挙に描き始める。小さなドローイングをしたり、テストケースでやるということはない。
吉田 その点で、現在美術の作家の中でも草間さんは例外であるということですね。
建畠 そうでしょう、極めて例外的でしょうね。習作をたくさん描くのは悪いことではない。油絵なんかは描き直すことはできますけど、彼女はしないですね。一挙に、早いですよ。すごく。横で見ていると、もっと真面目にやってくれと。悩んで煮詰めて1晩くらい徹夜してくれといいたくなっちゃう。ある仕事をお願いした時、ミラーボールを海に浮かべる作品ですが、草間さんが「予算いくらなの?」「ないんですけど」。助手の高倉君に「ミラーボール2000個、海に浮かべておいて」と。こっちは展覧会で悩んでいるわけでね。草間さん、一晩くらいアイディア考えてください。5秒ですね。実際に、その作品が横浜で実現した時に。
吉田 それは2001年の横浜トリエンナーレですね。
建畠 ほんとに完全無欠な光景が目の前に実現したのを見て、天才というのは、こういうもんだと思いましたね。恣意性が必然性に結びつく。ドローイングについても、それは言えることだと思います。
吉田 このシリーズには「アートの臨界」という副題が付いていますので、毎回最後に、今回の映画に即して「アートの臨界とは何か」を一言ずつ言うようにしているのですが、今日はそれは不要だろうと思います。この対談のすべてが「アートの臨界」に関する話でしたので。
さて次回は3月5日に、ファッション雑誌『ヴォーグ』の編集長であるアナ・ウィンターのドキュメンタリーを皆さんと一緒に見たいと思います。
建畠 一つだけ、やめてしまった美術館を宣伝するのもへんですが、国立国際美術館で来年1、2、3月に草間彌生の新作のペインティング展をやります。草間さんの50点のドローシイングのシリーズの後につくられたペインティングのシリーズで、第二のピークといってもいい、すばらしい作品が生まれつつあります。2012年1、2、3月、草間さんに興味がある方には、ぜひごらんいただきたいと思います。
吉田 それでは建畠先生、どうもありがとうございました。
司会 建畠さん、吉田さん、どうもありがとうございました。ではこれで終わります。以上をもちまして公開講座「シネマで学ぶ人間と社会の現在」を終演とさせていただきます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。
Copyright © 立命館大学 All rights reserved.