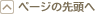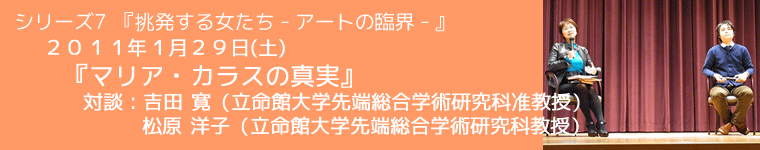
 松原
シリーズ7「挑発する女たち―アートの臨界」を企画した、立命館大学先端総合学術研究科教員の松原洋子と申します。今日の対談のお相手、吉田寛さんは美学、とくに音楽学の専門家です。映画の余韻を味わいながら、これから話を進めていきたいと思っています。
松原
シリーズ7「挑発する女たち―アートの臨界」を企画した、立命館大学先端総合学術研究科教員の松原洋子と申します。今日の対談のお相手、吉田寛さんは美学、とくに音楽学の専門家です。映画の余韻を味わいながら、これから話を進めていきたいと思っています。私はオペラについて全くの素人です。女性アーティストに関する映画を探していくうちに「マリア・カラスの真実」という作品に出会い、ほとんど名前だけしか知らなかったマリア・カラスの存在感に圧倒されました。今日は大きなスクリーンと大音響で彼女の姿と歌を堪能できて、企画者冥利に尽きます(笑)。
この映画には、プリマドンナとしてはもちろん、一人の人間としての生涯もつぶさに描かれています。描写については異論もありうるでしょうけれど、それでも胸に迫るエピソードがたくさんありました。
マリア・カラスというと、カルメンのように華やかで自己主張が強そうなイメージがありますね。映画でもビゼーの「カルメン」の前奏曲を聴きながら、カラスが表情やちょっとした仕草だけで、カルメンの世界に観衆を引き込んでいく見事なシーンがありました。その一方で、カラスはベッリーニの「ノルマ」で高い評価をうけ、彼女自身も気高く自己犠牲的なノルマに特別な思い入れがあるとインタビューで語っていました。歌手としての幅の広さをうかがわせます。また、ノルマはソプラノの難役で、20世紀以降カラスの登場まではほとんど上演されなかったそうですね。彼女は、オペラの歴史においてどのように「特別な人」だったのでしょうか。
吉田 立命館大学先端総合学術研究科教員の吉田寛と申します。本日はよろしくお願いします。 私の専門は美学・芸術学ですが、2009年に『ヴァーグナーの「ドイツ」』という本を出させていただきまして、その中でヴァーグナーの音楽劇──彼はあえて「オペラ」と言わないのですが──が当時のドイツの人々や社会、政治とどのように向き合う中で作られたのかということを書きました。
音楽は学問の対象として捉えた場合にすごく特殊な領域で、授業をしていても聴講している方々の方がはるかに詳しいのです。音楽ファンの知識や情報収集力は本当にすごくて、研究者も太刀打ちできないほどです。一つの曲をありとあらゆる演奏家の録音で聴いていたり、一人の指揮者の録音を全部聴いていたりする人がざらにいます。ですから──本日のこのレクチャーもそうですが──音楽研究者も「高み」に立って語るわけにはいかないのです。ですから私も研究者として、すべてを知っているというスタンスではなく、むしろ限定された知識や情報からいかにして考察を広げていくか、という方向に力を入れています。マリア・カラスについても、ここには──世代を考えても──私よりもお詳しい方がたくさんおられるでしょうが、そういう方にも関心をもっていただけるような話ができたらいいなと思います。
さて、ただ今ご質問にありました「カルメン」のシーンですが、本日の映画の中で一番美しいシーンといっていいと思います。カラスは一言も発さず、ただにこにことした表情を浮かべて立っている。そのバックにオーケストラが流れている。ですが、この映画全体を象徴するようなシーンです。その前に、カラスは「美声」ではなく「劇的真実」を重視した、という説明がありましたね。声の美しさではなく劇的真実、つまり劇におけるリアリティの方を重視した、それが他の歌手に比べて傑出していた、ということです。
オペラというのは基本的に「嘘くさい」わけですね。オペラは一応「音楽劇」とも言うのですが、劇というよりも歌を披露する場であって、登場人物の役割や心情の表現はどうしても二の次にされてしまうのです。ミュージカルもそうかも知れませんが、オペラと演劇の最大の違いはそこにあります。そうした中、カラスはオペラから「嘘っぽさ」をなくそうとした、あるいはオペラを演劇に近づけようとした。自分の役柄をきちんと内面から理解し、まずは表情を作り、それを観客に見せて、その上で初めて歌う、ということです。「カルメン」のシーンに歌は出てきません。フレーズを聴いて、表情を作り、役に感情移入する、という部分のみをカメラは映していたわけですが、あそこには、オペラの役をどのように演じるかという、カラスのキャリア全体を貫くスタンスが凝縮されています。カラスは歌手としての力量もさることながら、役者としての「演じる」才能が突出していた、オペラの歴史全体の中に置いてみてもそれは際立っていた、あるいは奇抜と言えるほど新しかった、そう言っていいと思います。
本日の映画でも言われていましたが、カラスは昔のオペラのレパートリーをどんどん復活させていくのですね。カラスが活躍した20世紀後半には、イタリアの劇場でももっぱら20世紀のオペラがかかっていました。そうした中、カラスはモーツァルトの作品やケルビーニ(イタリアの作曲家)の「メデア」(1797年)など、19世紀前半から18世紀にかけての古い時代のオペラをどんどん復活させていく、レパートリーを大きく過去に広げていくということをやった人なのです。劇の中の役に没入する彼女の力量が評価され、それまで難しいとされてきた役をどんどん引き受けていった結果なわけです。もちろんそれはカラス一人の能力や努力のみによるのではなく、指揮者のセラフィンなど周囲が作っていったもの、彼女を取り巻く世界の中で、彼女がそういう役割を期待され、それを担っていった結果である、という側面もあります。
松原 カラスの声とか、技量、演技力がそれを可能にしたのでしょうか。
 吉田
オペラ歌手の力量や個性は実に言葉で言い表しにくいので、カラスはこういう人だったからこういうことができた、と一口で説明はできません。ただその中でも、声域(声の音域)が広い──三オクターブ以上出せたと言われています──ことや、単に楽譜に書いてある通りに歌う、演出家に言われた通りに演じる、というのではなく、自分で作品を「内側から理解」して役を作っていく、自らメロディを紡ぎ出していく、という積極的な姿勢を持っていた点などは、明らかな特徴でしょうか。
吉田
オペラ歌手の力量や個性は実に言葉で言い表しにくいので、カラスはこういう人だったからこういうことができた、と一口で説明はできません。ただその中でも、声域(声の音域)が広い──三オクターブ以上出せたと言われています──ことや、単に楽譜に書いてある通りに歌う、演出家に言われた通りに演じる、というのではなく、自分で作品を「内側から理解」して役を作っていく、自らメロディを紡ぎ出していく、という積極的な姿勢を持っていた点などは、明らかな特徴でしょうか。
19世紀前半のオペラは、後の時代に比べて、歌手が作曲家を主導しながら作られていた部分が多いのですね。歌手が台本作家や作曲家と緊密に連携・練習しながら曲を仕上げていくという文化だったのです。ところがだんだん時代が下るに連れて、作曲家と歌手が完全な分業、違う世界の人々になってしまい、歌手はいわば「交換可能」、つまり作曲家はどんな歌手でも歌えるように曲を作る、という文化に変わっていきます。それ以前のオペラ文化では、まず歌手がいて、あの歌手のためのこの曲を書くのだということで作曲家が曲を作ることがしばしばでしたので、作品自体が歌手の力量に左右されるのですね。すると、そういう歌手のために書かれた曲は、その後、相当な力量を持つ歌手がいないと上演できないことになってきます。とくに、誰でも歌えるわけではない、難易度が高いアリアを含む作品は、再演されなくなることがある。今回の映画で出てきた例でいれば、ロッシーニ、ドニゼッティ、ベッリーニといった作曲家のオペラですね。こうした作品は昔の歌手の名声が今も──伝説として──残っていて、同じくらいの力量がないと歌えない、そういう人がいなかったので、何十年も演奏されていなかった。ところがカラスならばそれができる、ということで復活させたわけです。歌手が作曲家と同じくらいの地位でオペラ作りに携わっていた時代のオペラを、カラスだからこそ、20世紀に復活させることができた、ということは言えると思います。
松原 「ノルマ」もベッリーニが当時の傑出したソプラノ歌手のために書いた作品なので、それを演じられる力量のある人が20世紀には出なかったということですね。
吉田 挑戦する人がいなかったということもありますが、それだけではありません。オペラの上演は本当に大変で、オーケストラの練習も必要だし、舞台装置も一から作るわけですから、一人の歌手の都合で、やってみました、でも失敗しました、というわけにはいかない。ですから、この歌手ならいけるな、というところからスタートして、全体を一から作っていくわけです。オペラに限らず興業というのはつねにリスキーですから。それをやった、指揮者のセルフィンや劇場のスタッフは、それは「大冒険」をしたわけです。
松原 賭けるに値する力がカラスにはあって、セルフィンのような指揮者をかき立てたということなんでしょうかね。
吉田 きっと、そうでしょうね。
松原 ギリシャから一家がニューヨークに移民してきて、カラスが生まれます。その後彼女が13歳の時、お姉さん、お母さんと一緒にギリシャに戻る。そこで歌の勉強をするために学校に入り、映画にも登場したデ・イダルゴに師事します。オペラ評論家永竹由幸さんの『マリーア・カラス』(東京書籍)によると、デ・イダルゴは、アジリタという技法を駆使できるいわゆるコロラトゥーラ・ソプラノでした。カラスはイダルゴからアジリタを仕込まれ、高音での技巧的な歌唱法を身につけましたが、一方でメゾソプラノのような低い迫力のある声も出せました。ギリシャでデ・イダルゴに出会ったことが、ヴァーグナーとベッリーニを同時にこなせるソプラノ歌手としての幅の広さにつながったのかもしれません。
というのも、オペラ「清教徒」の代役を見事にこなしたというエピソードがあるからです。1949年1月8日から16日まで、ヴァーグナーの「ヴァルキューレ」でカラスはブリュンヒルデを演じた。「清教徒」はその3日後の1月19日に開演しています。「清教徒」について、イダルゴ先生はアリアなどのポイントは教えていたけど、全スコアをさらったことはなかったと言っています。それなのにカラスは急に代役に指名され、「清教徒」の全スコアを一週間で頭に入れたと。デ・イダルゴは映画のインタビューで、カラスが優秀で熱心な学生だったと絶賛していました。徹底した勉強家だったのでしょうね。
吉田 それは本日の映画でも取り上げられていましたが、カラスのキャリアの中でもとりわけ大事な瞬間、彼女が目覚めた瞬間だったと思います。「ヴァルキューレ」のブリュンヒルデは戦いの女神ですから、勇ましい声の役です。それと並行して「清教徒」の静謐な役を演じなければいけない。これは一人二役の最たるものです。ピンチヒッターとして、それをこなせたということが、カラスにとって大きな経験だったと思いますし、周りの評価も一気に高まったわけです。とくに劇場関係者は安堵したでしょうね。オペラ歌手もスポーツ選手のようなものですから、誰でも調子が悪い時があります。そこで代わりに出てきてパッとやってもらうと評価が高まる。カラスの場合は逆に、代役を立ててもらえない中で、声が出なくなった、というローマでの事件(1956年)がありましたね。いくら人気があるとはいえ、代役がいないのは心理的に相当きついと思います。繰り返しますが、オペラ歌手は、芸術家というよりも、スポーツ選手に近い存在です。毎日あちこちを移動して、コンディションも変わる中で、一回の本番でベストな結果を残さねばならない、そういう文化なのです。その中で、一回限りの場で、どうやって実力を最大限発揮するかが問われます。一方、成功しても失敗しても録音や映像は残るわけですから、後々まで語り継がれる。すごくしんどい職業ではないでしょうか。
松原 どんなアーティストでも大変ですけど、オペラ歌手というのは、全身が楽器でありパフォーマンスの素材でもあり、そこから発せられる声と演技が目的でもあったりするわけですから、とりわけ大変です。カラスにしても単にレパートリーが広いとか、何でも器用にこなせるという次元ではないのですね。「ヴァルキューレ」と「清教徒」という全く性格が異なる演目を、それぞれに演じきれた。これの離れ業で、イタリアでの評判を一気に高めたのだと思います。 ところで映画を見ていると、カラスは何カ国語も話します。イタリアでの活躍が目立つのですが、ギリシャ移民でアメリカ人としてスカラ座のプリマドンナを務めてきた。アーティストはもともと国際的ですが、中でもカラスは国際性を持った人だったのかなと思います。
吉田 ギリシャ人であること自体は有名ですが、この映画を見て、ギリシャ人であることがカラスにとって思っていた以上に大きなことであったのだということが分かりました。国籍としてはアメリカ人ですが、ギリシャ人のオナシスと結婚するためにギリシャ国籍を取った、というエピソードがありました。イタリアで活躍していた時期には、ミラノで家を買ってこれでようやく「ラ・ミラネーゼ(ミラノ女性)」になった、という話も出てきました。彼女の「居場所のなさ」とつねに表裏一体なものとしてコスモポリタン性があったように思います。
音楽家は、歌手でも楽器奏者でも指揮者でもそうですが、コスモポリタンのようにあちこち移動しているわけです。大学の研究者も「グローバル」と言われますが、音楽家はその比ではありません。指揮者でしたら普通、四カ国語くらいは話せますから。オーケストラはまず楽団員があちこち国際的に移動しますから、指揮者がオーケストラを訓練するときには、一度に多くの国の楽団員を相手にしなくてはならないわけです。ですからどの指揮者も、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語くらいは喋れます。カラスの場合は歌手ですからレパートリーの中にフランスとイタリアのオペラが含まれますし、フランスとイタリアの劇場で仕事をしていた時期もありますから、当然フランス語とイタリア語は喋れます。どういうわけか、英語がたどたどしいシーンがありましたね。英語も彼女にとっては「母語」ではなく、「外国語」の一つだったのかなと、考えさせられましたが。ギリシャ語はもちろん──「母語」の一つですから──喋ることができます。つまりカラスは、今日の映画で見るだけでもフランス語、イタリア語、英語、ギリシャ語の四言語を話せますから、その場の相手やコミュニケーションの仕方に応じて使い分けるのでしょうね。ただしその分、自分の本当の言葉(ランゲージ)をしばしば見失ってしまう側面もあったと思うのです。
この映画は、「ギリシャ人」としてのカラスにスポットをあてた作り方をしているなという印象を受けました。「メデア」という作品が出てきましたね。ギリシャの野外劇場で上演するシーンがありました。これはケルビーニというイタリアの作曲家のオペラですが、もともとはエウリピデスという古代ギリシャ人が書いた悲劇が題材です。このオペラを野外劇場──古代ギリシャ時代の遺跡──で歌ったときに、カラスは自分のギリシャ人としてのルーツを発見した、そう映画では言われていましたが、私は監督(フィリップ・コーリー)による一つの巧みな解釈だなと思いながら見ていました。古代ギリシャ悲劇に基づくオペラのレパートリーを古代の劇場跡で「ギリシャ人」として歌ったときに、カラスにとって帰るべき「ホーム」が発見された、そういう作りになっていたと思うのです。
そこにはギリシャの海運王であるオナシスとの恋の物語が重なってきます。夫のメネギーニはイタリア人で、不倫相手であるオナシスがギリシャ人。恋愛に国籍は関係ないのかなと思いきや、ギリシャ司教に二人が祝福されて、カラスもギリシャ国籍を取る、という場面が出てきましたから、「コスモポリタン」といわれながら、実は意外にもギリシャという故郷──彼女の両親の出身地──に絡め取られた人生だったのではないか。少なくともこの映画は、そういう描き方をしていたのではないでしょうか。
松原 たどたどしい英語。13歳でギリシャに渡るわけですから、確かにアメリカでは小学校教育しか受けてないわけですね。戦後、21歳でアメリカに活路を求めますが、その前にすでにギリシャのアテネ劇場ではスターでした。ギリシャがイタリアやドイツに占領されていた時に、多くのギリシャ人は飢えに飢えていたのに、カラスは丸々としていた。占領軍に協力的だったので、戦後ギリシャを追われましたが、紆余曲折を経てギリシャに回帰していった。それが彼女にとって、どんな意味があったのかなと思いました。
吉田 本日の映画はそういう話ばかりでしたね。ニューヨークのメトロポリタン劇場も最初はノーと言いながら、途中でやっぱりカラスを欲しがったとか。イタリアのスカラ座も最初は監督と折り合いが悪かったけれども、結局デビューできたと。ギリシャでもそうでしたし。喧嘩したり、うまくやったり、その辺りが激しい人なのでしょうかね。それこそ作られたイメージかも知れませんが。
松原 いろんなところで衝突もし、もてはやされたりもした。どんどん彼女がスターになっていくにつれて、劇場との軋轢も強くなったといいます。それに伴ってマスコミの餌食になっていく。決定的だったのが、ローマ・オペラ座での「ノルマ」で、第一幕だけに出てキャンセルした1958年の事件ですね。それによって、ネガティブな「メディアの寵児」になっていく。そのあたりのことについてはどういうふうにみられました?
吉田 今回のシリーズ「挑発する女たち」では三本のドキュメンタリーを見ていきます。そうした観点から今回の映画を考えてみる必要もあります。これまでのカラスのドキュメンタリー映画は、知人のインタビューなどを中心に、つまり死後の評価や周りの人の記憶に頼って物語を構成したものが多かったのです。ところがこの『マリア・カラスの真実』を撮ったコーリー監督は、それをやらなかった。彼は昔のアーカイブ資料を再び調査して発掘した映像と写真を中心にこの映画を構成しています。ですから第三者の証言はあまり前面に出てきておらず、むしろカラス自身の声と映像が語るという要素が強かったように思います。またアーカイブには1957年以前の映像は無かったので、それ以前の時代については写真と録音でうまく補っています。冒頭に出てきたパリの映像を覚えていますか?
松原 ブリジット・バルドーも出てくる。
吉田 そうです。あれがちょうど1958年なのですが、実はそれ以降の映像しかこの映画では用いていないのです。それ以前の映像はアーカイブに無かったからです。でもわれわれはそれをまったく意識せずに見ることができます。写真や録音、物語(ナレーション)やステージ衣装をうまく使いながら映像がない時代のカラスの歩みを実に上手に再構成していましたね。ホテルの映像の場合でも、現在のホテルの映像を使い──ダンスホールも天井だけを映すとか──それを録音と上手にシンクロさせることで、あたかもカラスが映像の中で動いているような印象、錯覚を持たせるくらい上手に作ってあると思います。でも実際にカラスが映像の中で歌っていたのは、1958年以降、つまりカラスが35歳から引退する41歳までの、わずか六年間だけなのですね。
松原 むしろピークを過ぎていた。
吉田 そうです。ピークを過ぎた後の映像しかなかったわけです。観た人にそういう印象が残らないとすれば、それはこの監督の構成・編集の上手なところなのでしょう。
松原 「ヴァルキューレ」と「清教徒」を演じ分け、華々しくスカラ座に乗り込んだ頃は、体重が100キロ以上あったわけですね。でもピークを過ぎる直前に、カラスは大変美しくなります。もともと華やかな顔だちの人ではあったけれど、あの変身がなければ、彼女はこれほど伝説的になっていなかったかと思います。ビジュアルの変化とそのインパクトについては、どう思われました?
吉田 ジャーナズムにどのように見られたかということに関係すると思いますが、単にオペラ歌手としてはあそこまで痩せる必要があったとは思えません。イタリアでのカラスの取り巻きが、彼女をファッション・リーダーとして売り出そうとした、という話がありましたが、自分が作ったのか、周りが作らせたのか、分からないままに、時代の中の「アイコン」としてのイメージを獲得していった、そういう存在ではないかと思います。オペラ歌手でありながら「時代」を象徴する女性になっていく面があり、そうした部分が彼女の評価を分かりにくく、混乱させているのかなという気がします。ただし今回の映画はわざわざ「マリア・カラスの真実」というくらいですから、それとは違うものを見せたい、という監督の意図があったのではないかと思いますが。「新たな敵としてテレビを発見した」というナレーションもありましたが、どう思われましたか。
松原 カラスはテレビが身近な存在にしたスターとして、最初の世代かなと思うんです。テレビに追いかけまわされ、持ち上げられ、落とされた第一世代ではないかなと。もしも彼女が大きな体格のままだったら、それは、なかったんじゃないかという気もします。
吉田 確かに、オペラ歌手以外の仕事はできないという感じですね。
松原 痩せたのは諸説あって、サナダ虫を飼っていたとか(笑)。
吉田 説得力がありますね(笑)。
松原 それは事実ではないらしいですが、16カ月で35キロ落としたそうです。歌に精進するのと同じくらいに、かなり本気で減量に取り組んだのではないでしょうか。太っていた頃、ヴィスコンティに「痩せたら世界一の歌手になる」と言われたとか。減量による舞台映えは、オペラに演劇性を復活させたという功績につながったのではないでしょうか。
吉田 最初にも言った「劇的真実」ですね。
松原 超絶的な歌声とともに卓越したビジュアルを獲得したことで、世界一になったところもあると思うんですが、同時にファッション雑誌から抜け出たような、モードのアイコンにもなっていく。そのあたりは、ただのオペラ歌手ではないですよね。
吉田 それは私も見て感じました。オペラというジャンル、あるいはクラシック音楽というジャンルを「大衆化」させるという役割を、カラスが一身に担わされていたように思います。この映画の中で印象的なシーンに──意図的にその映像を繰り返し使っているなと思いましたが──イギリスの公演のものがあります。カラスのコンサートにたくさんの若者が並んでいて、凍えた感じの若者がカメラに向かって「カラスは世界一の人ですから、ボクも見なくちゃ」などと言うシーンですね。あれは間違いなく、上流階級や社交界とは対極のものとして映されていたわけです。あれは確か「テレビが敵になった」云々のナレーションの後に出てきたシーンですよね。つまり──ここからは私の推測ですが──テレビの普及によって、カラスの名前が、ロックのコンサートに行くような若者の間にも浸透し、それによってさらにカラスが追い込まれていく。あの若者の映像はそういう主旨で流されていたのではないでしょうか。良くも悪くも、クラシック音楽の「大衆化」を背負っていたカラス、ということですね。
松原 そうですね…。ところで、今回のシリーズ7では「挑発する女たち―アートの臨界」をテーマに、アートに関わる3人の女性をとりあげていくわけですが、マリア・カラスの場合、何を「挑発」したと思われますか。また、オペラ歌手・カラスという存在はどんな意味で「アートの臨界」にあったといえるのでしょうか。
吉田 「挑発」に関してですが、カラスは自分に正直で、嘘をつかず、素直に、やりたいようにやってきた人です。でもそれが周り(劇場関係者やマスコミ)との軋轢を生み出してしまう。言わなくてもいいことを言っちゃうから、というのもありますが。本音で正直にやりながら、それが芸術的な意味でも、対マスメディア、対人関係においても、「挑発」になってしまう。つまりアーティストとして正直に自分のやりたいことをやることが「挑発」として受け取られてしまった、「挑発」を意図にしているわけではないのに、そういう位置・役割におかれてしまった。カラスの場合、そういうことなのではないかと思います。
もう一つの「アートの臨界」というのは中々難しいですね。この作品を含む三本の映画に共通する問題意識は、アーティストがやりたいようにやった結果が、はいアートです、というわけでは決してないのだ、そこにはアートをめぐる諸々の制約、社会的システムがあるのだ、ということだと思います。
カラスの場合でいえば、パトロンがいないといけないし、劇場の監督にも気に入ってもらわなければいけない。そうした中でようやく与えられた一回限りのチャンスを、どう生かすか。先ほどスポーツ選手に似ていると言いましたが、アーティストもまさに「ぶっつけ本番」の世界を生きており、「アート」という価値がどこか高いところで護られて、保証されている、というのではまったくない。とくにオペラ歌手などを見れば、「アート」がいかにギリギリ、すれすれのところで成立しているかが分かる。そういうことが「アートの臨界」である、というオチなのですが、いかがでしょうか(笑)。
松原 臨界でせめぎ合う緊張感あってのアートということですね。ところで、マリア・カラスは、20世紀のオペラ歌手としてどこが画期的だったのでしょう。一言でいえば、名人芸の復活でしょうか。「その歌手」ならではの感動を、20世紀のオペラに取り戻したといえるのではないでしょうか。プリナ・ドンナであり、ファッション・アイコンでもあるようなカラスのスター性は、メディアで増幅されました。だからこそ、カラスがオペラの悲劇のヒロインと重ねあわされ、人々はカラスという存在をそのようなものとして深読みしていった…それも含めての名人芸、ヴィルトゥオーゾを復活させたのでは?
吉田 その通りだと思います。ただしそこで大事なのはそのヴィルトゥオーゾが現代的な「スピード」の時代を生きなくてはならなかった、ということです。昔でしたら、世界各地を船旅で回りながら公演地に赴き、移動時間を利用して練習もしっかりする、というやり方だったのが──映画でも描かれていましたが──飛行機ですぐ移動できる時代になって、すぐに地球の裏側まで飛んでいって、いりなり顔も知らない共演者に合わされて、「はい、では明日やってください」という時代になってきたわけです。カラスは、古いレパートリーを蘇らせたと同時に、現代的なスピードにのって「大衆化」した音楽文化を生きた。その二つを両立させたのがカラスであって、他にそういう人はいないのではないかという気がします。単に昔のヴィルトゥオージティを復活させただけではなく、現代的な困難の中で、それをやってのけたということですね。
松原 なるほど。オペラ歌手としてのすごさですね。では、皆さんから質問を受け付けます。いかがでしょうか。
質問 カラスは20世紀の中葉に一世紀前のドニゼッティとベッリーニの難しいオペラを復活させたと。声質が合っていて、技量を持っているから新しい解釈を出せたというのは分かるのですが、ケルビーニの「メデア」やスポンティニの「ヴィスタの巫女」などの古典作品を、カラスに向けて支配人がやらせたのか、それともカラス自身のリクエストなのか。小屋主や支配人の権限がヨーロッパでは強いと思いますが、そのへんはどうでしょうか。
吉田 映画ではあたかもカラスが周りを引っ張っていったように描かれていましたが、カラスがやりたいからやったというよりも、周りがカラスをもり立てるためにやったという要素が強いのではないかと思います。具体的には指揮者のセラフィンたちですが。いくらカラスが突出した歌手であっても、廃れてしまったレパートリーを彼女が自分で見つけてきて「これを歌いたい」といって、周りが「はいそうですか、ではやりましょう」とはならない。自分のやりたいことを、練習から本番まで周りと一緒になってやっていく中で、周りに広げていかなくてはならないわけです。カラスが歌って古いレパートリーを復活させることは興行的にも「売り」になりますから、指揮者や劇場関係者は協力的であったでしょうが。
質問 マリア・カラスが気難しくて公演を断った時、毎回、違う相手役で、これは芸術じゃないと。オペラが大衆に浸透する、しないという次元と、マリア・カラスが、何を芸術と思っていて、何を浸透させようとしていたか。マリア・カラスが引いていた線は、どこにあるのか。今回、劇的真実というキーワードが出てきたと思いますが。
松原 「芸術ではない」と言ったのは本心なのか、それとも…。
吉田 「挑発」ですね。
松原 あるいは戦略なのか、よくわからないですよね。でも、完全な舞台をじっくり作りたいというのは本心だった思います。彼女自身がどこで芸術としての線を引いていたかはわかりませんが、ただこなすというのではなく、ひたむきに一生懸命取り組んでいた。だからこそ歌手生命も短くなったのかなとも思います。
吉田 字幕にはありませんでしたが「ルーティンは嫌だ」といっていましたね。そういうのが嫌だったのでしょう。
松原 それもあるかもしれませんし、興味深いポイントだと思います。彼女の一人の女性としての人生に関心を持った方もいらっしゃると思います。
吉田 せっかく子どもを身ごもりながら、流産してしまったとか、お母さんといつも喧嘩をしていたとか、女性としてのアイデンティティの困難さも随所に描かれていましたしね。
松原 そうですね。まだ話は尽きませんが、時間になりましたので対談を終わります。本日はご来場いただきまして、誠にありがとうございました。
Copyright © 立命館大学 All rights reserved.