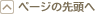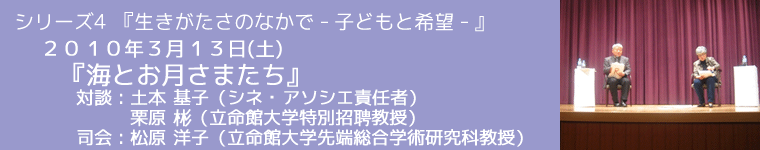
司会:今日は土本典昭監督の1980年の作品、「海とお月さまたち」をごらんいただきました。この後、いつものように制作にかかわった方と研究者の対談で進めたいと思います。
土本基子さんは、映画同人シネ・アソシエの責任者で、亡くなられた土本典昭監督のおつれあいでいらっしゃいます。助手として制作の現場にかかわってこられた方です。栗原彬さんは、立命館大学特別招聘教授で生存学のプロジェクトメンバーです。また、水俣フォーラム代表をされています。
先に、お手元の資料の確認をさせていただきます。1ページは、今日の映画の紹介と土本典昭監督と基子さんのプロフィール。2-3ページは、土本基子さんが雑誌に書かれたエッセイ「『おもてなしの心』-記録映画作家土本典昭の思い出」(『ビルメンテナンス』、2010年1月号)。土本監督とのお仕事に触れられています。4-5ページは、土本基子さんが今回の企画に際して作られた「海とお月さまたち」の概要メモ。映画の特徴がまとめられています。6-11ページは、「海とお月さま」たちに関する土本典昭監督の原稿。シネ・アソシエのホームページに掲載されているものの抜粋です。12ページは、栗原彬さんが「海とお月さまたち」をはじめとする土本監督の作品について、水俣の問題との関連で書かれた記事(「土本典昭の見果てぬ夢」『図書新聞』、2008年11月22日)。13ページは、水俣病の特措法の成立に際して栗原さんが書かれた記事(「水俣病特措法成立-誰のための『最終解決』か」『東京新聞』、2009年7月15日夕刊)。水俣病問題の現在について知ることができます。栗原さんは。そして14-15ページが、栗原さん作成の水俣病問題の年表。最後の16ページが、今日の舞台になった天草の深海(ふかみ)や水俣をはじめとする不知火海一帯の地図です。それではよろしくお願いいたします。

栗原:皆さん、こんにちは。栗原彬です。今日は土本基子さんをお迎えして、二人で映画「海とお月さまたち」についてお話をしていきたいと思います。映画を見た後で話をするということですが、映画それ自体がすばらしいものですので、その映画の解説より、映画それ自体から私たちは何を読み取ったのか、また、映画の背景にある事柄をお話して、この映画の見方が、それによって深まっていくことがあると、いいと思います。
この映画は土本典昭監督がお撮りになったものですが、土本さんのドキュメンタリーの特徴が、とてもよく出ている映画でもあるんですね。土本さんのドキュメンタリーの方法を二人で話しあってみようと。 この映画は、水俣病のことが正面に出ていないんですね。水俣病のミの字も出ていない。だけれども、水俣病についての優れた映画であるといわれています。この映画は水俣で最も好まれているんですね。私も何度か水俣に行って、催しがあるごとに、この映画を見ています。患者さんたちは、この映画が好きなんです。今回、この映画を採り上げた理由でもありますが、なんでこの映画か好まれているのか、水俣病との関係があるわけですが、水俣病それ自体について、この映画と関係があるところで、そのお話をするという迂回路をとりながら、もう一回、今日の映画について、二人が話をする。その後、皆さんからご質問があったり、ご感想があれば、出していただきたいと思います。
この映画を土本基子さんも何度も見たわけですが、今日、改めてごらんになって、この映画は一体何を語ろうとしているのかというところから。
土本:皆さん、こんにちは。土本です。映画をご覧頂きありがとうございました。この映画は、「木造船をつくるおじいさんと孫」というのが最初の題材だったのです。おじいさんのそばで、孫が船のつくり方を学んだり、漁の仕方とか、お月さまの変化を学ぶというのが、最初の映画の構成だったのです。変わった理由は、土本典昭が亡くなったいまとなっては、わからないですが。
土本は映画をつくる前に「演出ノート」を書いていました。そこには「テーマは老人と子ども、自然と人間のありようです。」「月は現代生活の盲点です。農と魚とりの原点にかかわらず、月は忘れられています。その分だけシンボリックに復調させました」と書いてあります。 「映画同人シネ・アソシエ」のホームページに土本の論文を掲載しています。実はその論文は、土本の死後に出てきたものです。原稿用紙で280枚くらいがありました。その中に『海とお月さまたち』についての記述があったので、松原先生にお話しましたら、全文を資料の中に入れてくださいました。『海とお月さまたち』を子ども向けの話だと私は思っていたのですが、その文章を読むと、土本の思いはもっと深かったことがわかりました。今日は全文と私が作りました作品解説を皆様にお配りしています。
栗原先生から、『海とお月さまたち』が水俣の患者さんに人気があるというお話がありましたね。 映画の中に貝を拾っている子どもや、海辺で遊んでいる子どもや、籠を海に沈めて魚をとる漁法などがありましたが、あれは昔から水俣にあった風景なのです。一本釣りとか、鉾突き漁というのは原始的な漁で、多分、大昔からあったのではないかと言われています。一匹ずつ獲るわけですから、魚をとりつくす漁法ではない。魚と人間が共生できる漁法です。昔は水俣にもあった。
水俣病が起こった原因は、漁師さんたちが貧乏なので、おかず用に有機水銀に汚染された貝を拾ってきて食べたり、お米の代わりに汚染された魚を丼に一杯食べたり、そういうことで自然の中で起こってきた病気なのですね。魚が汚染されているなんて夢にも思わないわけですから。
水俣病以前の平和だった水俣の風景が、『海とお月さまたち』の映像の中にある。水俣病が起こる前の世界が、この映画の中にあると思って差し支えないのです。そのことが水俣病の患者さんたちにはわかるので、「ああ、自分たちの昔の世界なのだな」と、チッソがくる前の、水俣病以前の良い世界が、この映画の中にはあると。そういうふうに思われたのだと思うのですね。
月がたくさん出てきますけど、月は、お魚をとることに関して、すごく関係があるのです。土本たちは映画をつくる前に、こういうグラフをつくりました。
(図を示しながら)お月さまが出る時と沈んだ時に潮が満ちる。満ちると、お魚がたくさん出てくる。一番出てくるのは潮が引く時なのです。潮が引いたり、満ちたりする時に海は川のように流れます。すると、餌のプランクトンが海の中にワーッと増えまして、魚がパッと出てきて、それを食べる。それを狙って漁師さんたちは漁をする。そういう仕組みです。
こういうグラフをつくって、映画を撮る時のポイントを研究したようです。
「月の入りと出」ということが、満ち潮と関係がありますからね。
もう一つの特徴は、天草はすごく干満の差が激しいところなのです。
「月の暦」というホームページを見ますと、よくわかります。 2010年3月13日の場合ですが「天草は潮高が83cm〜3メートル27cm」です。 京都に近い舞鶴はどうかというと「舞鶴は潮高-11cmから10cm」です。それくらい干満の差が激しい。波が激しいからお魚も来る。海の動きの速いところです。だからフグが来る、タイが来ることに影響している。
この映画の撮影は瀬川順一さんというキャメラマンです。瀬川さんはドキュメンタリーで有名な亀井文夫監督の映画「戦ふ兵隊」(1939年)の撮影助手をした人です。大キャメラマンの三木茂さんの撮影助手を担当しました。土本の映画の先生でもあります。すごく、撮影技術が巧みで、芸術的な映像づくりがすばらしいといわれています。羽仁進監督「法隆寺」(1958年)、土本典昭「水俣の図・物語」(1981年)などの作品があります。
音楽は松村禎三さんです。「管弦楽」「器楽」「声楽作品」「オペラ」「映画音楽」など、たくさん作曲をなさっています。映画は記録映画、劇映画を問わず作曲されています。
ですからこの映画は子ども向きの映画としてつくられていますが、実は大変なカメラマンと、大変な音楽家と、土本の編集で出来た映画なので、大人でも好きな映画ですという人がたくさんいます。
栗原:この映画は、今、おっしゃったように、水俣にとっていわば失われた風景であるわけですね。昔の水俣とそっくり似たような暮らしと風景があった。不知火海に奇跡的に残されているところが一つある。これは同時に今の水俣病患者たちにとっては、こうあってほしい、こういう世界に、もう一回戻ってほしいとういう未来の風景でもある。希望ということを、感じさせる、そういうものがあるから患者さんたちが好むという。この映画は、皆さん、おわかりのとおり、月があって、潮の流れがある。海の中に川のように流れがあるわけですね。これは資料の最後の地図をごらんいただくとわかりますが、天草諸島の南端に牛深という地名があります。南端です。右隣に獅子島があります。獅子島の北端の方を左右に水平に線を引いていただくと天草にぶつかるところが深海という町なんです。深海についてお話をした方がいいかと思いますが、水平線の右の方が水俣です。位置関係でいうと、そういう関係になっています。外海からの潮が獅子島と天草の島との間の狭いところを上るわけです。激流のように満潮の時に上ってくるわけです。月の満ち欠けと潮の干満が、この基本をつくっている。そこに命の営みが行われていくんですが、それは月から始まって、潮の動き、魚の動きとなっていって、それが人間まで及んでいく。しかもこの映画は深海という町の漁師たちの漁の仕方なんですが、一本釣りなんです。巻き網漁なんかだと、魚をとり尽くしちゃう。そうではなく、一本釣りである。
しかも画面の中で稚魚が引っかかると海に返しますよね。そういう形で海を大切にしながら、海との契約を結びながら、漁師たちが命のつながりの中に生きているということが言えると思います。 しかもこの映画の中で大事な場面は老人と子どもとの関係です。老人が縁側で一生懸命、偽餌をつくっている。それを子どもたちが見て好奇心を起こしていろんな質問をしてくる。あの時の目の輝きは、すごいものでありますが、これは老人から子どもへという、つながりが見事に出ている場面です。こういう命のつながり、そういうことが、とてもよく現れているところです。 しかも月があって潮のダイナミックな動きが出てくる。それと同じように老人がいて、老人が手仕事をする。そのことを通して、子どもが子どもらしい、知的な好奇心を起こして、子どもが本来的な子どもを表していくということが言えますし、それから子どもがいることで、老人が老人の尊厳を表している場面ですね。こういう老人と子ども、漁師と魚、魚もそうですけど、魚をとると簡単に言うけれども、この映画の中では、魚もまた命あるものとして、それを人間が釣って食べるという行為の中で、魚が、魚の本来性をあらわにしていく。その命を人間がいただくということの営み、それ自体をクローズアップしていますよね。これを何というか。たとえば、子どもが子ども本来の存在を表すという言い方ができると思います。さまざまな命があって、その命が他者とのかかわりの中で、しかもそこに、技術があるんですね。手仕事的な手の技が加わることで存在の現れ、本来の命の現れ、漁師の持っている尊厳、漁師の持っている人間らしさというものが、あるいは子どもの子どもらしさが見事に現れてくる。関係の中で現れてくる、そういう大きな命のつながりと、つながりの中での本来の存在の現れ、そういうことを見事にとらえているわけです。そのことが、水俣病患者にとっては、水俣病患者が自分って何なんだ、こういう不条理な病を負ってしまった時に、自分の本来性、人間としての私というものを、どういうふうにして表すことができるかという問題につながってくるわけですね。
土本さんの水俣病の映画は人間を撮る、そういう映画だと言えると思うんですが、土本さんのドキュメンタリーについて話をしていきたいと思います。今、舞台になったのは深海という町です。天草の南端に近い方で深海というのは漁師の町であるといっていいんですが、資料で「海とお月さまたち」の記録メモを見ていただくと、深海について書かれています。深海の漁師たちは、農民から差別を受けている。もう一つは漁の方法、鹿児島とか、不知火海の入り口のところで魚をとる人たちが船団を組んで網漁で魚をとる。しかし深海では、狭い瀬戸のところで一本釣りをする。鉾で突いて魚をとるということをやっている人たちが深海の漁師です。ある意味で滅びゆく漁なんですが、しかし海ということを命の宝庫として考えると、それを保っていく、持続することでいえば、一本釣りの意味が、とても大きい。深海は不知火海の入り口で、外海に面している。そのために水銀がここに堆積しなかったという幸運があったわけです。地図をごらんいだくと、そのことがよくわかると思いますが、しかしここにも水俣病患者がいたんですね。それは画面には出てきません。子どもの映画としてメルヘンとして描かれていますが、その背後に水俣病患者がいたわけです。水俣病患者の処遇、水俣で実際に水俣病患者たちが排除されたり、差別されたりするんですか、その原型が、実は深海にもあったんですね。
司会: 地図で深海と水俣の場所をちょっと確かめてみましょうか。深海は、地図でEとFの間の線を北にたどっていただいて、6と7の交差したあたりにあります。水俣はH7の真ん中あたりです。
土本: この水俣湾から海流に乗って水銀が出ていったということだと思うのですが、不知火海の島と島の間を縫うようにして、外海へ流れ出て行ったのだと思います。すごく速い流れですから水銀が堆積しなかった。
水俣病の患者には天草出身の方が多かったのです。水俣にはチッソがありましたので現金収入が得られるので、天草からたくさんの人が渡ってきています。水俣病患者運動の指導者だった故川本輝夫さんの父親の嘉藤太さんは深海の近くの茂串の出身です。
天草出身の人を「天草流れ」と言われていました。水俣病が発生した漁村は貧しいから、水俣でも差別されていた人たちだった。そこで水俣病が発生した。そして、水俣病は死んじゃうような病気でしたから、皆、恐れて、伝染病ではないかという噂も立った。深海でも、昔は漁民が、農民から差別をうけていたといいます。天草でも差別をうけていたという歴史があるわけです。
深海には悲しい昔話があります。深海で天然痘が流行ったことがありました。天然痘は伝染病で治らないので、深海の目の前に下馬刀島に島流しにしたのですね。天然痘の患者を子どもも大人も島流しにして伝染病を防いだという歴史があります。
土本典昭の文章を引用します。
「その水俣漁民が身に現れた奇病、一家に出現した神経どん(神経病のたぐい)にどんなにいわれないほどの羞恥をもって水俣の陸の市民に対したか。」
「…天草では生きながら島に打ち棄てる風習もあったのである。」
「-そうした共同体の共同記憶が、初期の“水俣奇病”のころに息をふきかえしはしなかったか」 島流しの恐ろしい記憶が、水俣病発生時にも出現したのではないかと、土本は推測しています。
下馬刀島は、この映画の中によく出できます。メーンタイトルの前に出てくる丸いかわいい島です。おじいさんが漁をしているバックにも映っていました。土本は何気なく「島流しの島」を映像の中に入れておいたと思います。 それがドキュメンタリーの面白さだと私は思うのですが、監督の思いを、映像のなかに隠しておくのですね。それは、土本の記憶の中に悲しい島流しの話があったのだと思います。
司会:下馬刀島(しもまてしま)。冒頭に左から右に船がスーッと動いていく。その上の方に、ぽっこり、かわいい小さな島がありましたが、その島ですね。
土本:私も、それだけだと思っていたら、今日、映像を見ていたら、かなり入っているのです。 インターネットでしらべたら、「下馬刀島のもんつき唄」と「島流しの話」が出ていました。島流しの話は悲惨な話ですが、今は亡くなった人たちを弔うための碑がおいてあるそうです。悲しい話だと思いますが、隠さずに自分たちの歴史としてきちんと伝えているということだと思います。
栗原:この映画は土本監督のドキュメンタリーの方法が、とてもよく出ていると思うんですね。たとえば老人が偽餌をつくっている。子どもたちがそれを見ている時、老人も子どももカメラを意識していないんですね。ある意味、自然体で、手仕事に双方がコミットしている。こういう撮り方というのは、土本さんの一つの特徴なんですね。「海とお月さまたち」を撮る時も、4カ月かけている。ちょっとそこの場所に行って「はい、写真撮ります」という話ではないんですね。そこには多分、その人たちと、とことん付き合う、カメラを回す前に付き合いがあるんですね。お互いにその意味では、写真を撮る人と、撮られる人の二項図式が消えたところで初めてカメラが回りだすという方法論だと思うんですね。そのへんのことを、少し手短に、どうでしょう。
土本:栗原先生が、子どもたちが自然に撮れているという話をしてくださいましたが、それを最初にやったのが羽仁進さんです。「教室の子どもたち」(1955年)という有名な記録映画がありますが、今までの撮り方の概念を取り払って、子どもが、カメラに慣れるまで、カメラを意識することがなくなるまで付き合った映画だといわれています。それまでは、そういう撮りかたをする映画は、なかったのです。土本も、羽仁さんの映画のつくり方を尊敬していましたので、そういうふうにして撮ったのだと思います。
深海には5カ月滞在したと書いていますが、かなり子どもたちとつきあったと思います。映画をやっているおじさんたちがいるなと、子どもたちは興味を持ったと思うのです。子供たちとご飯を食べたり、一緒に遊んだりして慣れていった。そうでないと、ああいうふうに撮れないですね。
土本という人は、とにかく人と付き合う人です。 「水俣-患者さんとその世界」は最初の作品です。水俣病闘争を撮るといった場合、一番の見せ場は患者さんたちが東京で役人とか警察官とドンパチ戦っているところだと思うのです。映画としては面白いわけですね。だけど決してそこでは撮らなかったのです。むしろ撮らないと土本は決めていた。その時にはNHKとか、TV局は撮っていたと思うのです。
土本は「運動している時は撮らず」、「映画を撮る時は運動せず」という言い方をします。だから、土本は撮らないで患者を守るために、支援者として座り込んでいたわけですね。それで、警察に逮捕されて留置されます。 患者さんたちも報道の人は慣れていますから、またTV局が撮りにきているな、という印象しか持たないと思うのです。でも、土本たちは撮らないで、一緒に闘っている。
患者さんは「なんだ、こいつは」と思いますし、なんか他の報道の人とは違うな、とわかったと思うのです。 そういうことを土本が意図してやっていたわけではなく、運動する時は物理的に撮れませんから、一生懸命にやって。そうやって逮捕されてから、患者さんたちが「ああ、こいつはなかなかいい奴で、俺たちのことをわかってくれるかもしれない」ということがあって、その後に水俣に入るのですね。 石牟礼道子さんに宿を紹介していただいて、スタッフと一緒に映画を撮り始めています。
土本の撮り方は、普通の撮り方とは、ちょっと違っていたかもしれません。それは対象への付き合い方の深さだったかなと思います。 水俣に行ってからもなかなか撮らないのです。 患者たちが会議をやる。その時は会場への運転手をするのですね。会議が終わると患者さんを乗っけては家に送ってあげる。「今日は、どうでしたか」と聞いたりすれば、患者さんたちは自分の気持ちを、そのまま話をしてくれますよね。だんだん「うちのも撮りなさい、あそこの家でいい話が聞けますよ」とか、そういうふうになって、そして「水俣―患者さんとその世界」という映画が撮れていったのだと聞いています。
栗原:とても面白い話で、そういうドキュメンタリーの方法論の中に、やっぱりこの映画になるような魂というか、哲学というものが、あるんですね。これは土本さんの青年期のある種の回心、「発心」と土本さん自身が言っていますが、そのことと、とても関係があると思いますが、土本さんの映画には生存学の哲学があるといっていいと思うんですね。死生学といってもいいんですけど。そういうものがあると思います。それは命とか、その人の存在を表すこと、人間存在を撮る。水俣病の映画を撮る時、撮れないで困っている、苦しんでいた時期がある。その時に渡辺京二さんという人が一言、「漁師というのは面白いんだよね、人間として面白いんだよね」、その言葉が手がかりになって「あ、人間を撮ればいいんだ」となっていくんです。人間を撮ればいいんだという、そこに至るまでの根本的な出来事があったんですね。
土本さんは昭和3年生まれです。戦争が終わる直前には自分が出征すれば、死ぬと。散華といいます。国のために死ぬ。死ということが自分の中に入り込んでいる。当時の同世代の若者が皆、そうだったと言えると思います。しかし、戦争が終わりになってしまう。終わってしまっても、死への思い、死ぬということについての思いは土本さんの中に生き延びている。しかも昭和23年という時点で太宰治の自殺がありました。若者たちにとってこのことはとても大きなことだったんです。言行一致、首尾一貫性、人生における。そういうことを土本さんは感じるわけです。それで死への思いから戦後、焼け落ちた小学校の理科室から劇薬と書かれたビンから、昇汞の粉末、無機水銀。それを持ち出して自分の手元においておいた。文学仲間、文学青年の仲間たちから俺たちに分けろといわれて、皆で分け持つ。先輩の友人が大学を卒業して一流の会社に入っていたんですが、その人が昇汞をあおって自殺をするわけですね。この昇汞というのは自殺志願者にとっては残酷な毒薬だといわれます。土本さん自身がいっていますが、腐食するんですね、体が。最初は歯茎とか喉、胃、直腸、膀胱と縦に腐食していく。まる1日かかる。肝臓、腎臓、すい臓がやられるのにあと2日かかる。さらに全身が腐食して失明し心臓が止まるまでに3、4日。その間、意識は明晰である。苦しんでいる先輩を、眠らずにモルヒネをあおって、土本さんは看病するんですね。その間に「俺を安楽死させろ」と先輩が言うんだけど、そのことにも失敗する。そういうことの挙げ句に、先輩は「死にたくない」という一言を残して死んでいくんです。その後、親兄弟が来て、うろたえている。蘇生を願って一生懸命なんだけど、そういうことを、悲しみと一緒に、ある笑いが、そこに浮かんでくる。土本さんは哄笑を数分間止められなかったというんです。こういうすごい経験をして、それを潜った後で、自殺ということを恐れる人間として生き続ける、そういう道を選んでいくんです。 新たな0からの出発だと。それは自己犠牲とか、他者への献身とか、人々の中での奉仕活動とかかわっていくんですね。もともと彼は戦後、共産党に入るんですが、党のとらえ方は仲間との間のことなんです。国のために死ぬ、党のために死ぬという、それから転じていくわけですね。党というのは、私と人間との間のことと彼はとらえ返すんですね。そのために内なる軍国少年を自分で解体することができていく。その時、得た心境を「発心の残照のもとで今も生きている」と土本さんは後に書くんです。この時の生命の肯定、そこへ行く時の大きな出来事、こういう生存学的な経験、死生学的な哲学があった。「他者を支配しない、自分も支配されない」ということです。国とか党とかの見方について、党の書記長は天皇とよく似ているという発言まであるんですね。そういうことが見えてくる。そうすると土本さんにとっての党というのは、支配しないもの同志の関係になっていくんですね。そういうことが同時に映画を撮る時も、被写体を収奪しない、支配しないことが大事になるわけでしょう。映像に写る人たちの主体を表す、そのように撮ることになる。
こういうドキュメンタリーの方法は小川紳介の撮り方と全く逆なんです。小川紳介は対象と真っ正面から向き合うという撮り方をします。土本さんは、そうじゃない。自分がどこかで消えていく。その中で、しかし土本さんがいることで、そこに、ある寛ぎが生まれる。「自分を開く」ということが生まれ、ごく自然に構えが崩れて、自分というものを表していく。人間というものを表していく、そういう瞬間にカメラが回る。そういうことなんですね。その意味では土本さんが自分を消すことによって、対象の主体を表していく。こういうドキュメンタリーの方法だということですね。 この映画は水俣病を撮った映画ではないんですね。水俣病という言葉を使わないで、水俣について語るという、そういう映画です。常に子ども向けのメルヘンであるという撮り方ではあるんですよ。ですが、常に背後に水俣病の患者さんたちのことがあったわけですね。
水俣病について資料の年表を見ていただきたいと思います。これで見ていただければわかると思いますが、左の欄に社会的な出来事、水俣病関係の出来事、事件史の区分。水俣病の発端というのは55年体制が成立する前後なんですね。1953年頃、水俣病の発生が確認されています。公的に水俣病の発生が記録されたのは1956年です。チッソの水俣工場がアセトアルデヒドと酢酸をつくる時に無機水銀を媒体として使う。その時にいろんな条件が重なって、製造工程で有機水銀という猛毒を副生してしまった。それを悪いことに水俣湾に垂れ流しをする。その結果が、水俣病を引き起こすことになったんです。そういう原因物質がわかって、チッソの水俣工場の垂れ流しが原因であるとはっきりしてくる頃に、なおかつ、これは国の判断ですが、「原因物質を発表するのは時期が早すぎる」という、1959年の閣議決定があって、チッソも原因物質を隠すわけです。原因物質はわからないことにして垂れ流しが続く。そのことの結果、1968年に公害病として認定されます。これは新潟水俣病が発生して、原因がはっきりしていますから、同じメカニズムですから熊本水俣病も公害病であると認定せざるをえない。同時に垂れ流しも止めることになる。原因物質がわかってから9年間も垂れ流しが続いたことになる。そのことによって水俣病の拡大と深化は想像を絶するものとなった。不知火海一円に有機水銀は広がっていますから、少なく見積もっても10万人くらいは被害者になっている。しかし水俣病患者としての認定を遅らせたり、認定を極度に少なくするという政治的な判断、1977年判断と言われるものがありますが、それによって水俣病患者の救済は著しく遅れるわけです。結局、そういうことが裁判闘争を通じて悉く患者側の勝訴になっていくんですけど、最後に国と県にも責任があるということで、国家賠償をめぐっての訴訟が起きます。1996年には和解が成立するんですが、関西訴訟だけは続いていくことになります。その結果が、最高裁の判決で「国と県に責任あり」と正式に認められて「77年判断基準が誤りである」ことも確認されたんですが、その後も、救済が行われないということです。
水俣病特措法は自民党と民主党との手打ちで、昨年、決まった法律です。これに基づいて患者たちの救済をするとういことですが、同時にチッソという会社を分社化することによって、賠償するチッソという会社と、どんどん儲けを拡大していく新しい別会社は補償にはかかわりないと。チッソという賠償の主体を消していくということですね。これは、ある意味でとんでもない法律です。こういう法律の範囲内で、精一杯、一時金を出そうかとういう程度の話です。その前提として、患者が、一体、どれくらいいるのかという問題、これが全くわからないわけです。国が調査をしていないから。猫踊り病といって有機水銀に汚染された魚を食べた猫が狂って海に飛び込んだりする。猫踊り病が発生したところをマッピングしていきますと、不知火海一円になるわけです。不知火海は内海ですから、その一円で、少なくとも10万人乃至は30万人の被害者がいるといわれています。その人たちの調査が行われていない。最高裁判決があったものですから、認定の申し立てが続々と出ている。裁判も新たに始まっています。水俣病問題は終わったとは、いえないわけです。
水俣病問題に、もう一回、皆さんに目を向けていただくことが大事なんですね。もう一つは恒久的な救済対策が考えられないといけないんだけれども、一度も考えられたことがないんです。一時金で終わりにする。そういう問題ではないはずです。救済が行われていない。それだけに水俣病問題を、再び再定義する形で、皆で考えていくことが必要なんですね。そういう意味でも、この映画は、とても意味があります。 私がかかわっている「水俣フォーラム」で、水俣病患者さんのパネルを250くらいつくりまして、展示することをやっています。その中の中心の部分に、土本さんが水俣を歩かれて集められた500の遺影があります。「記憶と祈り」と土本昭典さんが名付けた円筒の空間の内側に、500の遺影が飾られています。
それが水俣フォーラムの展示会の中心になっています。「記憶と祈り」ということも土本さんの映画の基本軸ですね。500の遺影というのが重要で、これは土本さんの作品でもあると思っています。500の遺影の空間の中に入る。入った時の経験というのは、多分、展示会に行かれた方もあるかと思いますが、500の遺影の眼差しの中に自分が立つわけです。その時には私が遺影を見ているのではなく、遺影の方から私が見られている、そういう感覚になるんですね。この空間について、基子さんからお話を。
司会:500の遺影は、1996年の「水俣・東京展」のために、水俣病患者遺族の家を監督と回られて集められたそうですね。その時の様子を教えていただけますでしょうか。
土本:私は土本と張り切って水俣に入ったのですが、なんと水俣病死亡者の名簿がなかったのですね。訪ねていくべき人の住所も電話番号も遺族もわからなかったのです。チッソは亡くなると、お花を出したり、お香典を出したりしますので、チッソにあるのではないかと思って行ったら、チッソは出せないと。患者団体が20派くらいあるのですが、皆が賛成してくれないと出せないと。プライバシーに関係があるからと。 ですから、私たちは亡くなった方の名前を探すことから、しなければいけませんでした。水俣病の運動をしている人たちが協力してくれたのですけども、何カ月かは名簿を作るのが大変でした。
それが終わって、「東京で水俣病の展覧会をやりますのでご遺影を出してほしい」とお手紙を書くのです。遺族の家を訪問して、仏間に飾ってあるご遺影の複写をさせていただくわけです。 電話をかけますと、「あ、もういいです。そんなことはしてくれなくていいです」と断られる。電話だと「生命保険」とか「株の勧誘」と間違えられてしまう。その当時は「オウム真理教」が流行っていましたので、お前たちは「オウム」ではないかと疑われたこともありました。
お手紙を出して一戸、一戸訪ねていきました。端から訪ねていくのですね。「端っこ」から訪ねてきたというと疑われないのです。誰にも迷惑はかけませんし。トントンと戸を叩いてから、「実はお手紙を出したものですけど、いかがでしょうか」というと「あ、結構です」といわれることもあります。
水俣病に認定されるとお金が入るのですね。被害があったら補償金が入るのはあたりまえなのですけど。そのことによって家族の中で喧嘩があったり、いろんなことがあるわけです。大金が急に入るとたいへんです。また、結婚や就職の差別をおそれて、「水俣病患者ということは子どもにも言っていない、孫にも言っていない」というお宅があるわけです。
そうかと思うと「よく来てくれましたね」と、いろんな話を聞かせてくれたり、お茶を出してくれたり。「あんたたち大変だから」と、おばあさんが千円札をくれたこともありました。だから、門前払いもあったけど、よくしてもらったことやうれしかったこともたくさんありました。 実際、やることはお金がかかるのですね。1741万円かかりました。土本と私とで負担したお金です。500名近く遺影を複写させていただいて、1996年に、「水俣・東京展」の時に「記憶と祈り」とタイトルをつけ、水俣病死亡者遺影群を展示しました。 それを展示しますと、水俣などでは、お参りをしてくださいます。写真であるけれども、魂が来ている。自分のじいちゃん、ばぁちゃんが、ここに戻ってきている。石牟礼道子さんは「魂入れ」といいますが、ちゃんとお参りをしてから見ていただきました。その他の展覧会場でもそういうことがあったと思います。ですかた、ご覧になった方が霊的なものを感じられるとか、そういうことがあっても不思議ではないと思います。写真であるけれども、不思議なモニュメントだと思います。
司会:それだけ資金面でも足を運ばれて大変なご苦労をされても、そういう遺影を集めるという企画をなさった背景には、土本監督のどんな思いがあったのでしょうか。 土本: 展覧会で何を展示しようかと、いろんな人たちが集まって考えたのです。思いついたのは、あの当時、「アウシュヴィッツの被害者」、「ポルポトに殺された人たち」、「チリのアジェンダ政権で殺された人たち」の写真を飾って犠牲者たちを偲ぶ、平和を祈るというのが世界的な潮流だったんですね。それがもとにはなっていると思います。名前よりも写真は見るものに強烈な印象を残しますから。 松原: それでは皆さんから、ご質問をいただきます。映画そのものでも結構ですし、それ以外のことでも結構です。漁とか潮のこと、季節のこととか、お気づきのことがあれば何でも・・・。では考えていただく間に、補足することがあれば土本さん、栗原さんからお願いします。
土本:この映画を見まして、月って、面白いなと思いました。「空と月と暦」(米山忠興著)が、とてもわかりやすいと思いました。月とか潮、旧暦の暦のことが簡明に、よく書かれていますので、これをお読みになるとよろしいと思います。
司会:方眼紙に新月、満月、上弦、下弦と月の満ち欠けが書かれていて、その下に青、ピンクの線で潮位が記入されています。監督が撮影の準備のために、作成されたのですね。伺うところによると、映画のプロット自体は撮影前にざっとつくられるそうですが、事前の調査を綿密にされて、スタッフと共有されるということでした。自然の変化についても研究なさっていたんだなと感慨深く拝見しました。 土本: 「ある機関助手」という土本の作品がありますが、電車が走っていく映画なのです。あの映画は、すごく贅沢な映画で、1本の電車を何日も映画のために走らせたのです。「ある機関助士」は「月」ではなくて「太陽」ですが。夕暮れ時に太陽とともに汽車が走っているというシーンをとるのは計算がいるわけです。一日に一カットしか撮れませんから。太陽が沈んでいく角度にあわせて、どこの場所で機関車を撮るということが決まっていないと、自然な日没が再現できないわけです。私など素人は、映画の人はすごいことやってのけるものだと感心するのですが、月の場合もそうだったのかと改めて感心したわけです。 松原: 私たちは映像を何気なく見ていますが、制作する側は技術を駆使して、準備をいろいろするわけですね。時代によってやり方が違うかなと思いますが。
栗原:今、表になっていますが、さらに一つ冊子がありますね。細かいカットです、カット表が綿密ですね。 土本: その時のカット表です。本物ですから、後で見ていただいて。
司会:制作で実際に使われた資料をお持ちいただいていますので、何点か後ほど茶話会で見せていただこうと思います。
栗原:「海とお月さまたち」について。補足として二つのことがあります。一つは魚の目ですね。最初に出てきたのはイカだったと思います。海底でタマゴを産み続けるイカの目がクローズアップで出てくる。釣ったタコの目が印象的です。それからフグも目に焦点がある。タイ、大ダイとなって、最後はイカの赤ちゃん。ふわふわした綿の中に黒い点みたいな目がはっきり写っていましたね。魚を撮る時に土本さんは目を撮っている。そのことは500の遺影の眼差しと重なってくるんですね。大画面でしたが、そこに魚の目が、ものすごく大きくクローズアップされて、魚に見られているという感覚ですね。観客が魚に見られているという状況をつくるという土本さんの意図が、はっきり見えていますね。それは500の遺影の眼差しの中に私たちが立つ時に起こることと重なっています。
もう一つは縁側の場面が出てきました。縁側とは何か。失われたものではあるんだけども、これは深海のような小さな町で一つの大事な公共性の場面ですね。公共空間をつくっている。縁側は公共空間です。公共性、公共空間という時に、おそらくそれが国家的なチッソのようなアセトアルデヒドを生産するということが、公共性であるという考え方もあります。電力は公共性だとか。そういう公共性というのは間接的な公共性だということを、この映画は言っているわけですね。そこに直接的な公共性があるんだ。それは生存学的な発想とかかわってくるところだと思いますが、縁側という公共性、公共空間、海という公共空間、そういうもののあり方を、この映画は、はっきり語っていると思います。この2点だけ、補足しておきたいと思います。
司会:ご質問があれば伺いたいと思います。資料をごらんになってお気づきの点でも。
質問:水俣病については教科書とか報道くらいのことしか、75年生まれで京都なので、詳しく知っているわけではないんですが。映画そのものはとっても素敵で楽しく見せていただきました。でも作品の背景を解説していただいて、深く理解できました。知らなかったこと、天草の地方の人たちに水俣病の患者さんがいて差別があったと。私が天草で連想するのは「からゆき」さんの人たちのこと、貧しくて売られていった女性たちのことですが、構造的な差別と産業が発達していることなど、たくさんの問題が重なっていることは漠然と想像してはいたんですが、具体的に教えていただいて、映画の中で深海の風景を見せていただいたことは深く考えさせていただきました。 映画を見ていて、映像の美しさもあると思いますが、単純にその風景のところにいってみたいという気持ちがわくというか。京都では海も、そばになくて、今、妊娠していますが、テーマが子どもということで、たくさんの子どもたち自然とともに暮らすこと、風景の映画を見ていて、月との関係とか素朴なことを考えることが大切だと。もっとたくさん見てもらったらと。京都だったらどこで見られるのだろうと。行ってみたいなと思える美しい景色だったと思いますが、経済的なこと、コミュニティとしてどうあるべきか、時間が30年ほどたっていると思いますが、現在の深海は、どんな雰囲気になっているのか、教えていただければと思います。
土本:今の深海のことは、わからないのですけど。私と土本が会う3年前にできた映画です。この映画の中に出てくる兄弟たちは養殖業についていると思います。撮影当時も一本釣りではなく、養殖につく人が増えていったということで、一本釣りをしている人がいるかどうか。 深海に似ている例としては天草の御所浦島があります。水俣の近くで、ここもフグの養殖をやっています。フグの養殖はホルマリンを使います。ホルマリンはよくないといわれますが、虫をとるためにつかっていました。それで海が汚れてホルマリン汚染になりました。いまは使っていません。 いま、養殖魚の値段は下がっています。御所浦島は夏ミカンを山の方でやっているのですが、今の天草の漁業は養殖に転換したところが多いので、たいへんだろうと思っています。 でも、天草はよいところです。景色もいいし、山も美しい、海も美しいです。キビナゴとかおいしいですよ。
栗原:資料8ページに養殖が多いという話が出ていますね。遊魚船、都会から釣りにやってくる客に船を出すことで生計を立てる。それがまた民宿と船が系列化されていて。描かれている一本釣り、鉾で突く漁法は、ほとんど死滅の状態だと思います。水俣病患者の方で漁ができる人は意識的に一本釣りをやっています。緒方正人さんは太刀魚の一本釣りをやっています。意識を持ってやっている方が、水俣病患者の中にいらっしゃるということでしょうね。
司会:今日は長い時間、ありがとうございました。公開講座シネマで学ぶ「人間と社会の現在」、第13回「海とお月さまたち」の上映、対談を、このへんで終了したいと思います。
Copyright © 立命館大学 All rights reserved.