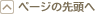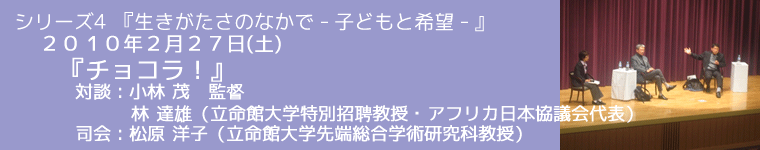
司会 それでは対談に移りたいと思います。林達雄先生から映画について、口火を切っていただけますでしょうか。

林 こんにちは。林達雄と申します。私自身は25年前からエチオピア、ケニアで飢えの問題、エイズの問題にかかわってきました。日本にこういう問題が伝わる時、厳しいというか、悲しい場面ばかりが先行してしまって、私たちがアフリカに行った時、底抜けの明るさが、なかなか伝わらない。生のアフリカが、なかなか伝わらないことが、いつも残念だなと思っておりました。この映画を興味深く拝見しました。まずは小林さんに、映画の中でも「小林さんの病気が治りますように」と字幕が出ていましたが、腎臓の病気だそうですが、病気を押してまで、どうしてまた、こういう映画を撮ろうと思ったかというあたりをお聞きしたいと思います。
小林 聴こえますか? ついついデカイ声が出るんでね。
林 監督業をやっていると、そうなるんですか?
小林 つい力が入るんですね。私も学生時代を含め長い間京都にいましたので、立命館大学の昔の広小路校舎には、よく遊びにいきました。こんなに立派な校舎ができて、本日は呼んでいただいてうれしいです。
15年前、ケニアの西隣のウガンダに、エイズ孤児の写真取材に行く機会がありました。そのとき、この映画に出てくる松下照美さん――テルさんと呼んでいます――が同行者の一人でした。テルさんはすっかり子どもたちに魅せられたようで、その後、アフリカに移住し、ケニアでNGOモヨ・チルドレン・センター(以下モヨ)を立ち上げたわけです。ティカという地方都市で、学校支援や孤児院の運営、路上で生きる子どもたち(ストリートチルドレン)のケアをしています。
2005年11月、長岡(新潟県の私がいる町)のそば屋で、テルさんが「アフリカの子どもたちの今を映像で残せないだろうか」と切り出したんです。「お互い病気もして、今がいいんじゃないの?」と。テルさんも私も、脳梗塞を経験しています。
持病の腎臓病は大分進んでいまして、透析も近い状態でした。私もウガンダ以来、きびしい状況の中でも笑顔を忘れない子どもたちの記憶とともに生きてきたもんですから、すぐに決心をしました。早くしないと、人工透析になってしまうからですね。
主治医は、シャント手術(※)を条件に協力してくれました。多くの方々から映画製作のカンパをいただき、半年後に出発しました。2006年、5ヶ月間の滞在でした。
※ 血液の取り出し口を確保するために腕の動脈と静脈をつなぐバイパス手術のこと
林 きっと子どもたちもまた、一日一日をチャレンジしているんだと思いますが、小林さん自身も病気とのおっかけっこというか、チャレンジだったんですね?
小林 あんまりそういう自覚はなくて、透析になったら、えらいこっちゃな、と思うんですけど。もし健康だったら、「そのうち、考えておくわ」なんて言ったかもしれませんね。人間というのはおかしなもので、時間があるときはやらなくて、切羽つまってレポートを書くとか、今回はあまり考えずに行ってしまったという感じなんですね。
林 わかります、私も実は10年前に直腸のがんになりまして、その時から逆にチャレンジしたい、動きたいというか、命そのものよりも、もしアフリカに行けなくなったら、どうしようと思ったくらいですから。
僕のイメージでアフリカというと、わりと賑やかな音楽の中にあるアフリカなんですが、今日の映画を拝見しますと、静かな音調で、音を非常に押さえてあって、最後に子どもたちの宴のところと、ラストシーンのところだけが、ガーッと盛り上がるという、何か意図して、そういうふうにしたんですか?
小林 確かにおっしゃるように、向こうにいくと楽しくなりますよね。
林 なっちゃうんですよ。
小林 街中にリンガラ風の音楽(※)がガンガン流れていて、まともなスピーカーが1つもないという。 ※コンゴ民主共和国(ザイール)のキンシャサで発達したポピュラー音楽。ルンバ,コンゴ・ジャズ,ザイーレアン・ミュージック,スークースとも。欧米からの移住者のもたらしたキューバ音楽と現地の音楽が融合した,エレキ・ギターを中心とする音楽。(「kotobank」参照)
林 そうですよね。
小林 スピーカーの音が割れている、そのビリビリ感がまた好きというか、そういう感じですよね。テレビがあれば皆で見てるし、ちょっとした宗教団体が空き地でタイコたたいて踊りながら布教している。そういう喧騒の町ですよね。にんげんくさい感じというか。映画は子どもの心情に寄り添う形になっていきましたので、あまり余計なものは入らなくなっていったんですね。実は音楽も入れるつもりはなかったんですよ。
林 全然、何も入れないで?
小林 そうなんです。ところが、男の子が森の中で水浴びをするシーンが映画の中で4回くらい出てくるのですが、同じ子なのかどうか、気になるらしいんですね。そこで、その水辺のシーンに、毎回、同じ音を入れることにしました。その楽器が親指ピアノ※です。(客席に見せる)。演奏は音楽界の風雲児、サカキ・マンゴーさん※。アフリカと出会い人生が変わった1人ですね。
ここは象徴的なシーンで、話の筋とは関係なく、ちょっと休憩して、映画の中の子どもたちの内面を感じてもらいたいと思っています。
男の子はチョンバ(13)といいました。街に出てきたばかりで、「ギブミー・チャイ」(お茶代頂戴)と歩き回っていたのです。仲良くなって、主人公にできたらと思ったんですが、突然いなくなったんですね。でも、水辺のシーンはとってもふしぎな空間で、編集の方の機転で映画に残りました。
ところで、これが子どもたちが吸っているシンナーです。皆さんで手にとって見てください。現物主義なもんですから。(小さなプラスチック製の酒ビンを客席に回す。中にあめ色に固まったゴム系接着剤がこびりついている)。
※親指ピアノ。板や共鳴箱に細長い金属片の一端を固定し、反対側を指で弾いて音を鳴らすシンプルなアフリカの民族楽器。演奏される地域によって、ムビラ、リンバ、リケンベなど、さまざまな呼名や種類がある。
※サカキ・マンゴー。1974年生まれ。アフリカの楽器・親指ピアノの可能性を日本から更新する「親指ピアニスト」。現地調査を自ら行いアフリカ各地の伝統的な演奏スタイルをふまえつつ、テクノもパンクもファンクも音響派も通過した現代日本人ならではの表現を展開している。http://sakakimango.com/
林 シンナーが出てきたり、子どもかタバコを吸ったりとか、どっきりしますけど、あるものは、あるがままに出そうとされていたんですか?
小林 そうですね。ストリートの日常の暮らしぶりをそのまま見てほしいと思いました。カメラの前でシンナーを隠すようでは、彼らの「日常」とは言えませんものね。そういう関係になるには時間もかかりましたが。
それから言葉の問題ですが、子どもたちはキクユ語※でしゃべっているので、まったく分かりませんでした。でも、なんだか、撮影している時は、分かったような気分でいるんですね。日本に帰ってきて編集部に「翻訳をどうする?」といわれて「そんなのいるの?」といったくらいで。
※ケニアでは部族により42の言語が話されている。スワヒリ語と英語が公用語。
林 なるほど。
小林 たとえば映画の中に、早朝、7、8歳から14、15歳の子どもが10人くらいで輪になって、ダンボールを燃やして暖をとっているシーンが出てきますが、もし自分が小学校1年生くらいの時のことを考えると、5、6年生がしゃべっている内容なんか、ちょっと分からなかったりするでしょ。でも、なんとなく仲間に入れてもらって、やっていくじゃないですか。そういうふうな感じでカメラが自然にそこに居られたらいいなと思いましたね。あとで翻訳されたものを見ると、子どもたちは結構、我々のことをボロクソに言っていますね。「そこの鶏でも撮っていろ!」とか、「チャイをおごれ!」とかね。何か言われているなと感じますが、まあ、知らんぷりしてます。おたがい言葉が分からない方がいいことも、あるかもしれませんね。
林 ずいぶん、こづかれたり、ひどい時はカメラに靴を投げられたり。
小林 あれは、うまいこと、当たってましたね(笑)。それから、「あいつらはテルミに告げ口したりしないから大丈夫だ」と言ってるんですよ。
司会 タバコとかシンナーとか、そういうシーンも特別視してないぞと。
小林 モヨの活動で、スタジシムでサッカーやってお昼にパンを食べる時には、シンナーを持って来ないという約束になっています。しばらくでもシンナーから離したいというのがテルさんの願いです。ムトゥリという子が、シンナーを取り上げられて泣いていましたね。
私たちはシンナーをいけないとか、タバコはいけないと言いに行ったわけではなくて、映画を撮りに行ったわけですから、私たちの前では何をやっても僕らは何も言わない。ただしシンナーが良くないことは私たちも分かっていますよ。シンナーはどんなふうに酔うのかなと、私も吸ってみました。
林 あ、ほんと。
小林 1日中、頭が痛かったですね。お酒のように酔えるようになるには相当「訓練」が要りますね。だいたい朝早くから撮影すると午後は疲れちゃって、ストリートの子どもと遊んでいるんですけど、ごろんと道端でよく寝ていました。いつもムズング(外国人)が寝ているぞ、というそんな感じでしたね。
林 あまりいい子ちゃんになってしまうと、映画としての面白みが欠けるんじゃないかなと思うんですけど。特にこの映画の援助者といっていいのかどうか、照美さんの位置が、どうなんだろうと。何か助けている側の人が目立ってしまうと映画自体が白々しいものになってしまうのではないかと、おこがましい言い方ですけど、そんなふうにも、ふと思ったんですけど。照美さんの位置はどういうもんでしたか?
小林 テルさんは徳島の散村で自給自足のような生活をしていたんですが、パートナーの方が亡くなったこともあって、それでたまたまアフリカに行ったんですけど、はまっちゃったんですね、子どもたちに。求めるものと、求められるものが、ジグソーパズルのようにはまった時には、すごくいい人間関係ですね。
テルさんは「援助」のために向こうに移住したというよりは、子どもたちとずっと一緒にいられるにはどうしたらいいかと考えた結果、NGOをやればいいんじゃないかということで始めたようです。政府にNGOの担当窓口がありますが、なかなか認可が下りない。何回も足を運んで、いつも書類が下になっているのを上にやってもらって、とうとうNGOを立ち上げました。ワイロは使わないと決めていたようですけど。
そんなテルさんを主人公にしたら、よくありそうなテレビ番組ですよね。これは違うじゃないかと。しかし、テルさんの長い活動があるから、私たちも街の人たちや子どもたちから受け入れられるという面もあります。そこはジレンマですね。ですから、テルさんを主人公にしない。モヨ・チルドレン・センターの活動の紹介の映画にはしない、ということはあらかじめ決めました。ただ、無理にテルさんを排除しない。テルさんがいなければ、子どもたちの実家に行くなんてことは短期間ではできませんものね。ともかく、「路上で生きる子どもたちの日常を丹念に描く」という気持ちでした。
そこから見えてきたことは、私たちは既成概念の固まりのわけですよね、アフリカや子どもたちに関して。
林 アフリカに滞在を続ける一番よい方法として、NGOを使ったという話、いいですね。
小林 アフリカをとりあげたテレビのクイズ番組なんか見ていると腹が立ちませんか。たいてい、アフリカの奥地に行って奇習、風習をとりあげて、「さて、これは一体、何に使うものでしょうか」とか言って、スタジオでは回答者がピンポンとボタンを押して答える。あれはね、ほんとに失礼な話でね。でも、考えてみれば私もそういう目で見ていましたね。アフリカというのはビルディングがあるのか、行ったらいきなり象しかいないんじゃないかとか。すごく作られたイメージがあるわけね。図書館でいろいろ調べると、藁葺きみたいな家で石を3個置いて、その上に鍋をおいて調理している。ケニアで有名なのはマサイ族でね、勇敢な。そういう感じなんですけど。
行ってみればナイロビは大都会で人口200万人もいて、そこに隣接して野生動物がいる。また、ケニア世界最大のキベラスラムがある。宗主国の英国が鉄道を敷いたりする時に労働力として集めたことが起源だと聞いていますが。「ナイロビの蜂」という映画で有名になりましたね。
林 ナイロビの町というと、ビルも建っているんですけど、ビルを囲むようにスラムがあって、そこに100万からの人が住んでいる。ナイロビの町はスラムに包囲されているんじゃないかと思います。
小林 朝になるとすごい人数が中心部に働きにいくので、長い行列ができていました。スラムにもきちんとした自治があってね、そこは家賃も高いですし。そういうところからはじき出された人は近郊の地方都市へ移ると聞きました。映画の中に出てくるティカのスラムもその1つです。
私もスラムといえば、おっかない(こわい)所というイメージでした。カメラマンも混雑した撮影中に、ジャケットから金をとられたこともありました。それはそれで諦めて、そのお金で酒でも買って皆で楽しくワーワーやってくれているだろうなと思いましたけど。
林 なるほど。
小林 ただスラムの中に入ってみると、HIVに感染したルーシーさんと2人の子どもの場面ですが、お隣さんに子どもを預けて洗濯に稼ぎにいきますね。そのおばさんもエイズで、その体験の語り部をしていましたが、体調が悪かったですね。ルーシーさんとは、親戚とかではなく、エイズ撲滅の活動をやる仲間でした。小さい金網窓のキオスク(雑貨屋)をやっているのですが、お店の内側にいると面白いんですよ。朝は近くの人がチャイ(ミルクティー)に入れる牛乳やパン、たばこ(1本)を買いにくるのですが、「どうしてるの最近は」なんて声かけてね。子どもが飴を買いにくると、「しっかり勉強しなさい」とかね。
そういう中でね、助け合いの精神がすごいじゃないですか、アフリカの人たちは。そういうことをね、ほんとに知ってもらいたいと思うんですけど、我々のイメージはステレオタイプ的に「貧困」とか「飢餓」とか「紛争」とか、マイナスイメージじゃないですか。そういうことはもちろんあるわけですが、彼らとつきあってみて、映画を撮るということは、自分の持っている既成概念とどう向き合うのかということなんじゃないかと思いましたね。
林 ほんとに、そう思います。アフリカのイメージでいうと、既成概念として可哀相な人、辛いと考えがちなんですけど、そうじゃなくて、HIVとか病気になっている人も、今日、1日を楽しむという、日本の人と比べても楽しむ力、1日1日を大事にする力を非常に強く持っている。もう一つはお互いに助け合う。ケニアだとハランベ、南アフリカにいくとウブントゥというんですが、助け合い、共に生きることをしめす言葉があり、どんな暮らしをしていても、助け合っているんですね。切ない話なんですけど、「もしあなたが、私より先に死ぬことがあれば、あなたの子どもを私が養うから、私があなたより先に死ぬことがあれば、私の子どもを養ってください」という究極の助け合いですけど、エイズの人たちの間である。僕に言うんですね。「いつまでスラムにいるの。今度はいつ来るの?」。スラムで一緒に歌って踊りながらなんですけど。「1年後だよ」というと「それでは遅すぎるかもしれないわ。それでは私はこの世にいないかもしれないわよ」という意味なんですが。実際に行ってみますと、ほんとにこの世にいない。会うことができないという体験をしてきました。そういうエイズの問題は日常的に非常に大きいし、映画に出てきたルーシーさんのように明るい。2000年前後まではエイズの薬が手に入らなかったのが、ようやくここ数年の間、入るようになり、それまでならば死なないといけない人が死ななくて済むようになりつつあります。そういうことを一生懸命やってきた自分自身にも褒めてやりたいと最近思っています。
アフリカが私たちを必要とする以上に、私たちにとってアフリカが必要なんじゃないか。アフリカから学べることがずっと多いのではないかと感じ、パワーをもらって帰ってくる気がします。
小林 そうですね。元気になりますね。公立病院にはエイズの無料窓口がありました。検査して陽性であれば、治療薬ももらえます。しかし、エイズであるとカムアウトすることは勇気がいることで、よほど体調が悪くなってから家族や親戚に打ち明けるケースも多いようです。さっきのキオスクのおばさんもそうでした。
ルーシーさんにスラムの暮らしを聞いたことがありますが、そしたら、家賃が安いということもありますが、「ここではほんとうに自分の気持ちを正直に出して、お互い助け合いながら生きていける」と話されました。彼女はクリスチャンで自分の人生は神に委ねているということでしたけれども、子どもを育てることに精一杯でした。その前を向いて生きる姿に感銘を受けましたね。
最初はエイズ問題にとくに触れるつもりはなかったんです。ただ実際に、働き盛りのお父さん、お母さんがエイズで亡くなくなり、孤児になるケースがしょっちゅうですので、後半になって、エイズに触れないのはかえって不自然なような感じがして、テルさんから紹介してもらって、ルーシーさんを撮らせてもらったんですけど。
5歳になるマイケルという甲高い声をしている男の子が、なかなかいいんですね。ルーシーさんの洗濯仕事の続きのように、マイケルがごしごし洗われる場面は思わず笑っちゃいますね(笑)。それまでずっとストリートで撮っていたものですから、スラムの一室だけど、ソファとベッドがある。寝る時もベッドに3人いっしょです。長女は逆向きですが。小さな幸せを感じながら現場にいました。
途中でルーシーさんを訪ねてきた女の友だちがいましたが、彼女も感染者です。ルーシーさんは「石鹸いるんじゃないの?」と笑いながら黄色い小箱を渡しますが、あれは教会で配られるコンドームではないかと思います。いつもならルーシーさんはその友だちと夜出かけていくのかもしれません。長女が「お母さん、今日、出ないの?」という言い方をしていますから。その日は、寝るまで撮影をお願いしたこともあって、ルーシーさんはこの夜は外出しないようでした。
あのつつましい夕食も、映画を撮るからということで、ご馳走だったかもしれません。その日はお母さんがいて、マイケルがすごく甘えて、「一緒に寝ようね」とはしゃいでいました。日頃は長女がマイケルを寝かしつけるのかもしれません。
このルーシーさんのシーンは、ストリートチルドレンをテーマにした映画に入ると違和感があるのではないかと最初思いました。しかし、何回も見ていると、ストリートの子どもたちが幼い時、マイケルのように幸せな時があったのかもしれない。また、ルーシーさんが亡くなった場合には、2人は孤児になるわけですが、ストリートの子どもたちのようになるかもしれない。そんな風に考えるとこの場面も意味が深いように感じました。
林 そうですね。あのシーン、ルーシーさんのシーンは決して特殊なものではなくて、今、あたりまえのようになっている。エイズ治療が若干進んできたところもあって、子ども自体が亡くなるケースは減ってきているけども、エイズ孤児の問題はかたづいていない。このままではケニアも南アフリカも皆、子どもたちがストリートチルドレンになってしまうのではないかと10年前、思っていました。
10年たってそれが現実のものになっていることを目にして、悲しく感じます。悲しいけど、悲劇はこの映画で見せていただいたような、底抜けなポジティブな生き方と同時に存在します。病気も生きることを難しくすることの一つですけど、たとえ病気であっても彼らは一日一日を希望すらもって生きているという感じを受けました。
小林 松原先生(司会)ともさっきしゃべっていたんですけど、貧困=ストリートチルドンみたいな感じは、もうやめた方がいいと思いますね。また、極端な話をすれば、アフリカを援助の「対象」として見ることも、やめた方がいいと思いますね。「援助する側と受ける側」という関係ですね。これはちょっとでかい話ですが。
ルーシーさん一家の夕食の前に、長女のお祈りが映っています。「お母さんに仕事が見つかりますように」、そして「コバの病気が良くなりますように」と、私の病気のことを祈ってくれているわけですね。それは撮影が終了して1年後、翻訳されてはじめて分かったのですが、その瞬間、電気のようなものがからだを走りました。非常にショックでしたね。ストリートチルドレンの原因をグローバリゼーションの中に提示するという気持ちも失せましたね。それこそ、ステレオタイプ的で、そんなんではなく、自分の手の届く枠の中で、そこを深く掘ろうと思い直しました。
私はいかにも子どもの目線で映画を撮ろうとしていたんですが、やっぱり、いい歳をしたおやじであり、一人だけですけど娘がいて、親の目線でいえば、心配するのはこっち側で、子どもたちは心配される側だと思っていたんですね。けど、あにはからんや、私のことを子どもたちが心配してくれているんですね。私の方が心配される側だったのです。私は子どもたちのことを祈っただろうかと。映画のことばかり考えていて恥ずかしいかぎりです。
そのことを考えると、つまり「心配する側と、心配される側」という関係を越えるためにはどうすればいいのか。そうすると「自分自身の思春期」というものと、重ねていかないと、どうしても子どもたちの心情は見えてこないんじゃないかと思ったんですね。
みなさん、どうですかね。子ども時代に家庭内のいろんな嫌なこと、そういうことを表だって友だちや先生に言ったりしないですよね。今の虐待されている子どもだって、殺されるまで、こうやって自分を躾ているのは、僕がいい子になれば、愛情を注いでくれるんだと思うから、誰にも本当のことを言わないし、逃げ出さないわけですよね。私も両親のけんかで茶碗が飛び交うような家でしたけど、そういうことを学校へ行って先生に言うとか、友だちに言うとか、なかったですね。
映画では、先生や大人が「どうして学校に来ないのか、ストリートに出るのか!?」と質問しますが、皆、「ナッシング」(別に)と言いますよね。そういうことから私はあえて1つの答えを求めることはやめました。問いはあっても答えがない映画かもしれません。
ただ、自分の思春期のことを思い起こせば、先は見えない。一度こじれた父親との関係はなかなか元に戻らず、たいてい、男ですとね、30歳くらいになって子どもができたりして、「親父もこうやって育てくれたのかな」と思ったりね。そんな感じだと思うんです。そのへんの感覚はいっしょだと思うし。ただ、かれらは、何しても、今日、どうやって生きようかということで、そこはね、サバイバルなんですね。本来、生きていくってことはおもしろい。自分の肉体を自分で養っていくこと、生きていくことは、すごくおもしろいことなんではないかと、子どもたちが言っているように思いましたね。
それで、ちょっと話はもどりますが、映画の中で、はだかのシーンが何回か出るのですが、皆さんは、どう感じましたか。身体つきを見てほしいんですよ。そんなに食ってるわけじゃないのに、食べたものは全部、血にし、骨にし、肉にするぞ、という生命体としての身体ですよね。それがね、水に入ると、黒い肌というのはエナメルの鉄板のように光るでしょう。いいんですよね。こういうギリギリ生きている子どもから出てくる光みたいなものを、感じとてほしいと思っています。
林 ほんとに、なんかびっくりするくらい、細いけど、鋼のような身体をしていますよね。
小林 そうですね。食い溜めができますから、彼ら。孤児院に来ると腹いっぱい食べ続けるそうです。食べたものを吐いたりして。とにかく今、目の前にあるものを、食べられるのは今だと。ちょっと盗んだりしてベッドで食べたりね。3カ月くらい経って、ここはきちんと食べられるんだと実感してくると、無茶食いは止まるそうです。本能ですよね、目の前にあったら他人の分でも取って食べる。そういう逞しさはありますけどね。
林 最初、ストリートチルドレンで、きたないんじゃないかという印象を受けますが、川で洗濯して洗っているシーンを見ると、結構、きれいなんですよね。
小林 そうですよね。服はぼろぼろですけどね。あまり臭わない。湿度がそう高くないですから、それで過ごしやすいんですね。日本で2、3日、夏なんか風呂に入らないと、臭いし、たまったもんじゃないですよね。ケニアは過ごしやすくてお勧めですよ。旅行はケニア。1500メートル以上の高地でね。英国人がいい所に町を作ったのが、ナイロビということですから、押してしるべし、ですよね。あのサバンナ。皆さん、行ってみてください。飛行機が飛んでいるところにすぐ、ナショナルパークがあります。キリンがいたり、象がいたり。中心部から車で30分くらいですよね。
林 ほんとにいいところですよ。いいところだというと、いけないかもしれないけど、近代的なビルもお洒落なビルが多いし、サバンナがあって動物たちがいて、アフリカというと気候が悪くて病気になっちゃいそうな印象を受けるかもしれないけど、そうじゃなくて気候がいい。皆さん行ってみたらいい。ただ僕自身はね、アフリカに行くと悩むのは、本当にいいところで、リゾート地もすばらしいわけですよ。もう一方、スラムに行くと、うんときたないわけですよね。その格差で頭がクラクラして、同じ国でこんなに違うのかと思ってクラクラしそうになるんですけど。だけどスラムもまたスラムの中に入りこんでみると、これがまたあったかいんですね。愛情に溢れているというか、民泊するところに泊めもらうと、こんな、あったかい、ぽかぽかしたところもあるんだと。逆説的ですけど、両方のアフリカを、ぜひ見てもらいたいなと思います。
小林 排水路もちゃんとしていない、臭ったりしますけど、行くと元気になりますね。それに日本も昭和20年代、30年代なんか、僕の田舎では裸足で遊んでいましたし、まっ暗い道を、走ったもんですよ。アフリカで自転車の荷台に乗せてもらったことがありますが、真っ暗な細道を疾風で走るんです。逆に野性味がいかに自分になくなったかと思うんですけどね。アフリカへの順応は早いと思いますが、かえって日本に戻ってから僕はだめなんですね、しばらく。自動販売機で水を買う。その100円なんて、子どもたちは2日くらい働いてやっと稼げるお金ですもんね。電車が3分おきにピッピッと来る。あれなんか、信じられないですよね。
林 信じられないです。日本に帰ってくると、今まで極彩色の世界、いろんな色のある世界にいっていたのが、急に灰色になってしまって、これは困ったぞ、という状態に陥るんですね。
小林 この映画を見て、ケニアを訪ねたいという人がたくさんいます。モヨも大歓迎です。昨年はこの映画とともにモヨの「子どもたちの家」の設立キャンペーンをして、昨年末に着工しました。何とか、途中で終わらないように、皆さんに継続してカンパをお願いしている状況です。
林 アフリカを好きな人、照美さんが大好きだから、わざとらしさがない感じがするんですよ。やっていることは小さなことなんですけど、その仕事の中で大きなことは、多分、私たち、アフリカを知らないものにとってアフリカを知るものがアフリカが見えてくる、一つの窓になってくれているのではないかなという気がします。私たちが少しずつ支援しながら窓を充実したものにしていくことは大事なことだなと思います。
もう一つ私自身、今回(2009年11月に)アフリカに行ってよかったなと思うことの一つは、エイズ治療薬が行き渡るようになってきたことです。つい7、8年前までは年間エイズで毎年300万人の人が死んでいました。ところが今で毎年に死者が200万人に減ったのです。年間100万人の人が生き残るようになってきた。私も運動して岩波新書にも書いていることですが、世界の誰もがエイズ治療薬をえられるように国際的な連帯運動を10年前にした結果、エイズ治療薬が普及するようになってきた。明らかに変化が見える。そういう努力がなければ、声かけが、なければ死んでいったはずの子どもが立派に生きている。「この子、生きているよ」という、そういう変化が現実に見られたこと自体が、自分自身に対しても「あ、頑張っているね」と褒めてやれるような気持ちがしています。小林さんからグローバリゼーションに対して、という話がありましたが、世界を変えようと、あまりに不公平な世界を変えようという動きも、やって、うまくいく時もあるということを、皆さんに知っていただきたいなと僕自身は思っております。
小林 林先生がお書きになった岩波のブックレット「エイズとの闘い」。非常におもしろいです。お勧めです。
司会 林先生はご自身お医者様で、ホワイドバンドで有名になった「ほっとけない世界のまずしさ」というNPO活動の先頭に立ったお方です。長年、HIV/エイズの問題に取り組んでおられます。それではここで、会場の皆さんに感想でもご質問でも、何でも自由にお話しいただきたいと思います。いかがでしょうか。
質問 映画を見ていて気になったことがあって。子どもたち、ケニアに住んでいる方を見て、明るくなったんですが、女の子が、あまり出てこなかったな、という印象があって、それはなぜなのかをお伺いしたいなと思います。
小林 国によって違うようですね。ドキュメンタリー映画や本を見ると、フィリピンのスモーキーマウンテンとか、モンゴルのマンホールチルドレン、ブラジル、メキシコとかにはストリートに女子がいるようです。ペルーの映画でしたが、リマの路上で女の子の姉妹が芸をしてお金を稼いでいました。その場合は、遠くからお母さんが見守っていましたが。ティカには子連れの若夫婦がいました。夜はスラムの片隅で寝ているようでしたけど。他の町はよくわかりませんが、女の子はあまり見かけませんでした。昔、日本も貧しい家の女の子は子守りに出されたように、ケニアでも親戚に預けられて家事手伝いをしたりと聞きました。学校に通えているかどうかは別として。夜の仕事の方たちはいますよ。街に立つ女性ですね。
司会 女の子の場合には何らかの形で大人相手の仕事があり、強いられて、ということなんでしょうか?
小林 具体的には様々でしょうが、どの世界でも、大きくなれば、ね。いずれ幼い頃は親戚に引き取られたり、孤児院などの施設に預けられたりしています。さっきも言ったように、そういう相互扶助が強いですから。ただ、あっちこっちから預けられても限界がありますから、街へ出て行ける年齢になれば、追い出されるとか、自分で出て行くとか。
司会 マウラ君、14歳のリーダー格の男の子。彼はお母さんと義理のお父さんがいて、家にいようと思えばいられるはずなのに、学校に行かずに町に出ている。映画に出てきた子どもたちのなかには、誰か家族はいて、そう居心地がよくなくても、家がある子どもたちがいますね。学校に行きたいんだけど、いじめられたとか。それで家を飛び出てしまう。一つは、そういうことは男の子に多いのかなと。マウラ君のお母さんの困り果てた表情に、アフリカも日本もなく共感してしまいました。日本でも家にいられない、学校にいられなくて、町に出ている子もいますよね。ストリートチルドレンといっていいような暮らしをしている子どももいる。一見豊かな中での「貧しさ」や、親はいるけど学校を出ていって道で暮らしている日本の子どもと、「チョコラ!」の背景にある社会や子どもとの違い、共通点とか、ありましたら伺いたいのですが。
小林 何でも思春期という言葉で片づけるのはいけないんですが、7、8人の子どもがいて、スラムの狭い部屋で暮らしていれば、思春期の頃には家を出たり入ったりしますよね。映画の中でも児童局の女性担当者が、「あんたよく(貧乏なくせに)7人も産んだわね」と言うと、赤ちゃんにお乳をふくませたお母さんが、「彼氏の要求を断れるかしら」と、2人で笑うシーンがありますが。子どものお父さんがそれぞれ違うという場合もあります。それは性の問題とすれば、日本の感覚とは違うところもあるでしょうね。
狭いところに、小さい子どもはしょうがないにしても、思春期の子どもがいられない状況があるわけです。そこに男性が来るような場合にはとくに。腹をすかせていますから、働けるようになれば、稼いで食いたいわけですよね。さっきのお母さんは「食べ物はあるし、昼飯代は渡しているし、洗濯はしてやっているし」と学校の先生に言っていましたが、生活ぶりをみると、なかなかそうではないですね。子どもを近所に預けて、ゆでたトウモロコシを売りに行ったり、賃仕事をしているようでした。
マウラは乾燥地帯の貧しい小作農家が実家なんですね。そこにいるよりは町へいって一旗上げようという感覚ではないでしょうか。あの子は英語もできて才覚がありましたね。家に帰った時、車から降りて「あ、お兄ちゃんが帰ってきた」と弟妹が寄ってきて、お父さん、お母さんが出てきますが、マウラはポケットから札を出して、さっとお母さんに渡すんですよ。これは、わからない人が多い。実は私もそうでした。だからこの映画は2回見る価値があるんですね(笑)。
ストリートの子どもが実家に帰る時は、朝から1時間くらいおめかしですよ。こうやってね(頭を洗うまね)、身体を洗って、油をつけて、いい服を着て。マウラはお土産を買いたがっていましたね。家に帰るときには小ざっぱりした恰好を見せたい。彼らの意地ではないでしょうかね。そういう感覚で見ると、そんなに日本と変わりはしないかなと。
家にいて、自分の仕事があって、生き甲斐があるということであれば、そこにいるかもしれませんが、でもあの年代はねえ・・・。自我が出てきて、なんか家を飛び出したい。広い世界を見てみたい。その気持ちはわかりますね。私もそうでしたから。貧しいことはわかっているから自分の分は自分で稼ぐ。
ただし学校へは行きたい。やっぱり小学校(8年制)はみんな卒業したいと思っていますね。子どもたちが「学校に行きたい」と、大人たちや児童局に訴えることは、権利としてあるわけですよ。でも早くから学校をドロッフアウトしていますから、なかなか難しい面もある。小学校では自分の生まれついた言葉とちがうスワヒリ語と英語を習うわけで、4年生以上は原則的に英語で授業することになっていると聞きましたけど、勉強も大変だと感じました。
アントニーなんか14歳でしたけど、かれのクラスに行きましたら小学校2年生の教室でした。かれはもちろんいちばん大きいから目立ちました。もし、かれの立場だったら、なんか嫌ですね、こんな小さい「同級生」といっしょに勉強するのは。
ストリートの子どもたちに、いじめや自殺など、日本の子どもたちの現状を言うと、なんで、あんな裕福な国が?とふしぎそうでした。物を盗ったり、喧嘩したりはあるでしょうが、かれらは自殺など考えたこともないようでした。テルさんもそう言っていましたね。何かの数値を基準にすれば比べられるかもしれませんが、「しあわせ」という尺度では比べられないと思いましたね。私は今の日本の子どもはとても精神的にきついと思っています。いろいろな格差が広がって、「貧困」問題がどの先進国といわれる国々でもありますよね。一方、アフリカは、子どもはよく死にます。マラリヤや医療・福祉の不足によってですね。エイズ孤児も多いですし。しかし、ティカのコーヒーやパイナップルのプランテーションの周りは大豪邸がたくさんあって、玄関から建物が見えないほどでした。
世界の子どもたちを、一概に比べられないと思いますが、ただ、1人ひとり、それぞれに、自分らしさというか、自分なりの「ほんとうの幸せ」を求める環境、たとえば、衣食住とか学習とか、職業訓練とか、子どもの権利とか、生きる希望とか、そういうものを子どもたちは、当たり前ですけれど望んでいると思います。
2002年に当選したキバキ大統領※の公約で、小学校を無料にしたわけです。スラムの中のこの小学校でも300人くらいが600人くらいになりました。でも予算があるわけではないですから、何もかも足りない。外国のNGOが教室やトイレを援助していました。モヨも支援していました。一割くらいのとくに貧しい生徒に給食が始まっていました。エイズ関係のNGOは学校のすぐとなりで、エイズ孤児に限定して給食を出していました。
先生も給料が少ないから、補習をしたいと言いだして、20シリング持ってこいとか。先生も稼がないといけないから。我々の感覚で社会を見ては、ちょっと違うかなというのと同時に、思春期のあの感覚はいっしょのものがあるのではないかと思いますね。
※1963年の独立以来、ケニア・アフリカ民族同盟 (KANU) から選挙で政権を奪取した初めての大統領。2007年暮れの選挙で再選されたが、対立候補が選挙の不正を訴えたことから部族対立に発展し暴動が起きた。
司会 そうするとケニアの特有の教育事情の現れの一つとして、今日の映画のようなことがあるということなんでしょうか?
小林 ストリートチルドレンの問題はずっと前からですし、その問題の根っこはやはり痛めつけられたアフリカの歴史や、最近の世界的な社会、経済のグローバル化があるでしょう。我々の日常生活が、さまざまな食料や資源がアフリカからてもたらされていますが、我々も知らないうちに彼らの貧困に加担している部分もあると思います。
司会 大人が学校に行かせたがっているということを、わかっていると?
小林 小学校8年制で卒業の国家試験があるんですが、日本でいえば高校を出たくらいの資格の意味があるんではないでしょうか。英語ができないとオフィスの仕事とか、技術を学ぶことも――ティカの町を走る車の9割くらい日本の中古車でしたが、何台かの車を組み合わ、1台の車にするなんて当たり前で、たまに斜め走り(キンちゃん走り)をしている車もあって、おかしかったですが(笑)、――エンジニアになりたいといっても専門的な勉強が難しい。そういうことはあるんですね。
ストリートに出ている自分の子どもを小学校にもどしたいと熱心なお母さんもいました。そういう気持ちは子どももわかるのでしょう。しばらく学校へ行くのですが・・・裏切られるケースが多かったですね。
社会環境の変化もすごいですね。スラムにも携帯電話が普及しています。屋根の上にどんどんテレビアンテナが立っています。世界の情勢が間近にわかる。日本がどういう生活をしているかなんかも。もうほとんど全部が日本車ですから、ソニーで、パナソニックだから。「お前らどういう生活しているのか」ということですよね。援助や国際協力で来るのは欧米が多いと思いますが、(中国もアフリカとは関係が深いですが)、来たら来たで高級ホテルを借り切って、それは治安のためだと言うんですがね、こんな水飲んでね。(テーブルの上の水が入ったペットボトルを手に取る)。
地元の人が、こんな水なんか、とても飲めませんよ。ブレックファストを食べて。「こいつら俺たちをダシにして儲けているんじゃないか?」と現地の人々が感じても無理はない。UN(国連)なんてすごいですよ。白い車に黒い字でUNと書いて、その町全体を占拠している感じ。
司会 一番聴きたい話が、終了の頃になって出てきました(笑)。
小林 今の話はね、あまりいい話ではないので、ちょっとやめておいて。
質問 思春期でストリートに住んでいる子どもたちは活力に溢れている。20歳すぎて大人になっていくと彼らはどういう生活に入っていくんでしょうか?
小林 とてもいい質問なんですけど、難しい質問でもあります。ケニアの場合は法律的には18歳で成人です。15歳までは子どもで、16、17歳がユース。18歳になると捕まれば大人の扱いになります。一般的に町の人々はストリートの子どもをあまり良く思っていません。それで「チョコラ!」と呼ぶんですから。物を盗られるとか、いろんなことを考えて、警戒する。ちゃんとした就職は難しいですね。
貧富の格差、社会の矛盾、そういうものがいちばん弱い立場の子どもに押し寄せているわけなのですが、社会はやっかいばらいをするだけで、何も救おうとはしない。これは、敗戦後の日本も同じでした。「浮浪児」を誰も助けようとはしなかった。もちろん、そういう中でもすぐれた社会事業家はいましたが。
シンナーを買ってた子どもが、今度は売人になる青年もいました。いろんな職人仕事につければいいと思いますが、弟子入りするのに逆に金を要求されるようでした。コーヒーの缶をランプにするとか、ブリキの加工とか、家具や棺桶つくり。自動車の何でも修理。ケニアの人たちは器用な人たちなんだと思います。また、屋台で何でも売っていました。中古靴、衣類。機械化が進んでいませんので、農業でいえば鍬でした。牛で鋤を引っ張るのは見ませんでした。土方仕事はよく見かけました。これらの仕事につく子もいるでしょう。
モヨの「子どものたちの家」を建てるのに市が水道管を敷設しました。機械堀ではないので一列に20、30人が土掘りをしたと聞いています。1日100〜200シリングです。(日本円換算は当時では1.6倍)。その水道管が盗まれたそうです(驚きの声)。
見張りのガードマンを増やす費用でもめたようですが。ビルや高級住宅街では夜警さん、これをアスカリといいますが、夜6時〜朝6時まで12時間勤務ですが、結構、きつい仕事です。そのわりに賃金は良くない。マサイの人は勇敢だということで、マサイの人ではないんだけど、マサイの人が使っている弓矢を脇に置いたりしていますね。
モヨは、たとえ勉強が中途半端でも、職を身につけさせたいということで、提携しているウガンダにある職業訓練校に入学させるケースもあります。いま、2人の子どもが行っています。新しくできる「子どもたちの家」でも、木工と機械と縫製というような職業訓練的なものを、取り入れたいと思っているようです。
司会 それでは残る質問などは茶話会で、お二人に聞いていただければと思います。今日は長い時間、ご一緒いただきありがとうございました。小林監督、林先生に拍手をお願いいたします。これをもちまして終了とさせていただきます。