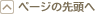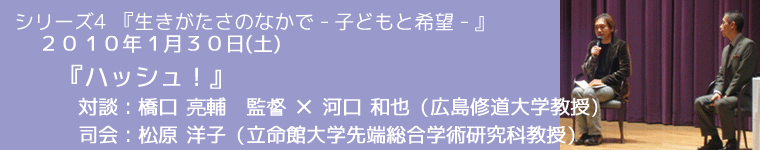
司会 橋口監督と河口和也先生のお二人に、ざっくばらんに『ハッシュ!』を巡ってお話をいただきたいたと思います。河口先生からご感想をお願いします。
 河口 私が最初に『ハッシュ!』を見たのは、私が広島に住んでいるということで、来るのが遅いんですね。心待ちにしていて、広島の劇場で見ました。その後、「コミュニティ論」という家族のことも扱う授業の中で毎年、学生といっしょに見ていまして、回数を数えると数十回、見るたびに新しい発見があって。私はゲイなんですが、ゲイの中にも子どもが好きだという人もいますし、私自身は子どもが嫌いで、なんか、うっとうしいなと思っていたんです。『ハッシュ!』を最初に見た時には、まだ(子どもをもつということに)そんなにリアリティがなくて、その先をみてみたいと。子どもと3人で新しい生活を始めていくというところでエンディングを迎えるんですが、その後の生活は一体どうなんだろうと。そのことについては私も全然想像がつかなくて、それ以降、8年くらいが経過して、その中で何回か見ていくうちに、今では子ども嫌いの私にも想像の域を超えていたものが想像の範囲のなかに入ってきたなという感じを持っています。子どもを育てるということはどういうことか。自分の生活の中に子どもがいたらどんな感じになるんだろう。自分はどういう振る舞いをして、どういうふうに子どもと接するのかと考えたりするくらいに、私もちょっと大人になったんでしょうか。
河口 私が最初に『ハッシュ!』を見たのは、私が広島に住んでいるということで、来るのが遅いんですね。心待ちにしていて、広島の劇場で見ました。その後、「コミュニティ論」という家族のことも扱う授業の中で毎年、学生といっしょに見ていまして、回数を数えると数十回、見るたびに新しい発見があって。私はゲイなんですが、ゲイの中にも子どもが好きだという人もいますし、私自身は子どもが嫌いで、なんか、うっとうしいなと思っていたんです。『ハッシュ!』を最初に見た時には、まだ(子どもをもつということに)そんなにリアリティがなくて、その先をみてみたいと。子どもと3人で新しい生活を始めていくというところでエンディングを迎えるんですが、その後の生活は一体どうなんだろうと。そのことについては私も全然想像がつかなくて、それ以降、8年くらいが経過して、その中で何回か見ていくうちに、今では子ども嫌いの私にも想像の域を超えていたものが想像の範囲のなかに入ってきたなという感じを持っています。子どもを育てるということはどういうことか。自分の生活の中に子どもがいたらどんな感じになるんだろう。自分はどういう振る舞いをして、どういうふうに子どもと接するのかと考えたりするくらいに、私もちょっと大人になったんでしょうか。もう一つの感想として、『ハッシュ!』を見る前から頭の中に漠然とした小さな疑問としてあったんですけど、カップルというのが、すごくこの世の中で強いものになっていて、つまり二人で一つの単位があって、それが根強い規範として働いているんですが、ひょっとしたら二人以上の単位というのがあってもいいんじゃないかと思ったんですね。『ハッシュ!』を見させていただくと、こんなふうに3人で生活していくということがありえるのではないか。3人ではなくても、4人とか、5人で生活をしていくことも可能性としてあるのではないかと、私の想像力もかき立てられましたし、それが少しずつ現実に近づいているなという感想も持ちました。
ちょっと子どもについて考えてみると、私は子ども嫌いというのは、おそらく子どもが異文化に属するもの、異なるものだからかな、という気もしています。つまり、子どもは他者、私と違うものという意識があって、そういう存在が自分の生活の中に入ってくることに対する、ちょっとした恐怖、心配を感じていたのかなと自己分析をしています。でも異なるものが自分の内に入ってくるというのはそんなに恐怖とか、ネガティブな言葉で語るだけではなく、何か自分というもの、自分が生活している場を変えてくれるような存在であるかもしれない。もちろん子どもは明らかに世代が違うものですし、私なんかも学生と接していますと、年々、私の考えが遅れて古くなっていくのか、学生がとどん変わっていくのかというのが、わからなくなるくらい違うものなんですね。私もおそらく学生と同じくらいの年代の子どもがいてもいいくらいの年になってきましたので、そういうことも考えてみると、違うものが自分の生活の中に入ってきて、自分の生活を変化させてくれるということもいいんじゃないかと。
映画の中ではゲイのカップルが扱われていますが、ゲイのカップルとして生活をしていても、なかなか私などは未来というものが、あまり考えられない。その場、その場で生活はしていて、時間は流れていくけど、この先どういうふうに生きていったらいいかはあまり考えることがない。そうしてみりと、じつは子どもは未来の時間を私の生活にもたらしてくれるような存在なのじゃないかと。ある意味、未来のシンボル、そういうものでもあるのではないか。もう一つは変化ですよね。未来がない、今の生活状況が閉塞しているとか、固まってしまった状態を何か変えてくれるような存在としてあるんじゃないかというような。未来を志向したり考えたりすることができるのは人間だけと言われていますが、それがある意味、苦悩である場合もあるし、喜びになる場合もあるということを感じました。
私には、『ハッシュ!』について文書にしたものがありますが、そこでは、家族というものの生きづらさについて書いています。『ハッシュ!』の中で秋野暢子さんが演じている「容子」役の人が、家族にこだわる、血統、家系にこだわるということをしているわけですが、よく考えてみるとその容子さんは外から来たお嫁さんですから、彼女にとっては、もともと家族の一員ではなかった。それだけのことにしかすぎないのに、あれだけ家族にこだわらせる、家族を守る側に立たせてしまうことを考えると、家族というのはそういう意味では生きづらいなというイメージがあります。それは、たとえば「家父長制」(の大変さ)という概念で捉えることができるわけです。しかし別の側面から見ると、家族をもう少し肯定的なものとしてとらえてみることもできるということを学生のレポートから学んだりすることもあります。ある学生は、秋野暢子さんが演じる「容子」は、(弟の同性愛をうすうす感じていて受け入れようとしていた)夫が死んでしまうことによって、同性愛という異なるものを受け入れるきっかけをなくしてしまった。他方、朝子さんたちは3人で暮らしていて、子どもを設けることによって同性愛を受け入れるような土壌を、つまり生活の基盤を作り出すことができるようになったのではないか。その意味では家族というのは、まんざら否定的な側面でみるようなものだけではないのではないかと、学生のレポートから学んだりしたこともありました。
こんな感想を持って、橋口監督にお話を伺いたいと思いますが、最初にスポイトが出てきますよね。スポイトの意味はどういうものなのか。私なりに考えてみると「男なんてあんなもんだよ」ということをいっているんじゃないかなと思ったりもしました。それを学生の前で言うと、男子学生によく思われないんだけど、スポイトの感想ではスポイトが出てくる以上に「あんな大きなスポイトがあるの?」という驚きをする人が、思ったりする。「大きさかい?」と大きさに驚くなという感じですが。橋口監督に。スポイトには何か着想があったりするんですか?
橋口 そこで振るんですね(笑)。もともと『渚のシンドバッド』という映画に浜崎あゆみというのが出ていて、当時、浜崎あゆみが17歳で、ほんとにすばらしいなと思ったんですね。で主演という感じではなかったので、あゆみ主演の映画をとりたいなと当時、思いました。ゲイのカップルに育てられた女の子が17歳の浜崎あゆみで、ちょっと一風他の少女とかわっていく。その少女が恋をする。その恋をした男の子の方にも普通の両親がいて、家族がいて、ゲイの家族と男の子の側の家族と二つの家族と、あゆみと恋をした男の子の二つの家族を巻き込んだコメディができないかなと思って考えたんです。考えているうちに「じゃ、そもそもゲイのカップルはなんで子どもをつくろうと思ったのかな」と、一応、脚本をかく前の段階で監督としては考えないとだめなので、考えているうちにそれが『ハッシュ!』になったんですね。もともとはあゆみの映画をつくろうといところからゲイのカップルが子どもをつくる話になって、それで、実際に今の二人の男性と女性が子どもをつくりましょうというコメディのベースはあったんですが、たまたまオランダに雑誌の取材にいくということになって、「橋口さん、何を取材したいですか?」「こういう映画を考えているんだけど、こういうカップルいないですかね」。ほんとにいたんですね。一杯いたんですね。それで「じゃ、お願いします」とオランダの当時の性に関する取材をさせていただく中で、ゲイのカップルと一人の普通の女性が実際に子どもをつくって、僕がお訪ねした時に生まれて1歳くらいかな、ほんとに可愛い赤ちゃんが生まれていて、3人で暮らしているお宅にお邪魔したんですけど、そこでお話を聞いているうちに「どうやって子をつくったのか?」「聞きたい?」というから「聞きたい」と。これ、これとスポイトを持ってきたんですね。普通の。これ、これと持ってきて「マジですか?」というと、オランダ政府がちゃんとそういうカップルを支援していて、スポイトで男性に精子をもらって女性が自分で授精するということをちゃんと政府のファンデーション、勉強会があって教えていると。「これでつくったんだよ」とおっしゃっていました。ああ、スポイトか。子どもの遊びみたいですよね。科学の学習みたいな。それでちゃんと子ども、赤ちゃんという命がつくられているという。
僕なんかは想像の段階では、僕たちはゲイのカップルで「二人で愛し合っているね」となっていても、そこに女性が入ってきたら、一人の女性が僕たちの間に割って入っているみたいで、いろんな人間だから感情があるんじゃないかと思っていたんですが、そこのお宅にお邪魔すると、ものすごくピースフルなんですね。3人の関係が、ほんとに平和そのものだったんですね。「これ、ほんとかな、マジかな。ウソくさいんじゃないかな」と思いましたけど、そこが『ハッシュ!』の基本的な考え方にもなったんですけど、『ハッシュ!』では朝子、直也、勝裕というのが自分たちは、あたしは一生家族をつくることはない。直也 、勝裕も男の人が好きだ。家族をつくることはない。一生自分たちは一人なんだという諦めからスタートしたという、自分たちはずっと一人なんだと。その一人なんだ、孤独なんだと思っていた人たちが、もう一回、それでも人とつながろうとして手を差し伸べあっているという、つなぎあっていくという、そこに一切の嫉妬とか、濁りがない関係がそこにあったんですね。「あ、こういうことかな」と思って。それが『ハッシュ!』のベースになったというのがあります。
それでそこでいろんなことをお話して、『ハッシュ!』に反映したことがありますけど、帰ってきて何年かたって「もしかしたら、そうはいってもいろんなことが人間あるから別れているんじゃないかな」と、多分、別れて女の人が一人で子どもを育てているんじゃないかなと思いましたけど、なんというんでしょうね、『ジュラシック・パーク』で、ジェフ・ゴールドブラムの台詞かな。「生物は生き残っていく道を探す」というのがあったんです。まさにそうで、何年かたって「あのオランダの家族はどうしているのかな?」と思って聞いてみたら、3人はまだ一緒に暮らしているんです。二人目の女の子ができた。この女の人も「やっぱり私、一人では寂しいから」というので、女の人の親友、女性の友だちと4人で暮らしながら今度は、前はこの人と子どもをつくったので、この人の精子をもらって二人目の子どもをつくって6人家族で暮らしている。増殖してたんですね。ああ、こんなふうに僕の想像は丸々違って「別れているんじゃないかな」とネガティブに思っていたのが、どんどん生き残っていく道を探していっているという、いろんな価値観かあると思うけど、それを、いい、悪いということは簡単に言えないと思うんですね。その人が、どう生きていくかということ。『ハッシュ!』は、たとえば僕だったら「映画監督です、ゲイです」という「もうこういう生き方しかないんだ」と決めつけるよりも「もしかしたら僕にも子どもをつくる可能性があるかもしれない」といういろんな可能性を残しておく方が生き方として余裕があって楽しく生きられるんじゃないかなと思って。おすぎさんなんかに言わせると「あたしは古いオカマだから」と力を込めておっしゃるんです。「おすぎさん、僕だって、子どもをつくろうと思ってないですけど、人間最初から道を決めるの、つまんないじゃないですか」「あたしは古いオカマだから」と。
特に『ハッシュ!』をつくる前は、21世紀になる間際で、つくってからすぐの世紀が開けて21世紀きになって、カンヌ映画祭にいったんですけど、カンヌ自体が20世紀は戦争の世紀だったけども、21世紀は、ほんとにいい世の中にあるはずだという世界中の人の気持ちがカンヌに溢れていたんですね。で、『ハッシュ!』自体も「人間のいろんな生き方があるじゃないか。一つの生き方を決めつけるのはつまんなくないかな」ということを描いた映画だったので、僕自身もこの先、自分の人生がどんなふうに枝分かれしていくんだろうと、楽しみに希望をもってカンヌで感じてたんですけど。そのすぐ4、5カ月あとにテロがあって、世の中の空気が一変してしまって、切ないのは、あの時のカンヌが、21世紀はほんとにいい世の中になるはずだという、未来に向かって皆が思っていたような気持ちが一変してしまったという、すごく残念なんですけど。今、『ハッシュ!』みたいな映画をつくることも難しいのかなと。今つくったら日本の方たち、受け入れてくれるんだろうかということを、また久しぶりに『ハッシュ!』を見直して思ったりしていますけど。
河口 いろんな可能性を秘めた映画だとおっしゃっていただいて、私もそう思っていて、見た時に家族の中にいると役割を負わなければいけないのではないかというのがすごくあって、私も子どもはそんなに好きじゃないし、持ったとしても、私が親になったら、父親にならないといけないじゃないですか。こう見えても一応、男のカテゴリーに入ると思うので、でもなんか、父親になるというのはできないなと思ったりして。
橋口 なれますよ。
河口 そうですか。母親にはなれるかもしれない。
橋口 なれますよ。目の前に赤ちゃんいてごらんなさい。どっちにだってなれますよ。
河口 両方なってしまえばいい。父親にも母親にもなる。ただ朝子の言葉で楽になれたのは「結婚したり、妻になったり、母になったりしたいわけではない」ということを言うじゃないですか。それがなんか「ああ、こういうあり方もあるんだな」と映画を見て。今まで家族というのは、それぞれの役割があって遂行していかないと家族でないとうい思いがあったんですが、そういうところで自分の意識に変化がもたらされたのかなという印象を持ちます。そのへんはいかがでしょう。
橋口 血のつながりだけが家族と思わないんですね。あまり。だけど映画をごらんになればわかると思いますが、血がつながっているから示せる愛情とか、虫の知らせみたいなこととか、人と人と、ふっと、つながることとか、光石研の演じるお兄さんみたいに、ずっと勝裕が「ああ、僕たちは違うな」と思いながらもずっとそのことを胸に秘めながら見守っていたということはお兄さんにしかできないことだろうとかね。そういうことを全然、否定はしいなんですよ。否定はしないんだけど、果たして血のつながりだけが家族だろうか。自分で選びとっていく家族ということもあってもいいのではないだろうかというのを思ったのが、ずいぶん前なんですけど、ニューヨークにしばらく滞在した時にお世話になっていた方が、日本人のゲイの方ですが、パートナーの方がイタリア系移民のアメリカ人のゲイの人でエイズで亡くなったんですね。僕も存じあげていて。亡くなった直後に僕がお邪魔して、3カ月ほど。その時の体験が大きいと思うんですけど。その日本人の方は日本のすごくお金持ちの息子さんなんです。だけど自分の家族とは全く疎遠なんです。特にお母さんのことをちょっと憎んでいらっしゃる。でも逆にパートナーのことをすごく面倒みてらっしゃって、みとられて、なんだかんだやっていくうちにイタリアの移民の頑固な親父、お父さんですね。敬虔なカソリックで自分の愛する息子がオカマなのが許せない。しかも東洋人とつきあうのが許せない。臨終の席でも自分の息子がエイズになって死ぬということが受け入れられないという頑固な親父の一家なわけです。でもパートナーの方の死を通じて、自分の家族とは疎遠だったにもかかわらず、こっち側の頑固な東洋人嫌いの、ホモ嫌いの、エイズ嫌いのイタリア系移民の家族とほんとの家族になっていった。「人間というのは生きているうちも、死んでからも人との関係をきることができないんだね」と、その方おっしゃっていましたけど。パートナーの方が亡くなったことによって自分は別の家族を手に入れることができたという、血のつながりはもちろん大切なんだけど、果たしてそれだけが家族というんだろうかと。自分で選びとっていく家族もあるんではないかということですね。一つ。それも人の生き方だし、家族の一つのあり方ではないかということをその一端を『ハッシュ!』で描いたということです。
司会 では、フロアの皆さんからご質問かあれば伺いたいと思います。
質問 映画の中で朝子さんが男の子にいいよられたり、関係を持ったりとういシーンがありますが、あれはどのようなメタファなんでしょうか。
橋口 メタファなんて、そんな難しいものではなくて、最初はやりまんだった朝子が、自堕落なセックスをしていた朝子が、時間がたって最後、同じ男の子とあって、男の子は朝子に最初、拒絶されたことによって、気持ちがほんとに好きになっちゃってという、でも、「ごめんね、できないよ」といって大人の態度であしらっていくという、ただそれだけのことなんですけど。深いそんな。朝子、成長したなということですね。
質問 この映画、初めてみてちょっとわからなかったんですけど、冒頭のシーンですが、高橋和也さんが自転車で男性と寝ているところから出勤されたと思うんですが、その時に相手方の、同じベッドで寝ていたパートナーの男性が携帯番号を教えようとしている間に出ていったというシーン。その時の高橋さんの相手方の男性というのは田辺さんだったのか。わからなかったんですが。
橋口 違います。一晩だけのあれで、一発やって、これから、でも僕たちつきあえるのかなと思って高橋和也が「あのさあ、僕のケータイさあ」と。向こうはその気がなくて、ヒッーといった。高橋和也は「ああ、またこんな夜をすごしてしまったな」と思って寂しい気持ちで「まあ、いいや、仕事にいこう」と頑張って仕事にいくという。
質問 一応、そうかなと思ったんですが、何の予備知識もなくこの映画をパッとみたものですから。最初、ゲイの世界の話と、わからなくて見て。
橋口 そんな知識もなく見にきたんですか(笑)。おう。ちょっとショッキングだったでしょう。
質問 いえ、それはなかったんですけども。だんだんとシーンが進むにつれて、そういう世界の話だなということは。
橋口 そもそもなぜ見に来ようとおもったんですか?
質問 この会によく参加させていただいておりまして、学校の卒業生でもありますので。橋口監督の作品はみなみ会館で『ぐるりのこと。』をみさせていただき、大変よかったんです。ということは、そこからのつなぎとして、その後、田辺さんと高橋さんが暮らしてくのは浮気ということではなく、時間的経過があったというふうに解釈したんですけど。
橋口 最初、同じカットで撮っているんですけど、一晩限りでやった男と「ああ、だめだったな」と。次に田辺君演ずる勝裕君とやりましたと。「ああ、また今度も」と、パッと起きてきたら田辺君がいない。「ああまた、同じか、一晩だけか」と思っていたら、お湯が沸いている。あれと思うと田辺君が出てきて「こんどは違うんだ、今までと違うんだ。僕たち関係が続くんだ」と思って高橋和也はホッと笑顔になると。
質問 それで関係が発展していくという。理解できました。
司会 丁寧なご説明をありがとうございます。時間が短くて残念ですが、これで終了させていただきます。橋口監督、河口先生、どうもありがとうございました。
Copyright © 立命館大学 All rights reserved.