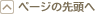中村(産業社会学部・応用人間科学研究科教授)
このシリーズは立命館科学人間研究所が主催で臨床人間科学の構築ということでチームをつくって日頃は研究しているものですが、サイエンスということだけではなく、アートも係留しながらアートとサイエンスの両面から考えていきたいと企画をしました。昨年秋から展開しております。「シネマで学ぶ人間と社会の現在」と題して第一弾として家族の現在をテーマに企画を組んできました。1回目は『誰も知らない』、2回目は『チーズとうじ虫』を子どものことや介護のことを描いたいい作品と思って企画をしました。今年1月は『ディア・ピョンヤン』、異なる視点からの家族の映画で監督もお呼びしましてトークセッションをしました。今回は『蛇イチゴ』『茶の味』と続きます。家族を考える多様な映画はたくさんありますが、いくつかピックアップしてみたいわけです。さらに映画だけではなく、少しばかりレクチャーと称して皆さんと一緒に考える機会を終わりで持っています。研究所に関係する教員がお話をさせていただくことにしでおります。とはいえ大学の講義ではありませんので、こういう見方もあるんだという一つの呼び水の話をしてもらいます。家族の現在ですので、いろんな思い、そんな見方もあるとか「そんなん、ちょっとちゃうで」とか、いろんな見方かあるかなと思います。その呼び水風になればと思って今日は私たちと一緒に研究しております臨床心理が専門ですが、家族のことについても造詣の深い村本邦子先生に呼び水風の議論をしてもらう方として、後でご登壇願います。
私もこの映画を何べんも見て見るたびに最後の15分くらいが、とてもいいなと思っています。皆さん誰に視点をあわせて見ているでしょう、そんなこともぜひ議論したいわけですが、私としては『蛇イチゴ』に一匹蟻ん子が、ひたすらはい回っているのが、とても印象的で、これはなんでなのかなと、いつも考えています。見るたびに違う発見があったりします。なんで『蛇イチゴ』の最後に一匹蟻ん子が這いずり回っているのか、最後に私も議論してみたいなと思っていますが、今日は村本先生に「私はこんなふうにこの映画を見た」という話をしてもらいたいと思います。その後、議論してみたいと思います。質疑応答もしたいと思いますので、いろんな視点からぜひアートな時間をとりたいと思います。村本さん、よろしくお願いいたします。
 村本
こんにちは。ご紹介いただきました立命館の村本です。私は20年くらいカウンセリングをやってきました。家族、女性や子どもの問題にかかわってきまして家族の内情、外から見える家族ではなく、中から見た家族の話を聴かせてもらう、見させてもらう立場にいます。この映画を見まして、結論があるわけではないのですが、家族の成員それぞれの微妙な心の動き、心理描写がほんとに見事にできているなと感心します。この監督は若手の女性ですが、女性ならではの視点かなと思います。この作品を、監督が20代終わりにつくったようですので、一体、この監督はどんな家族背景をもって、この作品をつくったのか、とても興味のあるところです。年齢から言うと、倫子さんと同じくらいの年齢でしょうから、そこから見たのかなと思ったり、この後につくられた「ゆれる」も面白いですけど、男二人兄弟の似たような葛藤というか、気持ちのずれだったり、役割分担だったり、そういうものが描かれています。おそらく、この監督は、家族の中で繰り広げられる表面から見えるものと、それからその下、深部、深いところで蠢いているさまざまな葛藤、隠された闇の部分を感じながら生きてこられたのかなと思ったりします。
村本
こんにちは。ご紹介いただきました立命館の村本です。私は20年くらいカウンセリングをやってきました。家族、女性や子どもの問題にかかわってきまして家族の内情、外から見える家族ではなく、中から見た家族の話を聴かせてもらう、見させてもらう立場にいます。この映画を見まして、結論があるわけではないのですが、家族の成員それぞれの微妙な心の動き、心理描写がほんとに見事にできているなと感心します。この監督は若手の女性ですが、女性ならではの視点かなと思います。この作品を、監督が20代終わりにつくったようですので、一体、この監督はどんな家族背景をもって、この作品をつくったのか、とても興味のあるところです。年齢から言うと、倫子さんと同じくらいの年齢でしょうから、そこから見たのかなと思ったり、この後につくられた「ゆれる」も面白いですけど、男二人兄弟の似たような葛藤というか、気持ちのずれだったり、役割分担だったり、そういうものが描かれています。おそらく、この監督は、家族の中で繰り広げられる表面から見えるものと、それからその下、深部、深いところで蠢いているさまざまな葛藤、隠された闇の部分を感じながら生きてこられたのかなと思ったりします。
今日は呼び水風にということですが、これについて何が言えるということはなく、見れば見るほどいろんな疑問が沸いてきます。資料に、10の疑問をピックアップしてみました。「私も答えを知りません」とお断りしていますように、この疑問について私が答えるわけではなく、どうなのかなと思うことをお話して、皆さんの仮説や考えも聴かせてもらえたらなと思い、資料を準備しました。
疑問その1。明智家というのは平凡な家族なのか、特殊な家族なのか、どっちなんだろう。どう思われます? どうなんでしょうね。一見ありふれた平凡な普通の家庭ですよね。だけどちょっと不思議だなと思う部分がいろいろあるわけです。普通にしては、ちょっと普通を超えているかなと思う部分がある。全く普通でなく特殊な家族とも思いきれない思いながら見ていました。
この明智家の構成メンバー、お父さんは昔気質で真面目に仕事一貫と言われていますけど、ちょっとお茶目なところがあったり、ユーモラスな人でもある。体裁を気にして恰好をつける。チャランポランな長男に愛想を尽かして、10年前に勘当してしまう。長男は多分、大学の途中くらいで勘当され、家を追い出されて一度も帰ってこなかった。これもちょっと極端かなという気がしますね。このお父さん、二面性があるわけですよね。たとえば娘が連れてきた恋人の男性の鎌田さんの前ではとても愛想よく振る舞い、娘の前では好印象の父親として反応しているにもかかわらず、実は内心「あんな奴」と思っているわけですよね。お葬式の後で、お姉さんに「本当にありがとう」と頭を下げる。お姉さんが「皮肉だけは一流だね」という言葉を引き出す、そして見ている私たちもその場面で、お父さんが、相手に対してよい反応をしている時に、ウソをついているという感じは見えない、本当にそんなふうに思っているように見える。でも、その人がいなくなると、奥さんに対してはものすごく悪態をつくわけですよね。こういう二面性がある。面白いのはこの二面性が娘には見えない、少なくとも今まで。修羅場の中では登場するんですが、娘にとって、「根が優しくて正直者で」と信じているお父さんだった。多分、娘の前では、よい人間としてのみ、自分の顔を見せてきた。奥さんに対してはちょっと違うらしい。わりと簡単におなかの中では違うことを考えていると表現しているんですよね。この人が実はリストラで会社をクビになって、それを家族に告げることができず、毎日会社に通っているフリをして借金を重ねて生活していた。そういうことが劇中でわかるわけです。
それからお母さん。良妻賢母のタイプで生きてきた。大変であろう介護に対しても、「嫌な顔一つ見せず、グチ一つこぼさず、この家を守ってきた」という言葉がありますので、今回の大きな出来事が起こるまで、お母さんも、よい人としてのみこの家族の中でいたのだろうと思います。お父さんみたいに陰口を子どもに聞かせるとか、どこかで悪態をつくとか、そういうことはしないでここまできたんだろうと思います。
主人公、一見健気で、精一杯両親を気づかって家族を支えてきた娘。小学校の先生で、同僚の鎌田さんとおついあいしている関係です。それからおじいちゃん。とても存在感のあるおじいちゃんですが、戦争に行った世代で、トラックに乗って、この家を築きあげてきた存在です。どうやら認知症になってしまって、食べることに執着している様子です。戦時中のひもじさが強烈に焼きついているのかもしれません。後でお葬式の場面で出てきますが、娘とは折り合いが悪く、嫁であるお母さんのことがとても気に入っていた。このおじいちゃんは途中で亡くなる。
お兄ちゃん、周治さん。この人は、大学に行っているフリをして、学費をネコババしていた。中学生の妹の下着を売って儲けていたという話が出てきます。お父さんと折り合いが悪く、勘当されて、どうやら明智家では追い出された10年間、存在を抹消されていたのかな、いないことにされていたのかと思います。
はじめに出てくる場面は、明智家の朝食の食卓の場面です。この食卓を見て皆さんはどんなことを感じられたでしょうか。ほほえましい、よくありがちな、あったかい家族の朝と思われたでしょうか。私自身は、「アレッ」っと思うことがいろいろあるんですね。おじいちゃん、お父さんの父親ですが、べちゃべちゃ食べこぼしてテーブルを汚している。お父さんは、「オイ」と妻を呼んで自分は新聞を読んでいるわけですよね。「自分で何とかしろよ」と突っ込みたくなる。とても違和感があるのは、お母さんが、娘に、「ジャージ持った?」と聞くんですね。社会人になって、学校の先生になっている娘に。「ジャージ持った?」と聞いて、それに対して娘も腹を立たないというのが私にはとても不思議です。思春期でも、うっとうしいなと思うんじゃないかなと思うんですが、むしろ、それにある意味、頼っていますよね。一見しっかりした娘なんですが、実は今日、水曜日で朝礼があることも忘れていて、曜日を勘違いして、ジャージを忘れていた。お母さんが準備してくれた朝御飯を一口だけ手をつけて、慌てて行ってしまう。それから、すごく不思議なのは、どうしてこのお父さんと娘は一緒に出勤するのかなというのがありますね。毎朝、一緒に出勤しているのかなと。慌ててお弁当を忘れていきますが、倫子が「もう行くわよ」というので、「ハイハイ」と慌てて一緒に家を出る。お父さんと娘は仲良く毎朝、途中まで一緒に通勤する。これもおかしいですよね。父と娘が一緒に出勤するのが悪いとは言いませんが、なんかへんだなと私は思います。食卓というのはある意味、その家族を表す象徴的な風景、その中で一見、普通に見える、そしてありがち、とも言えるかもしれないけれども、何かおかしいなと思うようなことが散らばっているんですね。
答えは知りませんので「明智家はありふれた家です」と言うこともできるし「特別です」というつもりもないんですね。どうなのかな、どうなのかなというところが私の関心です。
疑問その2。この映画はウソというのを中心のテーマとしておいているかなと思うんですが、この映画の中で一番のウソつきは一体誰なんだろう?というのが私の次の疑問です。皆さんはどう思われますか?誰が一番ウソつきなんだろう、この家族の中で。皆、多かれ少なかれ、ウソをついてるんですね。お父さんのウソは、クビになったことを家族に言うことができず、ウソを重ねてきた。娘の婚約者や自分のお姉さんの前では、平気で心にない社交辞令を言う。これもある意味、ウソですよね。ホンネを隠して体裁を繕う、その場に適応的な振る舞いをするというのは、ある意味ウソなんですけど、ただこのお父さんはすぐ次の瞬間に全く相反することを吐き出すわけです。場面が変われば。そういう意味ではウソの振る舞いをしているけれども、その気持ち、ここでウソ以外の自分のほんとの気持ちが常にそこにあるわけですよね。
そうであるにもかかわらず、このお父さんは、ほんとにウソつきで自己欺瞞で体裁ばかり取り繕う権威的な、男らしい男としているかというと、案外そうではなく、お茶目というか、駄洒落を飛ばすような憎めないところもある。徹底的に男らしさの権化を生きているお父さんだと、いろんな歪みが生ずるけど、このお父さんは抜けるところもある。それは健康的だなと思うんですが、娘に対してだけはウソをつき続けているんですね。娘の前では娘の信じる、よいお父さんという顔だけを見せています。
お母さんのウソ。このお母さん、おじいちゃんの世話をして見ているだけでも大変です。画面で見ていても大変だと思いますが、お母さんはこれまでグチ一つこぼさず、おじいさんを献身的に世話してきた。円形脱毛ができていましたよね。家族は誰も知らないでしょうけど。ここにお母さんのウソがあると思うんですね。お母さんのウソというのは、私が思うに、お父さんのウソよりも深刻なんですよね。ある意味で、自分に対するウソなんですね。自分がこの家族の中で大変だとか、しんどいということをこれまで一切表さずに良妻賢母として生きてきたと思います。その結果が脱毛症ですよね。臨床の現場でもたまに見ます。子どもの脱毛もありますが、お母さんの円形脱毛があるケースで、どこにも逃げ場がない、徹底的にいい人をやっている人の中に見られます。これはある意味、自己欺瞞ですよね。特に女性というあり方に含まれる可能性のある自己欺瞞を感じます。
いちばん気になるお母さんのウソというのは、おじいちゃんが亡くなることにお母さんは加担していますよね。積極的加担ではないですけど、お風呂場でおじいちゃんが何回か発作を起こす状況になっていて、お風呂を洗っている時、鏡で自分の頭を映し出して見ています。そこでおじいちゃんの発作を起こしている声が聞こえる。そういう場面があります。それに対してシャワーを大きく出して聞こえないようにして、ゴシゴシと掃除を続ける。その結果、おじいちゃんは亡くなっていますよね。義父、おじいちゃんの死への加担、責任というのは言い過ぎかしれまんが、無関係ではない。そしてそのことは誰も知らない。こういう状況の中で、おじちゃんが死んでくれたらどんなに楽だろうという気持ちが浮かぶのは、とてもありふれたことだと思うんですね。でも実際にその場面で知らん顔をして、積極的に死に加担するというのは、少し度が超えているかなと思うんですね。映画でとても不思議なのは、お母さんがこのことで自分を責める、誰にも内緒にしていたとしても、自分自身が自分を責めることをにおわせる場面はないんですね。このお母さんのウソはとても深刻ではないかと言いましたが、そういう意味では、ひょっとするとお母さんは自分がおじいちゃんの死に加担、責任がないわけではないということを、自分に対しても否定、心理学では否認という言葉を使うんですが、それはわかっていてウソをつくのではなく、防衛機制として自分で自分を守るために自分の意識に上らないように閉じ込めてしまう。ひょっとすると、そういうウソがあるのかなということを感じます。
それから倫子さんのウソ、婚約者、パートナーに、結婚を前提におつきあいをしている相手にお兄さんの存在を隠していたというウソ。この映画で扱われている修羅場の中で、いくらかホンネが見えるんですが、「お母さんの相手をするのは1日でうんざり」というお兄ちゃんに対して「私なんて毎日よ」。表面的にはお母さんと仲良くしているように見えて、実は毎日、うんざりしているという気持ちがホントはあったんだろう。「ずるい」と言いますよね、お兄ちゃんに対して。そうであるにもかかわらず、親に対して直接、非難とか怒りを向けることはない。よい娘として振る舞っている。倫子さんというのは、この家族の中で懸命に生きようと、健気に努力して生きてきた人だと思うんですが、実はいろんなウソがある。これはお母さんと合い通じる、女性であることと関係するウソかもしれないなと思います。
兄、周治君のウソというのは全部ウソなので、何がウソで何がほんとかわからない。ある意味でウソをついている感じもしない、すべてがウソで、刹那的で、その場そのぎという話かなと思います。これを演じている宮迫さんが「最初は感情の見えない、お兄さんをどう演じようかと悩んだけど、自分をやればいいんだとわかった。実は、自分はいろんな人格かあって、多重人格なんですよ、その場その場でウソでホントでもなくて、普通に自分をやったらいいんですよ」と言っているところがあって、映画ではないですが、それはなるほどなと思います。その場その場で適応的に振る舞っていく、ホントがなければウソはないわけで、周治君にとっては、ホントというのが存在していないのかなと思います。時々、こういうあり方をしている人と出会うことはあります。
この家族を平凡な家族か、特殊かと言いましたが、婚約者の側から見ると、客観的な視点から、鎌田さんは底の浅いたいしたことのない男という感じもしますけど、彼が、「倫子さんのことを恐くなってきた」と言う。お兄さんの存在が見えてから、逆に納得だなというわけですよね。「あの安らぎみたいなものは全部ウソだったんでしょ」と言うわけです。客観的に見たら無理もないなと、おつきあいして家族に紹介するような関係にありながら、こんな大きなウソが見えてしまえばと思う一方、だからといって、その安らぎが全部ウソだと言い切れるのかなというのは、私の疑問です。
疑問その3。増田君は嘘つきだったのか。これははじめの部分で、学校の場面で金魚の世話をしない男の子、増田くんという子がいて、お母さんが病気だと何回も言ってサボッている。倫子さんは「ウソは絶対にいけません」と思っていますので、増田君に対して、「ウソをついてはいけません」とは言わずに、でもそれはウソであることを前提にお説教します。それに対して、一緒に近所の世話を組んでいる女の子は「先生、ほんとに増田君のお母さんは病気じゃないでしょうか」という問いが投げかけられる。その場面だけ切り取られていますよね。結局、誰にも答えがわからない。私自身が子どもや学校場面での子どもにかかわる中で、あの話を聞いたら、それは子どものウソであるといって裁くことだけでは済まないものがあるだろうなと批判的に見ます。その対応は、倫子さんの生き方そのものとかかわっているのだろうと思います。ほんとにお母さんが病気かどうかはわかりません。たとえばお母さんがメンタルな問題を抱えていて、子どもが苦労しているケースもありますし、もしウソだとしたら、どうしてそんなウソをつく状況なのかということを知りたいと思う。そこから何かが見えてくることがあると思うんですけど、倫子さんは、そこを切ってしまうわけですね。この家族がお兄ちゃんに対して扱ってきた扱い方と同じです。
疑問その4。カリフラワーズの音楽が出てきますが、最初のオープニングのところで「まごころの手料理」という歌ですが、これは何なのかなと私は興味深く思いました。この映画には、食べ物が出てくるんですよね。それも、かなりエロチックなあり方で、食べ物が扱われている。「まごころの手料理」というのは、すごーく怖い言葉だなと思います。そしてこの映画が持っている怖さを、オープニングに使われている「まごころの手料理」が表わしているような気がする。カリフラワーズの音楽は周治君のテーマミュージックにもなっているみたいですけど、その場、その場の軽快さですよね。「まごころと手料理」というのは二重にうんざりという感じですよね。「まごころ」ひとつだったらいいんですけど、「手料理」ひとつだったらいいんですけど、「まごころの手料理」というと、急に押しつけがましい善意を感じさせられる。「まごころの手料理」というのは怖いなという感じがします。
女性役割、女性に期待されている役割について考えられるかと思いますが、よく紹介するんですが、女性学者の内藤和美さんがケア役割、人の世話をする、子育て、介護、家事をする。人の世話をする役割は専業でやってはいけないと。どうしてかというと、ケア役割は人のニーズ、相手の必要性に自分のエネルギーを使うことである。本来これは尊い人間の機能ですが、人のニーズのために自分のエネルギーを使うことは結果を評価するのは相手次第、頑張れば頑張るほど成果が現れるというわけじゃない。そうするとどうなるか。自分が自分の人生、専業でケアだけをやっている場合、兼業で違う世界を持っていると、そっちはそっちで、こっちはこっち、自分を尊重し、他者を尊重しということができるんですけど、自分の世界を持っていないて専業でケア役割をしていくと、人間ですから自己阻害に陥っていく。結果としては支配なんですね。子どものためと言いながら自分の人生、自分の願望、欲求を子どもに押しつけていくというあり方に結びついていく。専業で人のケアをする恐ろしさ、支配、自己阻害を生み、人を支配するということにつながっている。こういう臨床の場面での事例をたくさん見ます。「真心の手料理」という二つ思いのこもった言葉というのは、女性の自己阻害と支配とつながるかなと思います。でもこの歌は男性が女性の恋人を部屋に招いて真心の手料理をつくろうという歌ですが、ここで思うのは私自身が母が息子を支配し、増子がパートナーを支配していく、連鎖しいくことを思いながら見ました。
お母さんは自分自身の主体的な人生を持たずに生きてきたわけですよね。この事件、出来事があって、お父さんがクビになって借金まみれだったことが発覚して初めて、なじられる、なじることができる。「こんな家ばっかり」ということを言うわけですよね。「こんな家ばっかみたい」と言いながら、この家をつくってきた自分が一人の重要な人物であるという自覚はない。良妻賢母は恐ろしいと思っていますが、受動的なわけです。自分で人生を楽しくすることができない。「お兄ちゃんがいてくれたら少しは面白かったのに」。そういう生き方を残念ながらずっとしてきたわけですよね。
その幻想、思いに応える形でお父さんはウソをつき続けることが起こっています。そこは共謀関係ですよね、母と父と娘が共謀関係で家族というものを演じ続けている。そして相手の期待を感じて、その期待に応えるために自分が振る舞い、それに騙されたフリをして回ってくというような気がします。
私は心理学が専門ですので興味深いのは周治君と倫子さんがどんな子ども時代を過ごしたのかにとても関心があります。なぜこんな事態にこの家族がなったのか。どうやら上の世代でも同じことが起こっている。おじいちゃんは戦争から帰ってきてトラックに乗って0から家を築くために一生懸命働いていた。娘と息子がいたんだけど、もしかすると時代的なことがあって、息子だけを猫可愛がり、長男ですから、差別があったのかもしれない。姉の方はできの悪い子で家からほおり出され、長男が立派な人として成人して会社に勤めて家族を持つ。おじいちゃんは長男の嫁がお気に入り。ある意味で彼女が意図してというよりは良妻賢母に背中合わせにある欺瞞を愛する、信頼するというおじいちゃんだから、おじいちゃんも嫌なものは排除する、自分の都合のいいものを拾うという生き方をしてきた。それが受け継がれているのかなと思います。この両親のもとで周治君は小さい時から「だめな子」、倫子さんの方は「いい子」として役割分担がなされ、レッテルを張られてその役割を生きてきて、そして今も生き続けているように思います。これも臨床の例ではたくさんあります。心理学的には「スプリッティング」と言われたり、ユング派の言葉では「シャドー」と言われますが、皆、いい人の家族の中では一人が黒い存在にならざるをえない。人間はよい面も悪い面も皆、一人ひとり持っている。でも自分自身は悪い面を生きずに切り捨てて生きていると家族の誰かがそれを背負って生きる。そういう理論があるんですが、まさにそういう例ですよね。そういう役割分担の中で生きてきた、育ってきた二人なんだろうなと思います。そこで大きな間違いは、お兄ちゃんを切って、その存在を抹消したところから、この家族が一見平凡でありながら、ちょっとこういう状況に落ちていくような10年間になったのかな。周治君が中高生時代、いろんな問題が起こったと思うんです。それに両親は右往左往しながら家族のアンバランスを修正していくというプロセスを普段、私たちはよく経験するんですが、それをしきれずに家族の影の部分を引き受けている周治君を切って、ないものにしてしまったというところに無理があったかなという気はします。
疑問その6。蛇イチゴとカッコー。蛇イチゴは私も子ども時代のことを思い出して、蛇イチゴもカッコーも騙しの象徴だったと思います。蛇イチゴを見つけたらすごくうれしいんですよ。とっても魅力的なものを見つけた。おいしいだろうと思って食べるですが、全然おいしくない。蛇イチゴを見つけたワクワクする感じと失望を思いますし、カッコウは恐ろしい鳥ですよね。美しい声で歌う鳥ですが、でも実はカッコーは人の巣に自分の卵を産みつけてカッコーの雛は早めに孵るからその巣の持ち主は卵を全部落として親鳥に育てさせる。他人の家族を騙してきれいな声が歌う鳥です。蛇イチゴとカッコー組み合わせ、カッコーがお兄ちゃんと倫子さんをつないでいますよね。カッコーの歌と口笛がね。これがこの映画を象徴している形で取り入れられているかなと。蛇イチゴの存在はこの二人を引き離した。最後に倫子さんは溝なのか小川なのか岩場を飛べなかった。周治君と倫子さんは出会えないでエンディングになるわけです。
疑問その7。倫子と鎌田はセックスをしていたか。この家族の二人の写し方はひと昔前の、あまりセクシャルな関係をにおわせないようなかかわりになっています。ほんとにどのくらい深いつきあいがあったのか、とても疑問です。後半部分でも「僕たらの関係、誰も知らなかったよね」、誰も知らないようにふるまってつきあっている二人のつきあい方、これもぎこちなさ、違和感を感じます。明智家の性がどうだったのかを考えると、臨床で出会う問題を抱えた家族の中には、性的な関係が家族の中に流れていない家、冷たい人間関係を見ることがあるんですが、それはないんですよね。お父さんがお風呂で丸まった背中のお尻が写っている場面がありますが、憎悪みたいなのは感じない。ふれあい、あたたかさは感じる。ただ世代境界がごっちゃになっていることを感じます。お父さんが娘が可愛くて自分の思いどおりにしていくことと、お母さんが息子に甘えますよね。ちょっとセクシャルな関係で甘える。性的虐待までは思いませんけれども、世代境界を超えた性、お兄ちゃんが「おなかを触ってくれ」と妹に言ったり、大学の学費をネコババというのはそこまで思わないですが、中学生の妹の下着を売るということは妹の性を売るということですから、これはちょっと深刻かなと思うんです。妹に対する思い、家族での扱われ方の違いと同時に性的境界線の混乱があるのかな。そのことが妹にとってはものすごいショック、傷つきの体験なんだろうと思います。お兄ちゃんを信じていったのに蛇イチゴがなかった、騙されたということと、お兄ちゃんが自分の下着を売っていたことはとても大きな傷つきの体験で、そこからますます頑に倫子さんは「お兄ちゃんみたいに生きるまい、自分は誰も騙さない」なんて言って生きる生き方を選ぶことになったのかなと思います。
疑問その8。ウソをついてはいけないのか。これについて他の映画をいろいろ思いだしました。『蛇イチゴ』というタイトルから先に思いつくのは『野いちご』ですよね。ベルイマン監督の『野いちご』は男性の老人が主人公で長く仕事ばかりしていて、孤独と自己欺瞞がテーマだと思うんですが、自分の恋人を弟に寝とられ、自分の妻も浮気をしていることを知りながら感情一つ表さない。そういうあり方をしているからこそ、そういう結果になったとも言えると思うんですが、そうやって生きてきた人が最後、人生の終わりの部分でもう一度人生を振り返って少し変わっていて、野いちごが、主人公が取り戻したいきいきしたし感じ、ある意味のハッピーエンド、野いちごという甘い思い出として再構成される、ある1日を境に。この『蛇イチゴ』は毒を含んでいますよね。蛇イチゴは、毒はないんですけど、毒を含んだような言葉ですよね。
ウソを扱った映画として『グッバイ・レーニン』が好きで、東ドイツと西ドイツが統合する時に東ドイツのことを信奉しているお母さんが病気かなんかで意識がなくて、気がついてみると統一されていた。そのお母さんのショックを避けるために息子がニュースから何から変えて、とてもコミカルな面白い映画ですが、そういう話ですが。母を守るために息子はばかげたウソをつく。最後はわかるんですが、それを見ていると笑えるし。限界があって事実は発覚する。あの映画でもう一つ根底に流れているのが家族のウソで、お母さんは子どもたちに対して「自分の夫は自分を捨てて出ていって振り向きもしなかった」とウソをつき続けているんですね、実は。こんなウソはついちゃいけないウソだと思うんですね。
それ以外に思い出すのは『ライフ・イズ・ビューティフル』とか『ビッグフィッシュ』とか思うことはありますが、ウソをついたらいけないのかというのは一つ問い掛けておきたいと思います。
疑問9。 蛇イチゴの木はほんとにあったのか。答えはわからないです。最後の場面で蛇イチゴは結局あるんですよね、テーブルの上に。ほんとにあったのか、ピカピカ光って写っているじゃないですか。カーテンで光と影が入ってきているから、あんなふうに写っているのがわからないんですが、はっきりしているのはお兄ちゃんが家に帰ってきた。お兄ちゃんの口笛が聞こえてハンガーがゆらゆらしている。お兄ちゃんの上着がかかっていた跡がある。お兄ちゃんが家に帰って出ていったことはわかるんですが、ほんとに蛇イチゴがあったのかどうか。あれは私の中では「ほんとにあった」とまで言い切れないんですよね、「?」マークなんです。そもそも蛇イチゴの木がへんなんです。蛇イチゴって木って感じでもないなと。蛇イチゴを食べたらおいしかったということですけど、おいしくないです。でも野いちごの中には蛇イチゴのように生えておいしいものもあるので、あれがほんとだったとすると蛇イチゴではなかった、別なものだったのかもしれない。でもあれはもしかしたら倫子さんの幻覚かもしれないとまで思います。
皆さんも気になると思いますが、明智家のこれからですよね。どうなるのか。お兄ちゃんは逃げおおせるのか、逮捕されるのか。この家族は借金をどうカタをつけるのか。私もわかりませんが、ただはっきり言えることは、お兄ちゃんが現れず、このことが発覚していたら、この一家は下手すると一家心中していたと思うんです。お兄ちゃんが現れた、お兄ちゃんの存在によって家族がホンネをぶつけあう、醜く罵り合うことが始まる。そうすると新しく家族が再構成される余地が出てくる。そんなふうにこのチャンスをこの家族が乗り越えることかできたら、この家族はかなり大きな逸脱はあったけれども、まあ、ありがちな、ちょっと失敗は大きかったけど、10年間、子どもの存在を抹殺していた、それはちょっと極端だったけど、ありがちな一つの家族の形だと言えるかなと思います。何とか乗り越えていってほしいなと思いますが、倫子さんのこれからは、これまでの生き方をもう一度再構成していくプロセスというのは並大抵じゃないなということを一方で思います。
ここまでにしたいと思います。質疑応答というより、今、私が提示したことに対して自分の解釈はこうだということを聞かせてもらえたらうれしいと思います。
中村 いろいろ実にいろんな視点から解釈していただいて私も気づかなかったり、なるほどなという思う点がたくさんありました。私自身は社会病理学を専門にしているので、兄の視点に。私自身はモノレールと蟻ん子に、この映画に関心を持っています。空中に浮かんだ家族のような感じもするし、蟻ん子は最後、よく監督があれを演出したなと思うくらい蟻ん子を見つけてきたんですね。アリとキリギリスのエピソードを思いだしながら見ていました。この映画にとてもハッピーエンドを見たんです。とてもうれしくなったんです。このハッピーエンド感ってなんでしょうね。村本さん、どう思いました?
村本 ハッピーエンドではないですけれども、お兄ちゃんが帰ってきて、この事件が起こるよりも、よっぽどよかったなと思います。
中村 なんでハッピーエンドを感じたかという、この家族、親父さんは「壊れかかっている」と言いながら最後の出来事を通して力を持つ。本来持っていのが見えてきたのかもしれませんし。いろんなことがわき出てきたなという意味で、課題はあるけど、この家族、生きていくなという思いがして、通例、言われるハッピーエンドではないんだけど、直面していく課題が見えてきて、それぞれの人生を歩んでいくなという感じがして、とてもうれしくハッピーエンドを感じたんです。ある種、力をもらったような映画だったと思います。皆さん、どうでした。どんなふうに見ました?
望月(文学部・応用人間科学研究科教授)
僕は年代のせいか、お父さんの目線で見ていました。
中村 なんかウソをついているんですかね。
望月 そう。ウソをテーマで家族に絡めていく。倫子さんは正直者だけど、妹ね。一応、そこまで深読みしなくても一応ウソはつかずにきた。あれはジャージさえ持っていけるかどうかわからない人で貢献していないんですよ、家族に。貢献とウソというのは比例して、親父から言うと、ああいう崩壊を招いたけど、一生懸命ウソをついてお金を入れてきたわけだよね、家族に。最後はとんでもないことになっちゃうけど、ウソと家族への貢献は比例しているんだなと思ってね。ハッピーエンドかと言えば、誰が力をもらったか。これから倫子はウソつきになってくる。そういう意味で親の目線から見ると彼女が本物になっていくのではないか、これから。社会に貢献もできるんじゃないかという意味で、そう感じました。
中村 触発されることがありませんか。村本先生の問題提起についても。考えさせてくれる映画っていいですよね。
村本 私はこの倫子さんを見ていて、うちの大学にもたくさんいそうな女の子だなと思ったんです。それは悲しいなと思いますが、望月先生は家族が成り立つ上でウソを肯定されたと思いますが、私がいつも思うのは親の願望に応えて自分を生きない、とってもいい人で、親のよい子で、でも自分を生きないというのを、すごく感じるんです。特に立命館なんか。今日、午前中、娘の高校の卒業式で卒業生代表の人が感謝の言葉を述べる。お父さん、お母さんにも。感謝はいいと思いますが、その後、「これからはお父さん、お母さんに親孝行します」と言ったんですよ。そんな若いうちから親孝行せんでいいと思うんですよ。まだこれから自分の人生を立てるためにたくさんエネルギーも時間もいるのに、親孝行なんかしている暇はないんです。そんなふうに生きさせてしまう現代、少子化ということもあるし、社会階層の問題もあると思いますが、倫子さんを見ながら、今、大学の若い人たちに親の期待なんか、親の願望なんか、自分にウソをついて支えて、いいことなんか一つもない。小さい時は仕方がないですけど、後は家族のウソの共犯者になるだけだと思うんですね。良妻賢母、よい娘は脱ぎ捨てて、もっと自由に生きたらいいのになというのを私は伝えたかったんです。
中村 仮説でウソという言葉で説明しましたけど、いろんな言葉が可能なのかなと思います。『グッバイ・レーニン』の話も出ましたし、他にも映画の引用を出しながらウソという言葉を置いたけど、いろんな言葉が置き換え可能な言葉かなと思いました。ウソというと衝撃的な言い方ですが、人が納得して生きていくためには何かこういう機能が必要なのかなと感じたり、それをウソと言うと、ちょっと言葉が違うなという出来事があったりするかなと思って。家族のリアリティは臨床のケースとか人間科学的アプローチで説明可能ですが、映画で見せつけられると一瞬で何かを描いてしまったり、一瞬でわかってしまったり、映画って、ずるいですよね。ほんとに映画はずるいと思います。とてもいい媒体だなと思います。アートとサイエンスの両輪、二つはこんがらがってメビウスの輪になって転がっていくのかなと思っていまして、ぜひ引き続き、こういう媒体、チャンス、場所を一緒に共有しながら、それぞれ生きていける社会になっていけば、その縁になればと思っているところです。
次回は『茶の味』という奇妙な家族が登場しますので、ぜひまたお越しください。こんな形で「家族の現在」と称して今日、4回目を持つことができてよかったなと思います。村本さん、どうもありがとうございました。皆さんもどうもお越しいただき、ありがとうございます。皆さん、これからウソをついて生きていきましょう。頑張りましょうね。今日もウソをつきましょう。ここでは京都シネマでもかからないような映画をかけていこうと思っています。仕事と称して映画を見ています。学生たちがインディペンダントな映画を上映したいということで一言アピールを。
辻 立命館大学4回生です。3月〜4月にかけて大阪のプラネット+1、シネヌーヴォXでこの10年間関西を中心に撮られてきた自主映画を180本以上上映するという企画です。なぜこの企画を皆さんにお伝えするか。自主映画をつくって上映する、皆さんと近いところで語ることをするためにいろいろと宣伝活動をしています。そのための企画として監督とのトークショーを4月3日最終日、4月2日までの見ていただいた方の投票を得てプログラムを決める企画もしています。ぜひよろしくお願いします。
中村 この後は茶話会で。また来月よろしくお願いします。
司会 以上をもちまして公開講座「シネマで学ぶ人間と社会の現在」を終演とさせていただきます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。