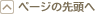今回のタイトルである「チーズとうじ虫」というタイトル、それだけ聞くといかにも地味ですよね。「チーズとうじ虫」というのは、カルロ・ギンスブルグという人が同名の本を書いているんですね。イタリアの方ですけど、この方は数年前、立命館大学にも講演して、かなり有名な方で知っている人は知っている。
デモテープをせっかく加藤治代監督から直々に送っていただいていたのですが、なんか「チーズとうじ虫」、「チーズとうじ虫」と呪文のように唱えるばかりで、なかなか視られないでいたら、それを聞きつけた研究部長の渡辺公三先生が、じゃ、これを読みなさいと本棚から、この本を渡してくれたんですね。それで初めてそういう本がもとにあると知ったわけです。
そこでまずギンスグルブの『チーズとうじ虫』を読んで、これだけでまずは話を考えられないかなと思って一昨日まで来たんです。そして、初めてやっとのこと夜更けにビデオを見たんです。
なるほど、これはこういう映画なのか。レジュメの最初にギンスブルグの言葉を書きましたが、それが冒頭、映画にも出てきました。
「私が考え、信じているものは、すべてはカオスである。すなわち土、空気、水、火など、これらの全体はカオスである。この全体は次第に固まりになっていった。ちょうど牛乳の中からチーズの固まりができ、そこからうじ虫が現れるように、このうじ虫のように出現してくるものが天使たちなのだ」。
これが今日の映画の冒頭にも出されましたよね。
もともとギンスブルグの『チーズとうじ虫』というのは、実際あった話なんですね。ギンスブルグというのは中世の異端審問、魔女狩りとかの古文書を読み解いて当時の文化や知のありようを深く観察した歴史学者、歴史家という方なんですが、この本は、異端審問にかけられたスカンデッラさんという16世紀に粉挽屋さんの話です。いつも真っ白い恰好をして粉を挽いている。
 そして、今、申し上げた言葉に表せるような、粉を挽きながら、この人は粉挽小屋から、そういう極めて大きな宇宙観、コスモロジーをつくっちゃったわけですね。当時は当然ながら神様がこの世界を造ったとなっているわけで、無から神様が人も空気も水もお造りになられたという中で、極めてラジカルな唯物論をかましちゃったわけですね。チーズから出てくるのは天使なんだ、チーズから生まれてくるようなものだ。混沌からカオスから固まりになっていく、牛乳を醸してチーズができ、そこから天使が出てくる。実際にチーズからうじ虫が出てきたら大問題なんですけど、これは言わんとするところは「あたりまえに出てくるもの」ということなんですね、「チーズとうじ虫」というのは。チーズというのはイタリヤの方では、日本でいえば味噌をつくるとか醤油をつくるというレベルの、ごく家庭の一般的な作業なんですね。これは、今回の映画の中で現代の日本の日常生活に出てきましたよね。オガ屑かなんか入れてゴミを処理していくあれです。あれと同じようにどこの家でもチーズをつくる。牛乳を発酵させて、水を抜いて豆腐をつくるような感じでそういう形でチーズができていく。ちょっと油断すれば、すぐうじ虫が出てきちゃう。うじ虫が出てくることなんてことは、ごくあたりまえの、ごく自然なことという意味なんですね、「チーズとうじ虫」というのは。逆に何ら神秘的なところもない、ごくあたりまえのことだというニュアンフが含まれた見方なんですね。
そして、今、申し上げた言葉に表せるような、粉を挽きながら、この人は粉挽小屋から、そういう極めて大きな宇宙観、コスモロジーをつくっちゃったわけですね。当時は当然ながら神様がこの世界を造ったとなっているわけで、無から神様が人も空気も水もお造りになられたという中で、極めてラジカルな唯物論をかましちゃったわけですね。チーズから出てくるのは天使なんだ、チーズから生まれてくるようなものだ。混沌からカオスから固まりになっていく、牛乳を醸してチーズができ、そこから天使が出てくる。実際にチーズからうじ虫が出てきたら大問題なんですけど、これは言わんとするところは「あたりまえに出てくるもの」ということなんですね、「チーズとうじ虫」というのは。チーズというのはイタリヤの方では、日本でいえば味噌をつくるとか醤油をつくるというレベルの、ごく家庭の一般的な作業なんですね。これは、今回の映画の中で現代の日本の日常生活に出てきましたよね。オガ屑かなんか入れてゴミを処理していくあれです。あれと同じようにどこの家でもチーズをつくる。牛乳を発酵させて、水を抜いて豆腐をつくるような感じでそういう形でチーズができていく。ちょっと油断すれば、すぐうじ虫が出てきちゃう。うじ虫が出てくることなんてことは、ごくあたりまえの、ごく自然なことという意味なんですね、「チーズとうじ虫」というのは。逆に何ら神秘的なところもない、ごくあたりまえのことだというニュアンフが含まれた見方なんですね。
ギンスブルグが、どう考えてきたか。すごくあたりまえ、今の考え方からすると、あたりまえというか、かなりラジカルに「唯物的なところから天使も出てきているのさ」という言い方はね、ほんとに当時としては、とんでもない話なんで、それこそ今、我々の冷蔵庫の中からうじ虫が出てくるより大騒ぎになったわけですね。本の中のメノッキオさんというのは、ずっとその論陣を張っていて、しかも歴史家の中からいろんな評価があるんだけど、なんでこんなすごいことを当時、考えられたのかというくらい、逆にあまりにナチュラル、あまりに即物的な新しい宇宙観だったわけですね。挙げ句の果て、メヌッキオさんは異端審問の審判にかけられて火あぶりになっちゃう。そういう話をギンスブルグは古文書から見つけてきて、ずっと過程を追って、なぜそんなふうに、そんなラジカルなことを、あの時代にその人が考えられたのか。そういうことを社会が生み出していけたのかということの歴史を書いたわけですね。
加藤治代監督が「チーズとうじ虫」というタイトルをつけたのが、いつなのか。編集する過程でできたのか、頭からそう考えていたとは思えないんだけど、どこかの時点でこのことを考えたことはどういうことなのか。
今、ごらんになったように、ほんとにホームビデオみたいな、まさにドキュメンタリーなんだけど、この母親の病気、がんになったということがわかって、監督の加藤治代さんは劇団にいたんですね。それで帰ってくる、お母さんが病気だということで。その時点ではお母さんは自分が、がんだということは知らない。それでずっと撮っていって、あるところでお母さんに「実はがんだったんだよ」という話を本人にも知らせる。「その時、どんな気持ちだった?」「あ、やっぱりね」という、そんなところから始まって、最後、亡くなって、そして亡くなったお母さんを思う、またおばあちゃんがいますよね。おばあちゃんが、また繰り返し、お母さんのことを考えながら、そこで淡々とまた語りあうという流れですね。言うまでもなく、お母さんが中心の映画ではあるわけですね。
ただまあ、言葉の端々に、確かに、お母さんも、おばあちゃんも、ただ者じゃないという感じがありますよね。「私の方がいい女だね」とかボロッと出てくる言葉とかね。お母さん、なかなかちょっと「人物」な感じがしますよね。絵を描かれる、学校の先生だった。退職教員の絵画展に出す、病気になってから。あれは退職されてから描き始めた絵らしい。実はそのへんは朝、ネットでちらっと見ましたけど。ただ者じゃないというのは、死に対する受け入れ方とか、そこに出てくる言葉の端々が、とてもジタバタもせず、涙も一つも出てこない。非常に淡々とこれを受け入れているし、極めつけは、ちゃっかり、がん保険に入っていて、がんになったらお金が出る。僕もあれから気になって、がん保険に入っているかどうか、アフラックで100万円くらい出るそうだと。それはともかく、お母さんはちゃっかり車を買うわけですね。欲しかった耕運機と三味線も、お母さんがそういうことになったら最後に楽しもうと思って買っちゃう。そういう意味では、単に精神的に淡々としているというふうではなく、実に着々としているというか、段取りがきちんとできている、そういう強い逞しさを感じることができる。
そういうことを話していけばいくほど、最初、ただ者ではない、お母さんと、おばあさんの家ではあるけれど、淡々と、淡々と、実に事実を語っていて、特に立派な人というわけではなく、ちゃっかりして、かつ笑いもユーモアもあるという形で時間が流れていくだけなんだけど、こんなふうに、じっくりと時間軸に沿った映像を見せられると、そこに確かに何か、最初はただ者ではないという話だったけど「ああ、ここからほんとに天使だって現れるだろうな」という感じがしますよね。
極めつけは見る人によっていろいろ違うと思うんだけど、皆さん、どのシーンに一番思い入れがあるか。どうでしょうかね。札束を積まれたところにインパクトを感じるという人もいると思うし、もちろん画面が反転してお母さんが亡くなって白い布を被っていきなり出てくる、あそこにもアッというインパクトを感じたかもしれないけど。でも、半分くらいの人は僕と同じ考えかと思うんだけど、病があり、死があり、新しい孫が生まれて、そしてあの孫が、1歳半になって、叔父さんが「俺と76歳違うのか」というあのおチビさんが、亡くなって床にいるおばあちゃんを踏んづけちゃいそうになりますよね。普段、おばあちゃんが、そこにいて、向こう側に呼ばれて回っちゃったりして、なんだか知らないけど、おばあちゃんを乗り越えて向こう側に行こうとした。そこでハッと、皆が真剣になっちゃったわけですね。亡くなったおばあちゃんを踏んづけちゃだめだと。その雰囲気を察して、1歳半のイチゴ組の女の子は、そこでワーッと泣いちゃうわけですね。あれがまあ、あの映画の中で唯一涙の出てくる悲しい場面で、それを見ている僕もちょっと胸で詰まったんですけど。そこにあるのは悲しさではない。皆、赤ちゃんにむけて思わず「ああ、踏んじゃだめ!」と言う気持ちで動揺したんだけど、でも、すぐに「いいよね、いいよね」と言って慰める。孫になんの悪意があるわけではなし。皆、そこで笑うわけですね、そのことを。「何も知らないんだから、びっくりしちゃったよね」と慰める。そこでは、ほんとに新しい命が、おばあちゃんの傍らで新しくチーズからできあがっているんだという、ほんとにそこにあるチーズから宇宙が見えるという思いをね、いたしてくれるような場面で、あの場面が、私は一番好きです。
この上映シリーズは「家族の現在」というタイトルの下に、コーディネートしてくれた中村さんや、神谷さんが考えられたんだと思いますが、この映画は確かに家族の映画ではあります。見た感じ、お母さん、おばあちゃん、なかなか、ただ者じゃない。非常に力強い、淡々とした、しかも着々と、いろいろな準備もして、という流れは、女性はすごいなという、母親の家族の中での力、すごさの軸で考えることもできますよね。そういう意味では似たような映画としては「東京タワー」もそうですよね。ほとんどお父さんの話やおじいさんは出てこない、この映画もね。僕の好きなスペインのアルモダバルの女性を称揚するような、家族の中の特にお母さんというものを生き方の一つの、実は何でもなく、淡々としているんだけど、こうやってつなげて、じっと中に入ってみると、これはすごいものがあるんだというような、そんなことを考えることもできるかと思います。
ただ、この映画は「チーズとうじ虫」と名がついているのはダテじゃなくて、家族の中でどうのこうのというような、そんなスケールの話ではないんじゃないか、とも思うのです。もちろん近場にあるお母さんとそれを中心にした家族の日常なんだけれども、さっき申し上げたように、唯一涙が出るシーン、大泣きするシーンは赤ん坊だけで、それはとても明るい泣くシーンですよね。新しい世代を皆が許して、死んでいるおばあさんが、そこにいるというね。そういう意味ではあまり情念とか、ウェットなものはここにはない。その点がたとえば、お母さんものの映画である「東京タワー」とか、かなり、どろどろなところがおかしいアルモダバルの映画とは違いますよね。そういう意味ではもっと抜けた映画である。抜けた映画というのは、まさに宇宙に広がったような、そういう映画だなという思いをしたんですね。
もちろん家族というものの中にこそ、逆に子細に見ていけば宇宙のようなものか見えてくるととらえることもできるんだけど、我々、現在、人間科学研究所やらオープンリサーチ整備事業の一環として「対人援助学」とか「臨床人間科学」を展開しており、またこの映画講座もその一部ではあるんだけど、この映画は、何かそういうことを生業としている我々に突きつけるものというのは、まさに宇宙、コスモロジー、そういう俯瞰した目で人の営みを見せてくれている。
もちろん、いかようにもウェットな背景を、この映画から嗅ぎ取ることもできるし、この登場人物の中で一番お母さんの死でショックを受けたのは撮影者である監督ですよね。撮影の仕方、とらえ方、編集の時にも、いろいろな試練があったのかもしれない。しかし、だんだん後になればなるほど落ちついていくんですよね映像がね。よくよく見ると、ほんとに、あるシーンから、急に、お母さんの死、あるいは凱旋行進曲が出てきたところからですかね、ちょっと画質が変わりますよね。あのへんからほんとにあれを撮影している監督の覚悟というか、強さが出てきたのではないか。そういうふうにいろいろ勘繰ってみればね、いろいろそこにある撮影する行為を通じて、家族の中の一員の死を受け入れていく過程の記録である、と言えば言えると思います。
しかし、そんなことでもなく、実は我々が余りにつまらない「物語」を安直につくって、家族の中の問題とか、最近、いろんなことが問題になるんだけど、もっと実は広い視野に立てば、あるいは枠組みというものを、もうちょっと後ろから見ることによってね、うっかりすると「対人援助」とか、「臨床」だとか、「心」だとか言いながら、実はつまらない小さなセコイものを当てはめてしまって、そこにある、ある種もっと突き抜けた偉大なものを台無しにしてしまう可能性があるのではないかという、そういう反省のための、と言うと大雑把な話で恐縮なんですけど、そんな映画として、この映画を見られるんじゃないかと。
確かにこの映画は「家族」という単位の映画、文字通りのホームビデオですが、しかし、これはホームドキュメンタリーではなくて、コスモスドキュメンタリー、コスモスって実際にコスモスの花が引喩として映し出されますけど、つまり宇宙を見るような、そういう観点に我々を引き戻す、連れて行ってくれる、我々が商売をする過程の中で使いがちな、いろいろな「病理」とか、「障害」というものに対する概念の枠組みを、ほんとにそういうことでいいのかということをね、そういうことを、見返させてくれるような話ではないかと思ったんですよね。
この企画は、映画を見たり、映像を通じていろいろなことを考えるということが、我々「対人援助」の仕事をしている人間にとっては極めて大事なことではないかということを改めて思わせます。今日も、応用人間科学研究科の学生なんかも、全員参加すべきじゃないかと思ったりします。そんなに直截に対人援助について教示的に教えるようなものではなくて、何か大きな文脈がジャブのように効いてくるような映画というのは何本もあると思うんですね。
映画というのは僕の歳から言うと、小さい時、感動したというのはたいてい映画です。小さい時、びっくりしたり見て感動したという思い出は映画であったというのは事実ですし、映像についてはテレビより先に映画から入ってきた世代なので、特にそういうことを感じるんでしょうね。ら理屈で言うより映画を見た方がいいとは言いませんけども、何というか、やはりなかなか対人援助で教えていく時に方法論としての枠組みで、それはもちろんそのことを教えていくことは重要だけど、そのことは、ごく一部でしかないのだという、さらにその背景になるような価値の持っていき方などは、こういう映画を何本も見て、もちろん感想は人によって違うと思うんだけど、そういうことを話しあうことによって初めてできるような力もあるだろうなと思うわけですね。
昔、応用人間科学研究科を立ち上げる時に、某資格認定のための個別折衝のために某大学に中村常務理事と二人に個人折衝にいった時、約束の時間から3時間くらい待たされたんですね。椅子もないロビーで。だんだん腹立ってくるわけですね。ここで怒っちゃだめなんです、頭を下げてお願いに行っているわけですから。それで延々と楽しい話でもしてないとやってられないというので、中村常務と「映画の話をしようか」とかね。そういう話をして「今まで見た映画で一番感動的なものを5本上げよう」とかやったんですよね。いつかそういうビデオ・ライブラリーをつくって、そういうものを学生が見るように設定ができたらいいね。
この「シネマで学ぶ人間と社会の現在」を、京都シネマさんの協力でこんなゴージャスな形でできるのはすばらしいことでね。最初はテレビやDVDでみればいいやと思ってたんですが、大画面で見ることができるのは、やはりすばらしいことです。夢のようなことが実現できて、ほんとに僕もうれしいです。
因みにその時に「今まで一番感動した映画はなに?」という時、中村さんが言ったのは覚えてないけど、自分が言ったのは覚えている。その時に言ったのは「2001年宇宙の旅」と言ったのを覚えています。皆、知ってますよね。モノリスというキーワードになる、変ちくりんなものが出てきて、最初、初めて人類が立ち上がった時に手に持っていた骨で攻撃して仲間を殴ったりするところからスタートする。暴力からね。それをポーンとほり投げると次のシーンではその骨が宇宙船になっているという有名なシーンから始まる「2001年宇宙の旅」、大変有名な映画ですよね。僕はそれが非常に印象的な映画として残っているんですね。
SF映画の最高傑作と言ってもいいと思います。しかもCGは一切使ってないんだけど、宇宙船とか惑星とか、すごくいいんですね。もう一つ有名なのは、そこでハルというコンピュータが出できて、それは途中でドジ狂っちゃう。自立しちゃうんですね。人間の言うことを聞かないで。宇宙船どこに行くんだろう。最後にどこに行くかよくわかんない。当時の流行語、当時の言葉としてサイケデリックというものが流行った時代ね。そういうものの感覚、宇宙船の先には胎児の形をした惑星が見えてきて、そこへ突っ込んでいくような、何がなんだか最後はわからないような映画なんですよね。あまりの映像のすばらしさと、シネラマ状の画面で前の方で見たので、ほんとに宇宙の中に突っ込んでいくような感じと、全く今までなかった画像と音楽の使い方のうまさですよね。骨をポンと投げて宇宙船になる時、ワルツがパッと流れる。いかにもあのスタンリー・キューブリック監督のやりそうな話ですよね。
その話をなぜ持ってきたかと言うとね、それは宇宙論というかコスモロジーに近い話なんですよね。非常に希有壮大な時空を超えた宇宙にまさに探検隊に出てくるような人たちが活躍する話なんですけれど、最後の結末はわけがわからなくなって、どんどん光か、時間がすっ飛んじゃっていくような中で胎児の形をした星に近づいちゃうなんてのは、ある種、とてもスピリチュアルなものを感じますよね。翻って今日の映画、これはね、ある意味では「2001年宇宙の旅」よりも、もっと宇宙観のある映画でしゃないかと思ったんですね。アメリカ映画はあのへんからだんだんおかしくなってきたと思うんだけど、だんだん極めて臨床的な、トラウマがどうとか、人間の内面に迫ってくるようなことを、あらゆる活劇の中にも忍ばせるような形で命脈を保ってきたんだけど、いよいよその種も尽きましたね、ハリウッド映画はね。斉藤環さんも言っているけど、アメリカ映画は今まで心理主義でもっていた。大抵出てくる。もちろん「スターウォーズ」もそうです。不思議なへんなトラウマとか小さい頃の思い出が絡んでいる。そういうのがだめになって、スタートは「2001年宇宙の旅」で宇宙へ向けた壮大なものを持っていたかと思ったのに、実は最後はそういう結末だったのでね、中途半端な、そこからだんだん心理主義、悪い意味でのスピリチュアリティに回帰してくるような感じが、今思うとね、この映画を見ちゃうと、そう思えてきちゃったんですよね。
今日の映画の方が実は、これで二度目なんだけと、よく視ると極めてディテールが計算されているところがあると思うんですけど、特に後半ね。そこで描かれて結果として出てきたものは、ほんとに、うじ虫とか、小さな、汚らしいようなもの、チーズとうじ虫、そこを「そんなレベルにも宇宙は見られるよ」という、そういうものを観客に、具体的な、淡々とした生活の記述から見せた点ではね、実は何か実際の宇宙船を見せたり、宇宙を見せたりする「2001年宇宙の旅」よりも、極めて大きなものを我々に見せてくれたんじゃないかと感じたんですね。
実は、視る前は知らなかったんですが、この映画は2005年に山形国際映画ドキュメンタリー賞をもらっているんですね。同じくフランスのナント三大陸映画祭ドキュメンタリー部門の最高賞。海外で有名なわりに日本では知られてない映画で、知っている人は知っている映画だったんですね。これは確かに賞をとったということではなくても、ギンスブルグの言葉を考えながらこの映画を見直してみると、なるほどな、という部分が、極めて強くあって、どこまでもアカデミックな話もできるし、一方で淡々と記録をするという、そのものを何の解釈も言葉で表さなくても、ここまで実は大変なことを我々は見いだすこともできるし、示すこともできるということを表している、大変面白い映画ではないかと思うんですね。そんな印象を受けました。皆さん、どんな感想があるか。ちょっとあんまり決定づけちゃうと、皆さんが折角、ここから得られた大事な印象を壊しちゃうといけないんで、ぜひこの続きはロビーに行って。ちょっと高いコーヒーをケータリングしていますし、エンゼルパイより、もうちょっといいお菓子があるそうですので、みなさんでお話をしながら、お菓子を食べてごゆっくりされてください。
因みに次回1月17日は「ディア・ピョンヤン」。監督のヤン・ヨンヒさんと神谷さんの二人を招いてゴージャスなセッションになると思いますので、ぜひご参加ください。どうもありがとうございました。