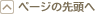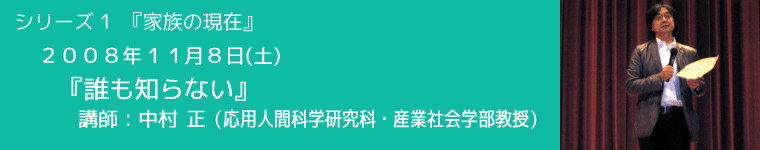
日本映画は家族を描くのがうまいと思います。たとえば、小津安次郎監督です。また、山田洋次監督は、ずばり、「家族」という題名の映画を撮っています。激変する社会に翻弄される家族の姿がリアルです。文字通り、「社会と家族」というテーマの映画です。さらに、現在の家族問題にとってもつながるテーマを「家族ゲーム」という映画が描いています。胸騒ぎする家族の映画、感情の波風が立つような家族の映画、つまり見たくないものを見せられたというあたりを意識して、今回のラインナップを揃えてみました。
 さて、今日の映画です。一般的に言えば虐待とか、中でもネグレクト、ほったらかし、それに関するテーマであることは間違いありません。日本社会ではabuseとneglectが混同して使われていますが、明確に違う言葉遣いです。ネグレクトは、放棄(ほったらかし)です。定義をすればそんなことになります。2006年度の統計を見ます。虐待の相談件数は4万件を超えています。いろんなタイプの相談が入っていますから、すべて虐待ということではないかもしれません。それを分類しています。身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、そしてネグレクトと分かれています。あえてマトリックスを使えば、そんなふうになっていきますが、こんな話をしても多分、届かない現実を、この映画は描いているのだろうと思います。
さて、今日の映画です。一般的に言えば虐待とか、中でもネグレクト、ほったらかし、それに関するテーマであることは間違いありません。日本社会ではabuseとneglectが混同して使われていますが、明確に違う言葉遣いです。ネグレクトは、放棄(ほったらかし)です。定義をすればそんなことになります。2006年度の統計を見ます。虐待の相談件数は4万件を超えています。いろんなタイプの相談が入っていますから、すべて虐待ということではないかもしれません。それを分類しています。身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、そしてネグレクトと分かれています。あえてマトリックスを使えば、そんなふうになっていきますが、こんな話をしても多分、届かない現実を、この映画は描いているのだろうと思います。そうした説明は、それはそれで理解するけれども、生活のリアルさや子どもたちのたくましさやなんともいえない母の無責任さやおそらくは異母きょうだいであることや周りに助けてくれる人のいることの安心感や兄の健気な努力等、いろんなことが描かれているので、ついつい自分がその周辺にいるような感じで見入ってしまいます。
もちろん、社会的にはこの兄弟姉妹は、この後、どうなっていくのだろうかという関心が成り立ちます。いずれ子どもたちだけの生活はもたずに児童相談所が入って一時保護をしたり、養護施設で暮らす手筈を整えたりしていくことは容易に考えられます。しかしそうした顛末では何か安心できない、そうしたことだけでは後味の悪いことが描かれています。おそらく兄は福祉というよりも、処罰されて児童自立支援施設で暮らすのだろうなと思います。
しかし、後のことは、いったんどうでもよくて、そのまま子ども同士で生き延びて欲しいとも思ってしまいそうなくらいに健気に生きることに声援を送ってしまう自分を見いだします。そのギリギリまで、もう少し児童福祉の話をする前に何か考えなければならないことがたくさんあることを直視すべきだということを描いているなと思いました。
私は今、ある児童相談所に通いながら「虐待をする親」たちと一緒に、できれば、もう一度家族でやり直すための作業をしています。児童虐待防止法では「家族再統合」と呼ばれています。しかし、なかなか具体的なヒューマンサービスがそこにはありません。まだ言葉としてあるだけで、親として生き直していきたいと願う人たちが多くて、やり直し、修復、いろんな言い方でニーズがあります。虐待された子どもたちを保護して、ケアすることに精一杯で、虐待する親への指導や面談まで十分でないのです。
虐待をする親、それは「何という親だろう」と、世間は思います。もちろんこの映画の母親も、世間的にはそう思われる親の典型です。しかし、この母親はどことなく憎めない側面があります。異母きょうだいであるので、父親が何人かいます。その父親たちも絶縁しているわけではなく、苦しい生活をいきています。コンビニの店員も温かいかかわりがあります。世間は虐待親を「何という親だろう」と一蹴して終わりです。でも、そう名指しされる親たちと一緒にいると、そうした親の課題が見えてきます。何とかやり直したくて、週末だけ子どもが帰ってくるようになった親もいます。でも、そう言うときが一番不安で、うまくいくだろうかと不安でしょうがないんですね。次の年の4月になったら、学年が上がるので、もしかしたら子どもが帰ってくるかもしれない。虐待で子どもは離されていますが、この親たちも不安なんです。人に愛着を欲する親たちや、親自身が十分に愛情を注がれなかったという事例がほとんどです。映画の母親も同じように自らの愛情不足のなかを生きています。
私は社会病理学が専門です。児童相談所で虐待をするとされた親たちと話をしたり、少年刑務所で犯罪をおかした人たちが社会に復帰する加害者臨床、司法臨床をおこなっています。また、DVをする男性たちと暴力を振るわないで夫婦生活を営んでいけるようにするという仕事もしています。加害者と言えば加害者なんですけども、何らかの問題を背景に持って逸脱とされる行動をする人たちと、何とかやり直す作業をお手伝いします。
その中から感じることですが、映画の母親も確かにネグレクトですが、そのネグレクトの前後左右、そこの文脈をもう少し考えた方がいいと「誰も知らない」は言っているように私には見えました。「誰も知らない」という映画が語る「ネガ像」みたいなものを理解した方がいいと思います。それは端的に言うと子どもの世界を、ここまで描けているということです。成長のメタファが至るところに出てきます。それは植物を育てたり、スーツケースのサイズが合わなくなったり、大きくなっていく様子、いろんな逆境の中にあって子どもが成長していく大きな主軸が、そこに描かれているなと思いました。
虐待するとされる親たちと話をしていく中で、一番親たちが変わっていくなと思う側面は、子どもの成長です。子どもが変化していくことに親がつられていくという感じがします。子ども自身が変化していく姿に家族再統合、あくまでも家族でやり直すということを考えた場合、お母さんも帰ってくるかもしれませんが、もしやり直す場合でも「子どもの成長」「子どもの最善の利益」が大事な観点だと思います。親がやり直したいからだけではなく、子どもの最善の利益という点で、家族でやり直す必要があるとなれば、それに向けて援助に入った方がいいだろうし、「いや、まだ、こんな親と暮らしたくない」と子どもが思う場合は、そうならないだろうし、子どもがそのことをどう思うかが重要な変数です。子どもがきちんと判断する力があって自ら成長していく中に寄り添いながら親たちが変化していくということは、虐待親への支援をしているとよくでてきます。この映画は、そんなことをとても感じさせてくれました。
キレる子どもたちとか、いじめもあり、葬式ごっこという形で、そしてひきこもりとか、家出とかありながら、学校にいっていないとか、子ども問題がよく話題になります。が、考えなければならないのは子ども自身の世界を私たちはきちんと見ているだろうかということなんですね。兄の姿に重ねて、では自分の小学校6年生から中学校1年生にかけてはどうだったかと思います。「私の小学校6年生はあんなだっただろうか」と考えて感情移入して観ていました。男の子としての育ちを彼に重ねて想起していました。
子どもは子どもで、きちんと生きる力があって、パワーを持って変化していく姿で痛々しくもあり、健気でもあり、甘えもみせ、万引きを思いとどまる規範も身につけており、そうした葛藤がとても感動的でした。しかし他方で、「家族不安社会」といえる状況もあります。家族の不安を煽る言葉遣いが多いからです。最近、家族を描く日本映画が多いことも芸術家の感性が無意識に家族のかたちの変化や時代や社会の無意識をとらえているのでしょう。虐待が増えたという文脈で家族不安を煽る言説に私はとても憤慨しています。虐待が4万件になったといういい方も同じです。そんなに騒ぐ必要があるのか、あるいは正確には、騒いでどうするのかということです。家族不安を煽っているだけのような気がします。そうじゃなくて、この映画は「もっと見つめなければならない現実があるんだよ」という形で見せてくれた、子どもがどんなふうにそこに生きているかということを。
『子どもたちの感じるモラル』という本があります。この映画を見た時にパッと思い出したのがこの本でした。児童精神科医のロバート・コールズさんが書いた本です。こうした子どもたちは厳しくて、最重要の仕事を、何か食べたり、飲んだり、栄養をとったり、まさしく根源的な意味での生きるという仕事を、どのようにやり遂げているんだろうか。弱い子どもなのに自分よりももっと弱い子どもに応えようと努力する。それは良心に促された努力だと言います。その良心のルーツは記憶された声、瞬間、光景、出来事にあるとも語っています。これは多分、母親との、映画の最初の方に描かれていた蜜月だったのだろうと思います。ディテールが詳細に出てきます。母親のマニュキュアを零した後とか。何ともならないネグレクトの親ではあるんですが、子どもたちの中に、その像はちゃんと沈着しているわけですね。この兄が示した良心が、どこから出てくるか。万引きをようやく思い止まりましたよね。援助交際をしながら稼いでくれたお金、最後に「貸してよ」と言いましたけど、突っぱねましたよね。あのモラルはどこから出てくるんだろうかと思います。
それとともに私は男性のことにとても関心があって、男性学や男性性と暴力と攻撃性のことを研究しています。ですから、兄の明くんの少年期のあり方に、とても関心が向かいます。あわせて父親たちにも関心が向かいます。明くんがいろいろ訪ねていきます。タクシーの運ちゃんだったり、パチンコ屋の従業員だったり、まだ他にもいるかもしれません。この父親かもしれない人たちとのやりとりが、とても短いですが、印象深く残っています。5000円、なけなしの金をはたいて出してくれました。あのお父さんとの会話、「チン毛は伸びたか?」、とてもよかったと思っています。「グローブがほしい」と言いました。時々遊びたくなって少年の仲間たちに明くうは入っていきます。危なっかしいなと思いつつ、何か変化をしていく。そして「お兄ちゃん、風引いたの?」という声変わりも、とてもうまく挿入されているなと思いました。こういう中で何かモラルを感じてケアする役割に徹していた明くんは、やはり男の子の育ちの中をベースにしたモラルが動く時を描いていると思います。
そして母よりも女であることを選んで時々、お金をくれることも印象的です。あのお金、もっと早く届いたらなと思う最後の場面がありました。なんという母親だろうかとも思いますが、それでもどこかにある、母への思いというのが、このきょうだいたちの絆となっています。帰ってくるかもしれないという思いでいきています。時間の経過が絶妙に描かれています。クリスマスの時の描写が印象的でした。将来、家族再統合となるかも知れません。あるいはずっと施設で暮らして社会的養護の方に入っていったとしても、子どもたちはここで生きていたということや絆を大事にしながら、この子どもたちの支援をする必要があると思いました。子どもたちがどう生きてきたかを大事にしないと、家族再統合や、児童福祉の言葉遣いが何か届かないのかなということです。それまで子どもたちはどんな具合に生きてきたのか、虐待する親やネグレクトする親であっても、よい親の姿を保持しているかも知れない。親を否定することはこうしたよい記憶を否定することになるということです。
保護されるだろう子どもたち、もしかしたら今後、どうなっていくかわかりませんが、社会的養護となります。児童相談所がかかわります。保護される子どもたちを弱い者として想定してはいけないと思います。だから、結末として、この子どもたちは保護されるだろうことを思って安堵してしまうことはいけないと思います。早く保護の方へということだけでは片づかない問題が、たくさん私の中に生起をしました。保護されるだろう子どもたちを想定して安堵する前に、あるいはそれだけではなかなか安堵できない自分かいたりして複雑な思いをしながら何度もこの映画を見ました。
だから、虐待と騒ぐ前に、虐待だと通報する前に、「社会は何をしなければならないのか」ということを、この映画はとても考えさせてくれました。虐待喧騒、虐待、虐待と騒いでいくだけで本当にいいんだろうか。その前に、子どもたちが成長する力を持って生きていくプロセスが、この映画の中にとてもよく描かれていたので、児童福祉とか、虐待という言葉だけで語れないものが、私たちが見落としてしまうものがあるんじゃないかと思います。成長し、何か支えがあったりする中で子どもが生きる力をそこに十分蓄えていることを、もっと直視した方がいいのではないかと思ったりしました。虐待やネグレクトについての安直な理解を啓発した物語とだけで観てはいけないということです。
児童相談所で親たちと接触していますと、映画のなかの親たちとよく似た親はたくさんいます。それはギャンブル依存症だったり、アルコールの問題も抱えていたり、あるいは女性として男を追っ掛け回したりという感じのものが今日はとても強く出ていましたけど、「自分のことで精一杯」という親たちがたくさんいます。「自分のことで精一杯」という親たちに対して、それはハタから見たら、とても勝手な生き方のように見えます。でもそうせざるをえない背景が一人ひとりあります。
複雑なのは加害者を告発して捕まえて「責任をとれよ、お前」というタイプだけでは、なかなか動かない人たちが、たくさん、親として登場してきます。この親たちといろいろ話をしながら、何かをほぐしていく作業をしているんですね。その中で見えてくるのは、その親たち自身が抱えている傷のことです。現在、一緒に関わっている虐待する親たちは、その子ども時代、多くの人が歩んできたわけではない苦しい現実を生きてきています。必ずといっていいほどの親たちの子ども時代は十全ではなかったなということです。つまり、映画であったようなサバイバルする子ども時代を過ごしてきたということです。30や40歳になって、確かに虐待してしまった、ほったらかしてしまっているという親たちですが、もう一回、その場に来て語り直したり、見直したり、反省したりするというプロセスを踏む中で、もう一回、自分の子ども時代を、今、虐待してしまっている、ネグレクトしてしまっている子どもたちに重ねながら理解たり、意識の上にのぼさせたりする作業をすることにしています。一緒に場を共有するだけですが、それしか私にはできないんですけど、とても貴重な時間を親たちと過ごさせてもらっています。
明くんのお母さんにも、そういう場があればいいのになと思ったりしますけど、なかなかそこにつながらないんです。そんなことを思いながら、子どもたち自身の生きる力に依拠して家族再統合をどうやっていければいいのかなということを考えさせてくれる映画でした。幸いなことに社会的養護の仕組みの中で、こんなケースを今、一緒に取り組むことができています。養護施設をうまく使いながら家族再統合をしている夫婦の事例です。一旦、壊れかけてしまった絆は、お母さんは明くんも好きなんですけど、お母さんの衣装を売る、売らないで揉めますよね。複雑な両義的な感情がよく出ているなと思いましたけど、それとよく似たことをやっているお父さんとお母さんがいますかなり激しい虐待で今、二人のお子さんが児童養護施設に入っている。お父さんとかなり話し込んでグループワークをしています。児童養護施設を利用しながら、児童養護施設から帰ってくるだけが家族再統合ではなく、児童養護施設を信頼しきって、週末帰ったり、年末年始帰ったりしながら家族再統合をしている方です。
そういうこともあるかなと思う事例です。つまり、家族だけでもなく、児童養護施設だけでもない、いろんな暮らしの形がそこにあってもいいんじゃないかということを思うわけです。このきょうだいも、一度、保護されたことがあると、エピソードで語っていましたね。でも「きょうだいで暮らしたい」と思っているわけです。これができるような、たとえば別のタイプの里親事業があればいいなと思います。施設か、家族かという二者択一ではない社会的な場面セッティングがどうできるかということを、この映画は鋭く問うているなと思いました。なぜかと言うと、このままきょうだいたちが保護されていくだけだと安堵できない自分がそこにいたからです。そうじゃない仕組みを社会がどうつくっていくかということです。そんなことがとても大事で、福祉か、家族か、施設か家族かだけではなく、今後、仕組みを、どうつくっていくかということの方でしか、このささくれだった私の感情がおさまらないと思いました。
虐待しているとされるお父さんたちと過ごしていると、そこにはそのお父さんやお母さんの家族なりのルールがあって、児童養護施設のワーカーさんやカウンセラーさんも頑張っているんですが、虐待家族の場合、通例の家族がもっているストーリーとは異なるルールがあって、そこには家族としての絆がある場合もあり(虐待する親のもつ両義的な性格の絆)、単純に制度が想定している回復モデルには乗らない人たちなんですね。乗らない理由が「一緒に暮らしたい」とか「忘れた頃にお金が届く」とか、何となく家族の秩序や記憶がそこにあり、幼いなりに核心となる絆感や傷つき感があるということです。家族の記憶に根ざしたケア、子どもたちのもつ内在的な力をひきだすカウンセリング、ネグレクトした母親ではあるが確かによい思い出もある家族の肯定性等をもとに、これからの人生を生きていく子どもたちであって欲しいと思いました。そしてそんな風にして、私は私の家族を生きているだろうかとも考えさせられました。
本日の映画をスタートにして、「家族は小説より奇なり」ということでたくさん話が続いていきます。ドキュメンタリーもあります。とても不思議な家族が世の中には多くて、自分が育ってきた家族や、こうありたいと思っている家族の姿だけではない、相対化してくれる家族の物語です。映画であるが故に余計にイマジネーション豊かにかき立ててくれます。立命館大学は衣笠キンパスで土曜講座をやっています。びわこ草津キャンパスでも講座をやっています。ここ朱雀でもこうした講座ができればいいなと思っています。京都シネマさんと一緒にやっていこうと思っていますので、ぜひ、今日を皮切りに月に一度、朱雀講座は映画とミニレクチャーということで日程を組んでおいていただければと思います。
Copyright © 立命館大学 All rights reserved.