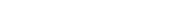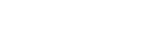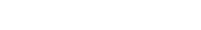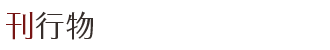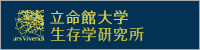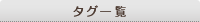『生きることと自己肯定感』(高垣 忠一郎 著)
新日本出版社
津止 正敏・津村 恵子・立田 幸代子 編 2004年7月/六四並版/総頁数:224頁 1,575円(本体1,500円)
いま、家庭や学校・社会のなかで押しつぶされ悲鳴をあげている子どもたち。著者は、「自分が自分であって大丈夫」という自己肯定感の大切さを伝えたいと、自らの体験とカウンセリングの実例を紹介しながら、やさしく語りかけます。迷い道に入りこんだ子どもの心と自信を失いかけているおとなの心が新しい生き方を求めて感動的に響きあいます。
関連プロジェクト
目次
| ■はじめに | |
| ■第I部 | 子どもの問題と自己肯定感 -「魂(いのち)の故郷」をもっていますか? |
| 1. | 子どもの問題とどう向き合うか |
| 2. | 調子どもの「パニック」「攻撃」と「不安・恐怖」 |
| 3. | 「守りの枠」のない子どもたち |
| 4. | 子どもの「心の問題」と自己肯定感 |
| 5. | 自己肯定感を感じさせない社会の病理 |
| ■第II部 | 生きることと自己肯定感 -「さようなら」と「こんにちわ」の峠 |
| 1. | 「さようなら」と「こんにちは」を生きる |
| 2. | 人は自分の物語を創りながら生きる |
| 3. | 「人生を生きること」と自己肯定感 |
| ■第III部 | 平和と自己肯定感 -「大きな存在」に身をゆだねる |
| 1. | 平和と「心の教育」と子どもの心 |
| 2. | 「自分が自分であって大丈夫」という自己肯定感 |
| 3. | 二つの「自己肯定感」と日本のゆくえをめぐって |
| ■あとがき |
関連企画「大人と子どもは出会えるか-良い子とは誰か」(自分探しとななにか-自己実現の幻想を問う-)
| 日時 | 第1回 2004年11月12日(金)18:00〜20:30(開場17:30) |
|---|---|
| 会場 | 立命館大学衣笠キャンパス 創思館1階カンファレンスルーム |
| 講演 | 竹内 常一 國學院大學文学部教授 |
| パネルディスカッション |
|
| 司会 | 滝野 功 立命館大学応用人間科学研究科教授 |
 竹内 常一 さん
竹内 常一 さん- 國學院大學文学部教授。
竹内常一教授は少年期・思春期・青年期のさまざまな問題に永年関わり、その広い知見と鋭い分析によって、小さな日常的事象から、隠されている大きな問題を読み開き、歴史的変遷を絶えず意識しながら、教師を初めとする対人援助の現場のさまざまな実践家に対する適切なアドヴァイスを与え続けて来たことで、よく知られています。非行問題を初めとして教育・心理・福祉など対人援助領域全体のスーパーヴァイザーとも言える人です。  遠藤 昌子 さん
遠藤 昌子 さん- 京都市立伏見工業高等学校養護教諭
京都で生まれ京都で育つ。養護教諭歴20年余り。現在は京都の定時制高校に勤務中。『保健室は「空気がやさしい」「学校でホッとする場所」「落ち着くなー」』という生徒たちの言葉を励みに今日もがんばっています。今は大変生き難い世の中、生徒たちの中には先が見えなくなったり、希望を失いかけたりしていることもよくあります。
本格的に社会に出るまであと少し、「保健室に出会えて良かったな」と思えるメッセージを伝えたいと思っています。  村本 邦子 さん
村本 邦子 さん- 立命館大学応用人間科学研究科教授
精神科クリニック思春期外来に3年間勤め、自身も子どもを持ったことをきっかけに、1990年、女性ライフサイクル研究所を設立。以降、女性と子どもの臨床に携わる。現在、2人の子どもたちは思春期に。『「しあわせ家族」という嘘』(創元社)、『思春期の子育て』(三学出版・共著)、その他、子育てや家族についての著書多数。
当日の様子


竹内常一教授

村本邦子教授

遠藤昌子先生

春日井敏之教授

滝野功教授
2004年11月12日(金)、18時から、立命館大学衣笠キャンパス、創思館1階カンファレンスルームにおいて、連続講演会・シンポジウム『大人と子どもは出会えるか ―良い子とは誰か?』の第3回(最終回)「『自分探し』とはなにか ―『自己実現』幻想を問う」が開催され、会場には学内外から140名以上の人々が集まった。
ゲストには、竹内常一教授(國學院大學文学部)、遠藤昌子先生(京都市立伏見工業高等学校定時制の養護教諭)、村本邦子教授(本学大学院応用人間科学研究科、女性ライフサイクル研究所長)お三方をお招きし、滝野功教授(大学院応用人間科学研究科)が司会をつとめ、春日井敏之教授(文学部)の挨拶で開会した。
冒頭の挨拶で春日井教授は、前二回の講演会・シンポジウムを振り返って、今回は、これまでの少年期・思春期の論議を受けて、青年期を主なテーマにして進めていきたいと述べた。また、今回のテーマにもなっている「自己実現」という言葉の扱いについても改めて注意を喚起した。
これに続いて竹内常一教授の講演がなされた。初めに「青年期」の捉え方の難しさに言及し、思春期とのつながりから、映画『スタンドバイミー』に見られるチャム(同年代・同性の親密な仲間)を例に出しながら、自分たちの新しい価値世界を立ち上げていく時期のことを話された。また、青年期の状態の曖昧さを「宙ぶらりんの青年期」と表現し、本当の「IDカード」を持たないこの時期を生きていくことは並大抵のことではないとも話された。これに関して、大学生の学生証の話をされ、ご自身が現在つとめていらっしゃる大学では、二部(夜間)の学生にとってはどうも学生証は彼らのIDではないらしいという、おもしろい観察も紹介された。話題は「不安定を生きていく力」から「生きるに値する世界を発見していくために長い青年期を遍歴していく」「第二の誕生があるかないかわからないまま歩いていく」現代の青年たちへの共感へと移っていった。
また、「常識」に凝り固まった青年というのは「権力の言葉」に占拠されてしまっているとし、教育基本法改正や教職を目指す学生たちのことにも言及しながら、権力との関係に無批判な「良い子」は自分の言葉を持っていないようだ、と述べられた。ナラティブ・カウンセリングの視点から、子どもがどれだけ他者の言葉によって侵食されていて、どれだけ自分の言葉をつくれているかに注目するご自身の観察方法を、ミハイル・バフチンの「人間のどの声も、他者に向けられた声である」という言葉と関連づけて語られた。それによれば、一人の子どもはいろいろな人に向けていろいろな言葉を発するものであるが、竹内教授自身は、「自分が子どもから受け入れられているんだろうか」ということがいつも気になるという。
話題は「子どもがどんな他者とのつながりをもっているんだろう?」という問いへとつながっていく。「重要な他者」である親との関わりから始まり、さまざまな関わりを経験するが、危機に瀕した時には最も印象的な関わりが甦るのだという。また、教育関係者の側から見れば、新しい子どもとの出会いによって「子ども」像を壊されていくことにより目の前の子どもが見えてくるのだとも語られた。竹内教授は「子どもを受け入れるということは私が子どもから受け入れてもらえるということ」であり、自分は目の前にいる子どもの中の印象的な他者と入れ替わろうとして子どもと関わっている、と話された。子どもは身体の中にこれまで出会った他者を取り込んでいるので、それに替わる新しい他者として子どもの前に登場することが重要だと述べられた後で、「自分探しというのは他者との関係づくり」という一つの定義を示された。
また、チャムのような親密な関係は身体の呼応から始まるのではないかという観察から、現代の子どもたちが求めているボディコミュニケーションにも言及された。そして、青年期の親密な仲間との関係は、親や教師によるのではない新しい評価を自分にもたらし、大人に強要されたのではない新しい意味世界を立ち上げていくことにつながっているという。現代の子どもたちが持っている意味世界は、学校どころではなく、サブカルチャーによって完全に網をかけられており、その中で自分たちの文化や自分の言葉を編み上げていくことが青年期のテーマであるというお話をされた。最後には、異なる他者との間に共通語をつくっていくことが、子どもにとって重要なのはもちろんだが、大人もそれができていないということを指摘されて講演を締めくくられた。非常に多くの事柄を語られた講演であった。
遠藤先生は、竹内教授の講演の締めくくりに応えられて、定時制高校の生徒たちの使う「おはよう」という挨拶に最初は驚いたが、今はその意味を汲み取れるようになって自分も使っているというお話から始められた。そして、テレビドラマ『めだか』に描かれているのとはかなり違う、現実の定時制高校の様子を、実例を交えながらわかりやすく紹介してくださった。ただし、「定時制がああいうかたちで話題になることは非常に嬉しい」とも言い添えられた。
「学校に来て何か意味があるの?」「高校って何なん?」「どうせ俺ら定時やし」という生徒たちの問いかけに自分は上手く答えることはできないと言いながら、つらい体験にあいながらも健気に生きている生徒たちの様子を伝えてくださった。彼らは「どうしたらいいかわからない」ような困難な中学高校時代を送り、さみしさ、悔しさに諦めまでもが追加されるような境遇にあっても、友達や大人の中で自分を変えるきっかけを掴むことで乗り越えられるという。
初めて定時制に移ったときは「世の中の常識がひっくり返った」と遠藤先生は言う。それまで当り前のように思っていたものは大人が都合のよいように勝手に決めた枠であって、それは生徒たちにとって幸せではないんだなぁ、彼らにとって生き易い枠というのは別にあるんだなぁ、と感じたという。また、とんでもない中学時代を送ってきた生徒が、定時制高校に来て優しい目を輝かせているのを見ると、「いつからでも変われるんだ」と学ばされるという。いま彼らが自分にかけてくれる「おつかれ!」の言葉がとても温かく自分を支えてくれるという。
ここで遠藤先生はある卒業生の答辞の言葉を紹介された。そこには、初めて経験できた教師との親しい関係、学校にたいする思いの変化、挫折と親や教師や仲間の援助、素直になっていった自分のことが綴られていた。
話題は定時制の生徒との関わり方へと移っていく。彼らは明確な答えよりも、傍にいて一緒に悩んでくれることを喜んでくれる。「横にいて体温が伝わるような関係で接することなしには彼らの心はひらけない」と遠藤先生は言う。ゆっくり関わっていくことが自分たちのモットーだとも話された。
最後に、定時制高校の統廃合問題に触れられ、「大人が思うより大きなダメージがある」と警句を投げかけられた。また、学校のフレックスタイム制について、「人やクラスメートとのつながりがないところでは、癒されず、次へも進めないということをよく考えてほしい」と訴えられた。
村本邦子教授はまず、家族をはじめ様々な人々との関わりが自分にとっての「現場」であると定義された。そして、「自己実現」という言葉について、それを用いるのは誰かという疑問を投げかけられた。その答えとして、マズローの自己実現の考え方に言及されながら、「おじさん」たち、主婦たちが先ずそれにあたるというお話をされた。彼らの使う「自己実現」という言葉は、楽しいことをしてお金儲けをするというような意味で使われている。村本教授の「現場」では、「自分探し」や「自己実現」がテーマになることはまず無いという。
しかし、「自己へのこだわり」というふうに意味合いを広げると、それは現場でよく見られることだ。ただし、自己へのこだわりを持つことは、ある種の特権性と裏腹である、と村本教授の話は展開する。実話に基づいた映画『モーターサイクル・ダイアリーズ』を例にとり、「旅をするために旅をする」ことのできる裕福な主人公のことを語られた。それに続き、日本の若者のバックパッカーやワーキングホリデーの文化が、安いパックツアーが可能になったことと連動して起こってきたと分析される。
「特権的なところで育てられた子どもたちは、限定された世界の中でしか生活できないが、その中では自分を見出せない。自分と出会うために、その守られた空間から出て行かざるをえない」と村本教授は言う。ここで、人が「自分」を感じるのはどんな時か?という問いかけをされ、ご自身が妊娠された時の体験から、他者とぶつかったり反発したりする時だという答えを導かれた。そして、「自分と出会えない子どもたち」ということでは、ご自身の現場の子どもたちが念頭に思い浮かぶという。その子どもたちは、他者の評価によってしか自分をかたちづくれず、自分がどう感じているかではなく他者にどう思われるかが大事になっているという。
そのような状況にあって、子どもたちの「二極化」が進行しているという。一方の子どもは「下りて」しまって未来への希望をなくしており、もう一方の子どもは、注意深く先の先を見てリスクを冒さない。そういった子どもたちには、「一度この特権性を手放したらもう人間らしい生活はできない」というような脅しがあって、冒険ができない。
そこから浮び上がってくるのは、脅しをする親たちの「自己愛の延長としての子ども」である。そのような親によって、子どもは傷つきやすく、傷つくのが恐くなってしまう。ここで村本教授は「『傷つき』は悪いことだ」「傷つかないように」と考えるのではなく、「傷つき」と上手につきあう方法を教えることが重要だと述べられた。また、アリス・ミラーが「傷ついた後にそれを表現して、他者が共感するというのがよい」と述べていることも紹介された。
これに続いて、司会の滝野教授からも「自己実現」というテーマは安易に肥大化していることが指摘され、このシンポジウムのひとつの意義が確認されることになった。
休憩の後は、フロアから上がってきた質問紙に答えるというかたちで再開した。竹内常一教授は、最近言われている「自己実現」や「自分探し」の出どころとして、1996年の中央教育審議会答申が「教育とは自分さがしの旅を扶ける営み」と規定していることに言及された。また、現在の社会状況の中では、子どもたちは自分の「個性」を探してそれを売り物にすることを強制させられていると述べられた。
「『自分探し』の対義語は何ですか?『他者探し』ですか?」という問いに関連して竹内教授は、「自己実現をしようとする人は、他者の自己実現を保障しないといけない。するとぶつからざるをえない。ぶつかったときから社会をつくっていくわけだから、自己実現は社会づくり。関係づくり、社会づくりでないかぎりは、『自己実現』というのは『勝ち組み』のお話にすぎない」と述べられた。
「現代の子どもに他者を抱え受け止めることができるのか?」という問いにたいしては、ご自身で実践されている文学教育について紹介され、「教師というのは境界を越えにくいところで苦しんでいるもの」であり、他者とどのように関わっていくのか、子どもとどのような関係づくりをしていくのかというところが焦点になっていると述べられた。また、対人援助を実践する者は、「思いもかけない関係づくり」をしながら、現在の社会における人間関係とは異質な、互いに生き易い関係をひそかにつくっていっており、そのことと結びつけながら、一人ひとりが背負い込んでいる問題を考えていきたい、と話された。
村本邦子教授は、「傷ついた自分と上手くつきあっていく方法を教えてほしい。先生はもう傷つくことは恐くないのか?」という問いかけにたいし、「傷つくことが恐いとか恐くないとか考えたことはない。生きているかぎりは避けがたくあるものだし、それを切り抜けてくるときには他者に助けてもらったし、その経験ごとに支えてもらったという実感が積み重なってきたことで、傷ついたときのつらさがだんだん減っていく」と答えられた。
また、バックパッキングやワーキングホリデーによる自分探しについての問いに答えられて、青年期のイニシエーションというのは命がけであり、それでも親は背中を押してやらなければならないんじゃないかと話された。ただし、その若者がどこに着地するかということが重要で、自分の安寧を超えて世界と出会ってほしいと述べられた。また、思春期以降の引きこもりについても、いきなり放り出すことがよいのではなく、時間をかけて、方向性を見出しながら援助していくことが必要だと話された。
遠藤昌子先生は、「高校卒業して何の意味があるの?という子どもの言葉にどのように答えているのか?」という問いかけに、その子どもは何がしたいのか尋ねるとともに、学校というものについて改めて考えなおしてみるいい機会になるとか、友達や人間関係のことをちゃんとするのによい場所だということを伝えると話された。「高校卒業」ということよりも、自分の大きな目標の中にそれが含まれているのであれば求めるといいし、学校の意味についても、そこに過ごしていくなかで見つけられればよいと述べられた。
この後、フロアにマイクを回してじかに意見や質問を募ったところ、「現代の若い世代は、言葉による意思疎通がしにくい、対話になりにくいことが増えているが、日常の生活の中でどのようなことに気をつければ意思疎通ができるようになるのか?」「子どもと他者を出会わせるときに『少年の日の思い出』(小説)をどのように使うのか?」「このようなシンポジウムは学生時代のほうが身近で、現場の先生や親御さんたちにとっては参加する機会が少ないのではないか。このような場で話し合われたことをどのように現場に生かしていったらよいのか?」など、それぞれの実感にもとづいた問いかけがなされた。
それらを受けて、3人のゲストが、順番にコメントをされた。村本邦子教授は、「意思疎通ができない親」ということについて、「大人になっていない」とされた。大人になるというのは、自分を相対化して位置づけるということで、他者に届く言葉をつくっていくことが大事だという。
また、このようなシンポジウムで語られたことの現場への生かし方について、理想を語るだけではなく、戦略や方法論を持つことが大事だと述べられた。
遠藤昌子先生は、生徒との言葉による意思疎通がしにくいことを現場の体験から紹介され、それが年々増えていることを指摘された。
竹内常一教授は、言葉の力ということについて、悪口遊びを禁止してしまっていることが子どもたちからパロディを奪ってしまっていることを指摘された。それによると、悪いことをたくさん言ってはじめて良いことが言えるという。また、傷つくということについても、他者を傷つけたことのない人などおらず、傷つけることをくりかえしているうちに、上手に相手が納得できるような方法で傷つけることができるようになるという。そのようなことを重ねながら、少しずつ人生の重荷を背負っていくことを教えるのが教育だと述べられた。
また、若い人たちの問題として、母親は人生を愛することを身体で教え、父親は必要なときには断固として人生と闘うことを身体で教える、ということができていないという。
そして最後は、「子どもを産み育てることの喜びを大人たちが取り戻さなければならない」という言葉で締めくくられた。
司会の滝野教授による、全3回の連続講演・シンポジウムへの簡単なふりかえりに続き、春日井教授が現在言われている「自己実現」の歴史、けっきょくどの子も守られていないのではないか?という疑問、大人の言葉への信頼のなさ、関係の入り口としての身体的な応答の重要性、関係づくり・社会づくり・文化づくりを大人と子どもがどう共有していけるか、など多くの問題を提起して締めくくった。
注)この講演・シンポジウムの内容を冊子として発行する準備をすすめています。詳細については、当立命館大学人間科学研究所のホームページの新着情報でお知らせします。またホームページにフルテキストでアップする予定です。ご確認くださいますよう、お願いいたします。
今回の参加者の声から
- 竹内先生のおっしゃった「異なる他者との共通部分をつくる」という言葉が印象深かった。今の若者は私も含めて面倒なトラブルをできるだけ避け、相手を傷つけないように、自分が傷つけられないように人との接触に気をつかって、合わない人とは接触しないという態度の人間が多い。他者との関係性によって「自分」が発見できる考えのもとにあるなら、コミュニケーションのあり方はもっと考え直されるべきだ。(学生)
- 「自分探し」とは自分の中だけで行われるものとばかり思っていたが、その裏には他者の存在が大きいことを知った。(学生)
- 大学の授業では国際関係学部に籍をおき、経済などを中心に学んでいます。しかし今回のような、自分の内への興味を引き出される講演に出ることで、目の前の世界が層を増したみたいな感覚を受けました。(学生)
- 比較的安易で、ことばによるコミュニケーションを必要としない「自己実現」活動に参加して昇華させていることが多い自分が、青年期や思春期にある子どもとの関係で「ことば」でちゃんとした関係づくりができているか、考えさせられました。(教員)
- 私たちのように主婦(子育て中)でこのような講演を求めている人が多くいると思います。近隣の小・中・高の先生、保護者にぜひ案内が届くようにお願いします。(主婦)
- 大人が子どもに「苦労させない」考えを持っているというのは、子どもの視点から自分の親を批判するのはおこがましいですが、確かに同様の考えを私の親は持って(くれて?)いると思います。それは、祖父・祖母(若者時代に戦争を体験しています)が私の親に同じように「苦労をさせたくない」と思っていたことも影響しているのかなと思います。そいて、親はちょうど働きざかりが高度成長期だったことも関係しているのではないかなと思いました。