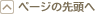司会 それでは、映画を見終わった後の対談ということで、中村先生と村本先生にご登壇いただきたいと思います。どうぞお上がりください。
中村 こんにちは。中村です。
村本 こんにちは。村本です。
 中村
いい映画だな、と思って何回も見さしてもらっています。それで今日は、この「ひとりだけど、ひとりじゃない」っていうシリーズの3回目なんです。ずっと一つの孤独、人には大事なテーマとして孤独っていうのがあるんだけど、その孤独は、孤立とは違うので、孤立っていうのは、ちょっとしんどいんだけど、孤独とそれを支える周りの人たちの眼差しなり、かかわりなりが扱いたくて、このシリーズを組んだんです。今回は「ひとりだけど、ひとりじゃない」っていうテーマにしようと思って4回並べたんですが、一番最初にこの映画を見て、このテーマでやろうかなと思って、後の3つを組み合わしたんです。幸いなことに、最初に『空気人形』。これは、ちょっと後の映画だと思うんですけど、監督さんが、うまく日程を合わして来ていただいたので。ですから並びは、「ラースと、その彼女」、これを最初にしたかったんですけど、全体的な日程の関係で、こういう組み合わせになりました。
中村
いい映画だな、と思って何回も見さしてもらっています。それで今日は、この「ひとりだけど、ひとりじゃない」っていうシリーズの3回目なんです。ずっと一つの孤独、人には大事なテーマとして孤独っていうのがあるんだけど、その孤独は、孤立とは違うので、孤立っていうのは、ちょっとしんどいんだけど、孤独とそれを支える周りの人たちの眼差しなり、かかわりなりが扱いたくて、このシリーズを組んだんです。今回は「ひとりだけど、ひとりじゃない」っていうテーマにしようと思って4回並べたんですが、一番最初にこの映画を見て、このテーマでやろうかなと思って、後の3つを組み合わしたんです。幸いなことに、最初に『空気人形』。これは、ちょっと後の映画だと思うんですけど、監督さんが、うまく日程を合わして来ていただいたので。ですから並びは、「ラースと、その彼女」、これを最初にしたかったんですけど、全体的な日程の関係で、こういう組み合わせになりました。孤独、必要な孤独と、それに触発されたり、孤立に追いやらずに周りがいろんな関係を作って生きていけて、うまい具合に、その人だけじゃなくて、周りもいろんな変化が起こっていくあたりを考えたくて選んだんですね。この映画はとてもインパクトがあった映画で、2007年だったかなと思うんですけど、ずいぶん印象に残っていたんです。それでぜひ、この企画で一度は取り上げてみたかったんですが、ラインナップがうまく組めなくて、何本か一緒に合わせて上映する企画ですので、他のものとセットにしながら、『空気人形』が幸い、そのあと封切られたので、セットにしたいなと。一番最初に触発された映画なんですね。これで見るのは3回目くらいなんですが、その都度、その都度、感動を与えてくれています。
私は、男性研究、「男性性」とか「男性問題」とか言い方をして研究しているテーマをもっていますので、男性と感情といいますかね、このエモーショナルなもの、この「傷つきと男性」とか、そんなテーマに関心があって、そういう側面から、ずっとこの映画を見てました。それで「男性学」とか「男性問題」という言い方をするんですけど、これはたまたま最近出たんですけど、『男性学』っていう本があって、私たちの研究仲間が男性に関するいろんな論文書いてます。それを集めたんですね。この中に「男性」のテーマはたくさんあるんですけど、もちろん暴力とか、戦争とか、男性の同性愛とか、いろんなテーマが出てきます。それから子育てする父親とかが出てくるんですが、こういう「傷つきと男性性」というのは、あんまり出てこないんですね。従来の「男らしさ」像から降りていく。あるいは変化していく。マッチョな男が、いかにしてこの社会の中で鎧を脱ぎ捨てていくかというテーマの主題が多いんです。それを、なんか、ある一面だけだなと前から思っていたんで、もう少し「傷つきと男性性」みたいなことをテーマにしたくて前から考えていたもんですから、こういう映画を、とても大事だなと思って、見て、主題化したかったんですね。
そういうふうに見ていると、また新しい男性のあり方を示してくれているような気もして、今日はここで取り上げたかったって、ことです。ラースの純粋さに心が洗われるようで、そしてその街の人たちも、それと同期しながら、一生懸命ラースさん、ラースくん、と言うのかな、27歳ですけどね、その生き方に同期していく様子が、とってもいいなと思って見ていました。ですので、傷ついた男性とともに、彼の未来とでもいいましょうかね、自立とか、そんなことに、一緒に共鳴したり、場に一緒にいたりする街の人たちや、兄の家族の変化もよかったり、全体的に最後、お葬式なんだけど、確かに悲しいんだけど、なんか元気が出るような、最後の2人の姿だったりして、いろんなものが想起されてよかったなあと思っていたんですね。
今日は村本さんは臨床心理の専門家ですので、女性の視点みたいなものから、また話ができたらなあと思って、お招きした次第です。それと、これ全編4回、今日3回目の人います? このシリーズ3回目の人、手、上げていただけます? ありがとうございます。これは全部、男性が、ある種、テーマになっているんですよね。『空気人形』も、彼女はもちろん主役なんですけど、空気人形を買っていく男性のテーマがあるだろうし、『リリイ・シュシュ』も男の子がテーマだし、今日もラースがテーマなんで、男の人なんですね。『トニー滝谷』も、妻を亡くした男性の話なんですね。そんな意味で、神谷さんと一緒に選んだんですけど、ちょっと男性のストーリーが、話として、もちろんいろんな人たちのかかわりがある映画なんですけど、そんな中で、女性としてどう見たかって話を、まずお聞きできたらなあ、と。村本さん、いかがでしょう?
 村本
今、中村さんの話を聞いていて、私、『リリイ・シュシュ』は見てないんですけど、『空気人形』、それからこの『ラースと、その彼女』『トニー滝谷』も、男性の物語って言われたけど、女性が見てると、女性の物語として見えるんですよね。それが映画の面白さですよね。「傷ついた男性」、男性の傷つきっていうのがテーマになりにくいと聞いて、「あ、そうなのか」って、改めて思いました。私の目から見ると、男たちこそ傷ついている。ただし、傷ついてるけど、無頓着。よくちっちゃい子どもが転んだ時に、「痛いよう」って泣いたら「そんなん痛くない、痛くない」って言うでしょ。血がダラダラ流れてても気がつかないで、無頓着、自分の傷に。それが、私の見ている男性像なので、男性の中で、それがテーマにならないってことなんだなって、改めて思いました。私の中では、それはクッキリと見えているものなので、それがないっていうふうには、ちょっと認識してなかったので。
村本
今、中村さんの話を聞いていて、私、『リリイ・シュシュ』は見てないんですけど、『空気人形』、それからこの『ラースと、その彼女』『トニー滝谷』も、男性の物語って言われたけど、女性が見てると、女性の物語として見えるんですよね。それが映画の面白さですよね。「傷ついた男性」、男性の傷つきっていうのがテーマになりにくいと聞いて、「あ、そうなのか」って、改めて思いました。私の目から見ると、男たちこそ傷ついている。ただし、傷ついてるけど、無頓着。よくちっちゃい子どもが転んだ時に、「痛いよう」って泣いたら「そんなん痛くない、痛くない」って言うでしょ。血がダラダラ流れてても気がつかないで、無頓着、自分の傷に。それが、私の見ている男性像なので、男性の中で、それがテーマにならないってことなんだなって、改めて思いました。私の中では、それはクッキリと見えているものなので、それがないっていうふうには、ちょっと認識してなかったので。この映画を見て私が真っ先に考えたことは、ラースの父親のことなんですね。自分の子どもを産むことによって死んでしまった妻。死なしてしまった自分っていうものを男はどんなふうに感じ、そうやって生まれた子どもを、どうやって、どんな気持ちで育てるのかなっていうのが、真っ先に思ったことでした。多分、自責の念やら、怒りやら、罪悪感やら、それから子どもに対する恨みやら、でも責任感やら、愛やら、多分、相矛盾する感情がごっちゃになったまま、子育てを、この映画の中では一人でしたっていうふうに出てきますので、それまでは、そうじゃなかったけど、それ以降は、人嫌いになって、誰とも付き合わずに子どもを育てたと。どんな子育てを彼がしたのかな、と私は興味があるんですけど、多分、とってもきめ細やかな世話をしたんだと思うんです。なぜならばラースは、とても礼儀正しい、身なりも、きちんとした人として育っていますから。男手一人で育てて、こうやってきちんといろんな人に挨拶をしたり、親切にしたり、身の回りもきちんとして、日曜日、教会にも行ってってという育ち方ができるっていうのは、とても理性的に、精一杯、誠実に育てたんだなって思うんですね。ただ一つだけ、抱っこしたり、抱きしめたり、スキンシップしたり、寄り添ったりってことはできなかったんだろうと思います。その表れが、ラースの身体接触に対して「痛い」っていう感覚なんですよね。スキンシップを受けずに育つと、身体接触が苦手。近い距離も苦手になってしまいがちですけど、そこに痛みを伴うっていうのは、なんか優しさとか、柔らかさとか、接触っていうことに対して、ラースのお父さんが息子に与えられなかったものにまつわる痛みを感じます。自分が傷つき過ぎて。だからこそ、そこにラースの回復の鍵があって、ラースは、リアルドールの柔らかい身体に、ほんの少しずつ接近していく。それから、バーマン先生っていうのがまた素晴らしいと思うんですけども、彼女が、ほんの少しずつ接触していくんですよね。お産のことを考えて混乱するラースに、とても躊躇しながら手を近づけて、触れて、それでそれが受け入れられるとわかると、少しさする。お葬式の時も、バーマン先生の手が出てきて、彼を支える。彼はそういう中で、リアルドールとの接触も広がっていく、接触の度合いが。それから他の人と握手をしたり、女の子と握手をしたりということもできるようになっていく。そうやって身体接触を受け入れられるっていうのが、閉ざしていた鎧をはずし、柔らかい人との接触が回復していくプロセスだなって思いながら見ていました。
少し心理学的な解説もするように言われたので、ラースが、どうしてこういう状況になっちゃったかと言うならば、やっぱり彼にとってはお産、出産っていうのがトラウマなんですよね。カリン、義理のお姉さんは、彼にとって、とても大切な存在としてあったんだと思いますけど、ただ、かなり侵入的ですよね、どっちかっていうとね。この物語は男の物語だって言うけれど、女たちが彼を助けるっていう物語なんですよ。一歩引いて本人の主体性を尊重するならば、近づけない近づき方を、女たちが、ズケズケとではないけれど、おせっかいに一歩踏み込む形でかかわるところから回復が始まっていく。カリンは、その役割を果たした最初の引き金なんですよ。その大切な存在のカリンが、赤ちゃんを産むという状況の中で、恐怖が蘇るんですよね。カリンが出産で死んでしまったらどうしようと。そこで彼は距離をとろうとする。そうなると、カリンが心配して、さらに接近してくる。
もう一つはマーゴっていう女の子に興味が動き始める。その状況の中で、彼は本当にどこにも逃げようのないところへ追い詰められていくんですよね。そこで、彼の心がつくりだしたビアンカという存在を介在させることで、突破口を開いていく。そういうところから物語がスタートしたかなって思います。
中村 最初に言われたように、「男の傷つき」の話なんですけどね、男は傷ついてるんですよね、確かに。それで男の傷つきはあるし、それは実感してるし、たくさんあるんですが、気づいてないわけじゃないんですね。だからそれが、うまい具合に表現できたり、表出できたりする私たちの社会のもってる、あるいは「男らしさ」という文化の、ある種のしがらみをもっている、感情表現がなかなかしにくかったり、あるいは自己抑圧をしたりするテーマがあるので、男が傷ついてない、っていう意味ではないんですけどね。男は傷ついてない、っていう意味じゃなくて、それをうまい具合に、多分こういう言い方をして、繊細なラースさんみたいに、ラースみたいに繊細な形で感受する「男性性」っていうのが、この社会のもっている「男らしさ」の文化行動の中では、うまい具合にフィットするものがなくって。それでどうしてもネガティブに、あるいは抑圧的に、あるいは歪んだ形で、自分を受け取ってしまうという作用があるので、傷ついた男たちの回復なり、再生の物語っていうのが大事かなってことで、日頃から感じているもんだから、ちょっと冒頭に、そういう言い方をしたんですよね。
村本 ちょっと、『空気人形』の話を付け足していい? 『空気人形』の時も、私、ここに来て見てたんだけども、あの後『空気人形』の話をしてて、私はやっぱりここで話題にならなかったことで、「すごく悲しいって気持ちで見てた」と言ったんだけども、そうすると「女性の視点から言うと、そうだよね」って返って来たんだよね。私が見てたのは、女たちの傷つきと同時に、そのさらに向こう側にある男たちの傷つきなのね。『空気人形』の主人公だったあの男性は、ケンカをするところで、なんか傷つきを表す発言をしてしまうところがあるんですよ。あの物語で、私がすごく思ったのは、なぜあの空気人形が人間になってしまったか、っていうのを、人形をつくった人形師が、「その人形は、みんなその持ち主、人形の受け手の心をもらって帰ってくる」と。だから、殴られて。
中村 どんな扱い方されたか、わかるっていう?
村本 そうそうそう。そういう意味では、空気人形が人間の心をもってしまったのは、あの主人公の男性が「自分はもう、こんなどうしようもない人間だから、人形を相手にするんだ」って言いながら、自分の意図を超えて人形を尊重する気持ちを、やっぱり消しきれない人間らしさっていうか、それがあの人形に心を与え、人間にしたと思うんですね。そこに男たちの傷つきとか、悲しみを見るんですよ。
中村 悲しいですか。この私たちの本の中でも「男の更年期」って言い方を扱うところがあったり、それから、はっきりした健康の変化が更年期に出てくるんですけど、更年期障害っていう、はっきりした言葉がないもんだから、男たちは、そのまま走りすぎてしまって、しんどいとか。それから健康診断すら行かないっていうね。こういうセルフケアの低さみたいなものとか、自分と、なかなか向き合いにくいとか、あるいは怒りだったり、悲しみだったり、辛さだったり、感情語が、なかなか出てこないとか、感情表出する機会が少ないとかっていうような状態を、なんとか改善したくて。それから自殺なんかも結構、中年男性が多いので、その辛さみたいなものが、そんな行動で社会病理っぽくあるのかな。だから、一つの社会的背景、文化的背景があって、そういう男らしさのテーマがあるとすると、個々人の別に男の弱さではなくて、私たちの男性性の抑圧さみたいなものを感じるので。それが暴力だったり、というテーマで出る人もいるし、こういう傷つき具合で自己抑圧、あるいは鬱的な事態になってしまったりするような形でのテーマがあるかなとか。それから、もう一つ戦争を体験した人たちが、自分の戦争体験をなかなか語りにくかったりとか、社会がなかなか語ることを許さなかったりするテーマもあるんですけども、封印してしまう。辛いことを封印してしまう。蓋をしてしまう。特に、生まれた時に、ラースはお母さん亡くなってたわけだから、その辛さを、お父さんも、そういう形で子育てしてるんだろうと思ったら、そんなに語らなかったかもしれない。お父さんが。
村本 だって彼はお父さんの仕事も知らないですからね。
中村 お父さんが語らなかったから。
村本 お父さん、死んだの結構最近でしょ?
中村 2003年ですからね。
村本 24歳だと思うんです。
中村 3、4年前のことですよね。
村本 そうそう。だけど、ラースはお父さんの職業すら知らない。
中村 兄は知ってましたよね。だから、語らなかったんでしょうね。封印してしまった。その中で男性の傷つきが表面化しない、表面化し得ない、しにくい事態で、結局、男性が落ち込んでいくテーマを、「失感情的」感情を失うような事態で表現する場合があるんですよね。それがとてもよく出てたなあと思って。それをそこから、もう一回自分なりの家族の物語だったり、自分の人生の物語だったりを回復したり、生き直したり、問い直したりする、ある仕掛けとして、ビアンカが現れて、とても衝撃的に現れましたよね。先ほど村本さんも、ある緩衝地帯みたいにして人形の存在って、大きかったなぁって話をされてたのは、私も、そう思いました。とてもいい存在でしたよね。とはいえ、ビアンカって誰なのか、ってことは、私は一生懸命最初から見てて考えていて、あれ確かに妄想だったり、幻覚だったり、いろんな自分なりの想いがそこに投影されていくんですけども、ビアンカって誰なのかな。お母さんのような気もしたし、それから自分の恋人のような気もしたし、しかし、いつまでもあの関係を続けるわけにいかないので、最後どう終わるのかなとかね。結局、自分でキスまではいったんだけど、母親だったらキスしないし、しかし現実の恋人のような人たちも現れてきて、だからものすごく葛藤が、ビアンカを通して見えてきますよね。あのビアンカは、よかったなと思いましたね。
村本 映画の中では、あれ、妄想って呼ばれていますけど、臨床心理学的な立場から見てますと、やっぱりラースの心の一部っていうか、彼の分身なんですよね。ある種、乖離したものを人形に投影しているって言えるんですけども。たとえば面接室の中でだと、ああいうことは、ありうるっていうか。ある種、人形という形で、リアルドールって形でおかないんだけども。
中村 そうですよね。
村本 そこに一つのメタファーと言えると思うんですけども。
中村 箱庭なんかも。
村本 それも、その一つだし、エンプティチェアなんかを置いたりして、やったりするのもあるんですけど、ある意味、彼の心がつくり出した空想的な存在であって、彼の分身であると思うんですね。そこにうまい具合に、というか、とてもうまくリアルドールというものを持ち込んだところで、他の人に、第三者に、要するに私たちだって、面接室の中で、ある種のメタファーというか、イメージとして扱っていくものが、リアルな存在として可視化されるんですよ。それが今度は、ラースの心の一部だったものが、実際、実体をもって街の人たちとかかわりを持ち始めるところから、この物語が展開していくんですね。だから常識的に考えると、もしこういうことが起こるとすれば、面接室の中と、せいぜい家の中だけで対話がなされる。その中で何かの変化が起こっていくんだけども、それが、小さな街、スモールタウンで人間関係があって、そしてお兄さん夫婦が教会の人たちにお願いに行くんですよね。とても受け入れられないけど、これ受け入れてやってほしい。普通は、それはあり得ないと思うんですけど、私たちの社会では。そこからみんなで悩みながらもその人形を一つの存在として受け入れていくっていうとことから、ラースの心というものを超えて、今度は他の人たちが巻き込まれて物語ができていく。それがこの映画の奇跡なんですよ。
中村 そうですね。トロントの街の設定なんだけど。小さな街、スモールタウンのフレームがわりとはっきりありましたよね。そこで教会があったり、あるわかりやすい淵があって、とてもそれが安心して見えて。あれが、もし京都の四条河原町とかね、街中だったらね、あんなふうに人がサポーティブにあり得ないので、「ラースは、アホちゃうか」って、こういう話になってね、また違うラベリングが起こって、ラベルが貼られて、あんなにサポーティブにフレームの中で人々を持たずにあるなって思って。大阪はもっとサポーティブかもしれませんけどね。後で別のフィルム見てもらいます。
そういうある種の安心感がありましたよね。フレームといいましょうか。多分、箱庭なんかも箱があるから、ある枠があって、何かいろんな妄想とか、自分の見たくない側面とか、嫌な側面とかいっぱい出てきてもいいんでしょうけどね。そのやっぱりフレームが、うまく描かれていたなという気がしますよね。そこのある安心感みたいなもの。
さらにもう一つは、あの先生もうまい具合に働いていたけど、援助する、されるだけじゃなくて、街の人たちも、なんか癒されていったり、変化していったりするのが、とてもよくわかりましたね。
村本 面白いのは、後で見るものは「女バージョン」らしいですけども、男たちにとって、ある種、好みの女をカスタマイズするっていう発想、自分の好みの女にして、そして自分が会いたい時は会って。
中村 あ、ネットの販売の話ね。
村本 そうそうそう。
中村 みどりさんって、東京の人も出でいましたね。
村本 そうそうそう。そうやって自分の思い通りの存在で、投影をそのまま受けとめてくれる女であってほしいって。しゃべらない女は最高だとかね。そういう願望が出てきますよね。ラースも、そういう意味では、自分の願望をそのまま受けとめてくれる静かな、静的な存在としてのビアンカという形でスタートするんだけども、でも実際、その中でいろんな葛藤が起きてくる。一つはマーゴっていう現実の若い女の子。興味をそそられている若い女の子との対比において、マーゴは、生きてるから後姿の表情、身体の表情が、ものすごく生き生きしていて魅力的に出てきてますよね、この映画ね。身体の表情。それと静的、静かな人形との対比であるとか、あるいはその中で、人形が街の人の誘いがあって、自立的な生活を始めていく。
中村 そうですね。
村本 そういうなかで自分の思い通りにならなくなっていく。ラースは、自分の存在に、とても自己否定感っていうか、罪悪感をもっているんで、誰かに自分の欲求を押し付けたくないし、押し付けたくないからこそ深い関係をもたなかったものが、少しずつ回復していく中で、愛着関係や執着心ができてきて、怒りが出てくる。その怒りを通して、今度は街のおばちゃんですよね、助けてる。そのおばちゃんが、自分自身の気持ちを代弁する形で「あんたも、うちの夫と一緒だね」っていう形で自己主張を始めていくっていうかな。そのあたりのダイナミックスがすごく面白いなと思って。
中村 そうでしたね。教会にデビューするっていう。多分、あれ、お母さんぐらいの年齢の女性たちなんですよね。最後の悲しい場面で一緒に編み物しながら、一緒に時間を過ごしてくれたり。なんかするわけでもなく、そこに一緒にいる。「とにかく食べなさい」と。ああいうの、よかったですよね。 それからあと、ビアンカも一人の人間だから、人生あるんだからっていって、余計なお世話のおばちゃんとかね。ああいうのもいいですよね。
村本 だからあそこのシーンはね、ある種、子宮の内部的なんですよ。おばちゃんたちが、みんなで編み物しながらそっと寄り添って、ラースが部屋の中でくるまれてるっていうか。あれがあって、あの湖なんですよ。あの湖、どう思いましたか? なんでビアンカは、もう死ぬ直前なのに湖に入らなきゃいけなかったのかって。それ、私の疑問なんだけど。水に入るでしょ、2人で。どっちかが先に入ったのか、わからないけど。あれはどう見ましたか?
中村 あれはやっぱり、葬式とかね、最後の場面全体につながるトーンだなと思って。最後、キスしましたよね、直前にね。あれ、リアルドールだから、本当は性の話がね、性の話までいくと私としては面白くなかったので、あそこで、よく止まったなと思うんですよね。それで、さっき言ったように、あの、ビアンカのある種の妄想の一部、幻覚の一部、あるいは物語の一部が、母親性があるとすると、あそこでやっぱりキス以上のことしてしまうとね、やっぱりラースの立ち直りによくないなって思ったんですよね。それでさらに、それ以上やっぱり、自分で死を、ある種、きちんと処理するためには、ビアンカは死ぬはずないわけで。人形なんだからね。やっぱり死ぬはずがないものが、やっぱり死んでいく。それは自分の次の人生をスタートさせるために必要な作業なので、別に恋人のようなものも現れたりするとね。葛藤を収めざるを得なかった。そのためには、湖の死って是非いるなと思ったんですよ。やっぱり「水」っていうのがもっている象徴的な作用があるかなって見てたんですけど。
村本 私も、そこいつも疑問に、シーンをね。なぜ、わざわざ水に入る必要があったのかって思いながら、とりあえず今のを聞いて、同意見なんだけども、やっぱり死ぬ、生から死に移る区切りのところで、難しいんですよね、人形だからね。危篤状況になっても救急車が呼ばれて治療を受けたりしてしまうし。
中村 そうでしたね。
村本 どこで、死っていうところに移行するかって時に、この映画は彼が子ども時代、少年を生き直して大人になる、ある種のイニシエーションなんで、彼が主体的に自分で殺すっていうことをせざるを得なかったと思うんですね。それがさっき言った、子宮体験の後にに続く「死と再生」というかね、そういう意味をもっているのかなぁって、私は見てました。とても象徴的でしたね。
周りの人がみな、助けようとするから、あそこでまたビアンカ生き返ったらどうしようかなって心配しちゃったんだけど。テディベアに一生懸命、救命措置施せるような繊細な人なので、なかなか終わり方、難しいなと思ったんですが、ああいう形で納得しながら見られたというような。それで遠目だったから、ちょっとよくわからなかったし、何が起こったのかもよくわからなかったけど。一つの象徴的な死っていうのが描かれたのかなと思って見ていましたけどね。それで、テディベアとかフィギュアの青年も面白かったですね。フィギュアの青年っていうか、パソコンの周りにいっぱいフィギュアを置いて。あの2人がいることで、フィギュアとかテディベアが出てくることで、ラースがすごく特殊な異常者ではなくて、その間をつなぐ存在になっているんですよね。
中村 そうそう。で、教会のおばさんも、「そんなん、普通のことよ。あんたのネコに服着せてるでしょ」って話から始まりましたよね。ああいうのがとても相対化していきますよね。ラースが、いるんだと。あたりまえ。私もふと、自分の部屋を想像したりしましたけどね。
村本 フィギュア、置いてるんですか?
中村 フィギュア、まあ、いろいろ近いもの置いているかもしれませんね。だから多少自分の中にある、いろんな自分を納得させたり、自分を落ち着けたりする、いろんなものがやっぱり周りにありますよね。そんなことの延長線上にビアンカがいてもおかしくないっていう、とてもいい設定でしたよね、あの2人。
村本 そう、だから私も思い出してたのは、娘がちっちゃい時に、乳母車に赤ちゃん人形乗せて、すごく混雑している梅田に行ったり、スーパーマーケットに行ったりするんですよ。そのシーンを思い出してね。子どもだから、「何でこんなに混んでるのに、遊んでるの?」っていう面もあるんだけど、ある種、ほほえましい見方をされるんだけど、大人の男が、車椅子で、こんなリアルドールを運んでると、みんなが奇異な目で見る。じゃ、どこで線が引けるのかなって言ったら、ほんとのところ、ないですよね。フィギュアと、リアルドールっていう線引きもないように。そういう意味でいうと、とっても突飛な話ではなくて、私たちの延長線上にある物語だなと思いますね。
中村 だから、街の人たちも、なんか同期するものがあって、シンクロするものがあって、私たちもそういう生を生きてきたし、これからも生きているかもしれないし、なにかフレームの中のサポーティブな、環境がよかったなあということでしたよね。
あと、ラースの繊細さみたいなやつね。確かに、お父さんの姿が全くわかんないから見えないんだけど、確かにお父さんが一生懸命に育ててくれたから、ああいう繊細さが育ったんでしょうけどね。でも、お父さんと、そんなに愛着形成しなかったんでしょうかね?
村本 だから、スキンシップ。
中村 身体の話ね。
村本 身体接触と寄り添う、っていうか共感っていうか、そういうとこが、なかった。
中村 矛盾してるんですかね。
村本 だから男性は、感情を置いてけぼりにして、とにかく責任感で一生懸命やった。それを愛情と読み換えるんだけど、親密性という点でいうならば、とても遠い存在だった。
中村 そうですよ、そこは矛盾してますよね、きっと。あんな繊細な多分ラースに育った。もちろん彼の力なんだけど。それでお母さんがいなくなったことに対して、いつも敏感だったからなんでしょうけどね。その身体感覚。女性恐怖なのか、なんでしょうね、対人接触の怖さなのか、それが、身体感覚に、よく出てるんですが、その繊細な心と対人関係が、ちょっとずれてますよね。
村本 もう一つは、街の人たちの優しい眼差しってものがあったと思うんですよね。お父さんだけじゃなくって、街の人たちは、みんな遠巻きに、小さな街なんで、みんな事情も知っていて、「ラースはいい子よね」って言ってくれるような。
中村 それでそこを大事だなって思って、今、聞いたのは、たとえばこの男性学の我々の研究の関心からいっても一つのテーマがあるんですが、キャンパスで若い男の子同士が手をつないで歩いているっていう身体親密さは、女の子同士が、女子学生同士が手をつないで歩いているっていう親密さ感覚と、ずれがありますよね。その周りの反応という意味で、ちょっと違うものが出てきますよね。男の子同士が手をつないで歩いているっていうのが、キャンパスでは、そう想像できないわけですよ。あまり、あり得ない。ところが最近の女の子は、比較的そういう身体接触もよくして、シスターフッドみたいにしてね、とても親密だし、っていう、身体という点では、とても違うコードがあってね、これはどう思います? 若い男の子、男子学生同士が手をつないで歩くという。
村本 特に今、日本は、そうだよね、きっと。だから女性同士であっても、アジアなんかに行くと、大人の女性たちが、みんなくっついてるし、去年か、中国に行った時、びっくりしたのは、大学で、女の先生と女の学生たちが手つないで歩いてたり、ちょっと日本ではあり得ない。
中村 そうですね、アジアとか。
村本 西洋だと、一応ハグするんで。
中村 儀式的な身体接触は、かなりありますね。
村本 そうそうそう。そういう意味で、日本の男が、一番身体接触がないのかな。
中村 これ、みなさん、どう思います? 男子学生がキャンパスで手をつないで歩いている。別に、これはあり得ることだし、親密さとしたら、一つの表現だし。父と息子が手をつないで歩いている。ちっちゃな子だったら別だけど、母と娘が、大きくなってもね、手をつないで歩いている。身体的に近い。やっぱり距離がありますよね、それぞれ。で、それが日本独特かどうか、っていうのは調べないといけないんだけど、日本は特にそういう感覚がありますよね。しかし男たちも本当は親密なんですよね。親密になりたいんですよね。それで、こういう世界を共有したいわけですよね。一緒に泣きたいわけですよ。ところが、何か別のものが邪魔をしているんですよ、きっとね。
村本 というか、だから、それに対してなりたいって思ってるよりも、恐怖なんじゃない?
中村 何の恐怖でしょうね?またいろいろ意見、聞かしてほしいんですけど。そういう形で、しかし、本当は親密な身体接触をしたいんだけど、そこでいろいろ装置を考えるわけですよね。一緒に装置を考えて、同性愛に対する、ある種の、ホモホービアっていうんですけどね。そのホモホービアみたいのがあって、ほんで同性愛に対する、ある種の恐怖感。異性愛からすると、そういうふうにあって、リアクションに対して、とても感じてしまう。同性愛恐怖、同性愛者として見られるんちゃうかっていう、ホモホービアっていってますけど、そういうのが強い社会ですよね。
ところが、アメリカなんかは、『ミルク』とか『ハーベイミルク』っていう映画があるように、殺人なんかが起こりますよね。同性愛者に対する殺人ですよね。「hate clime」。嫌悪犯罪っていいますけどね。日本はまだそこまで強くないのかもしれませんが、やっぱり同じようにホモホービアみたいなものが、男性同士の身体親密さには、やっぱり出てきます。
村本 そのことで、男性たちは、性関係において、とても損をしてるという気がしていますね。つまり、身体接触とか親密さの延長として性というものが、つながりにくいというか。そこが切れてて、自分の親密な感覚から延長していってるものというよりも、刺激、外から刺激を得て、なんか煽られてくる性っていのうか、なんか、それをすごく感じますね。
中村 そうですね。だから割と刺激とポルノグラフィは重なるんですけどね、そういう形の性の有りようっていうのは作られてるなと。
村本 だからそれは深まりをもたないよね。
中村 深まりは、そうですね。深まりをもつ、はい。かもしれませんね。
村本 外側の刺激として煽られるだけでは深まりをもたないから、男性が100%そうだとは言わないけども、傾向として、男性のジェンダーの問題として、ものすごく不幸だなと。
中村 あるいはセクシュアリティの幅が狭いのかもしれない。もっと本当は感受的なテーマがたくさんセクシュアリティにはあると思うんですけどね。そういうのがちょっと狭いのかもしれませんね。
とはいえ、これだけ男も繊細なので、こういうラースみたいな人が、やっぱりちゃんと存在感をもって受け入れられて、いいなと思っていたりします。ボウリング仲間もよかったですよね。あのボウリング仲間も、あんなふうにしてラースが一緒にまた、一緒になってそこでゲームができる。ああいう仲間関係の中にまた戻っていって。だから女性との親密な関係だけじゃなくて、そういう男性との親密な関係も、もう一回、紡ぎなおされたりするのかなって思って。
村本 でもあの映画は、女たちの一歩踏み込む力がなければ、男たち同士だけだと起こらないね。起こりえないね。
中村 女が、女が。
村本 女が大活躍の映画だと、私、これ思うね。
中村 これ、全部そうなんです。男の主題みたいにして選んでいるんですけどね、実は、男が全面に出てるように見えて、実は女に仕掛けられてるっていう側面もあって。別に対立させるつもりはないんですけど、ある絡まりあいの中で出てくるテーマ群だなと思ってね、選んだんです。だから、決して男も傷つかないわけじゃなくて、それをちゃんと表現したいし、うまく。でも、これ女性も、ちょっと引っかかってるところがあって。「やっぱり男は稼いでよね」「やっぱり男は軟弱だと困るよね」。こういうことありません?
村本 私はそんなこと言ったことないですよ。
中村 そこのテーマは、まだ残ってるなって思ってるんですけどね。男性を失感情的に追いやってるのは、そういう女性も加担する。
村本 もちろん、それは相互作用ですから。相互的なものだと思う。
中村 そんなことを感じながら、いろいろ見てました。いろいろ残り十数分なので、良ければみなさんのご意見だったり、もう一つお見せしたいものもあって。今日、スペシャルで、2分ばかりのある映像を準備させてもらいました。もう映画のことでいいですか。もし気づいたことがあったりしたら。
もう一つ、この映画をずっと並べて『ラースとその彼女』をぜひラインナップに入れたいな、と最初にインスパイアされたもう一つ前のフィルムがありましてね。これ、映画じゃないんです。映画じゃないんですけど、ラースは外国の話なので、もっと身近に感じてきたのが、もう十数年前から、私はある映像がこびりついていましてね。それがもっと前にあるんです。それで、これは私の大好きな番組で、テレビほとんど見ないんですけども、「探偵ナイトスクープ」というのがありましてね。その中に、「マネキンに恋をした」っていうタイトルのものがあるんです。朝日放送から許可を得まして、放映してもよろしいという許可を得ましたので、しかし全編は流してもらっては困ると。今DVDで売っているからと。その一部分だけ許可を得たので、ちょっと見てほしいなと思っています。これ、実に京都から近い、枚方の話です。ちょっと2分ほどですけど、見ていただけますか?
中村 朝日放送から、必ずこれ(宣伝用パワーポイント)を流してほしいと言われて許可をもらったのですが、今、売り出しているものです。「探偵ナイトスクープ」のこれが入っているのが、1巻か2巻のどっちか、だったようです。これが平成9年なので、もう11、12年前で、私これ、こびりついてましてね。これもっと前後がある話なんです。それで同じようにイケメンマネキンに恋をして、あのセットのマネキンたちは『空気人形』で出てきた人形師の家に、たくさん返されていたマネキンなんですよ。みんな、ああいうふうに復帰して結婚式に登場したんですよね。仲間ですから。それであの家族が凄かったですよね。「この子、こうなると思っていました」って、とっても理解してましたよね。「探偵ナイトスクープ」ですから、前のフリがずっとあって、あの人形を探しに行くところから始まるんですけども、最後、どうなると思います? これにもう一つオチがあるんです。当然、『ラースと、その彼女』と同じように、なんか処理をせなあかんのですよね。このままだと生活が続かないので、どうなったかというと、彼女は離婚するんです。うまくいかなくなるんです、当然ね。離婚をして現実の世界で生きていくわけです。ある種、離婚という作業。まだそこまではいかないんだけども、やっぱりマネキンとは結婚生活はできないという、自分なりの物語をつくって終わるんですけどね、っていうのが11、12年前、もう、こびりついていましてね。ここで『空気人形』出たし、『ラースと、その彼女』もきたし、とこういう一つのテーマ組んで、そこらへんの世界の話なので、とてもわかりやすくて。あのイケメンマネキンは亀岡の造り酒屋で登場してたようですけどね。そんな世界もあって、これは男女逆転してますけど。いろんな形で、自分の物語をつくりながら、とっても、そんなへんな世界じゃないものがそこにあるなと。アメリカ、トロントだけではない、カナダだけではない世界が、関西にもあるな。ちょっと紹介したくて流さしてもらいました。身近に感じてもらえたかなと思って、流さしてもらいました。どうでした?
村本 私の興味は、男と女が、ただ単に逆転するだけじゃないような気がして、もうちょっと、これよく見てみたいね。つまり、どっちかっていうと男性のほうが積極性、女性のほうが受動性っていう伝統的な役割の中で、だから「あなたのお人形さんでいたい」っというようなポジションにいがちな女性が、むしろ逆に、何もしない男性に自分が積極的にかかわるポジションをとるってことは、ただ単に逆転しただけじゃなくって、なんかもうちょっといろんな絡みが、あるんかなって思うんで、そのへん、もうちょっと見てみたい。
中村 はい、そうですね。このテーマを大事にしながら、そういうちょっと継続して議論していければなって思います。よければ、皆さんからもご意見なり、「私はこう見た」とか、いうのがあればどうぞ。なんでも結構ですから残った時間でいかがでしょうか?
質問 私、今日呼んでいただいたんですけど、私、「傷つき男」だからってことで、呼んでいただいたんですけど。
中村 決め付けたわけじゃないですよ。
質問 それで、さっきこの映画見て思ったのは、アメリカ映画だから、最後、また女の子と結ばれるんじゃないかなっていうふうな終わり方をするじゃないですか。だけど、私はあれ、むしろ、もう女の人いらないって生きてくれたほうが、面白かったかなと。セクシャルな女性は、いらんというような描き方も一つの選択肢として選んでくれたほうが。ヨーロッパ映画だったら、そういった描き方をする可能性もあると思うんですよ。アメリカだから最後は、どうしても異性愛的に終わっちゃったのかなって思いました。というか実は私は、この人たちよりもずっと年をいっていて、40代で結婚してないんですけど、実は私の周りにもで、私と同年代で全然結婚歴のない男性っていうのがたくさんいるんですよ。結婚してないだけで彼女がいるっていうふうでもないんですよ、みなさん。だから、女性がいなくても生きれる人はいるわけですよ。それでもって、私、今年になってブログで何人かの女性とケンカして、なぜケンカしたかというと、その女性のコメンターの人っていうのは、必ず私は大体自分の日常の愚痴とかを書くんですけど、悩みとか。そうすると、なんか「パートナーがいないから、あなた悩むんだ」ってことをコメントを入れてこられるわけですね、ブログに。この映画でも、最初のところで、女性たちが「一人で幸せなわけ、ないでしょ」ってことを何人かの女性が口にするじゃないですか。あれがちょっと私は正直言うと、不愉快でした。 あと、そんなことはないっていうか、そういう人もいるんでしょうけど、それはちょっと思ったっていうところでしたね。
中村 はい、ありがとうございます。まあ、まあ、そういう見方で、一つの視点ですよね。何かあります?
村本 これ映画なんで、もう一つ言えば、こんなに街の人が、みんな良い人たちだけって、ちょっとあり得ないとも言えるわけで。だから一つの物語で、最終的に異性愛っていう性に結びつかなくていいと思うんですけれども、でも、バーマン先生が「抱きしめられると安心するのよ」というように、近しいこととか、傍にいることとか、寄り添うこととか、そういったことに対して開かれているあり方っていうのはいいなって思いますけどね、私はね。みんないろんな事情があって、いろんな状況があって、最初のラースもそうだけど、それを尊重しすぎると、このラースは、このまま一生いくわけですよね。そこに葛藤があると思うんだけど、私が言いたかったのは、この映画の中で、男性だけだとラースが、「僕は一人でいいんだよ」って言うから「じゃ、それでいいよね」っていうことでお兄さんも引いていく。尊重しているわけですよね。そこからは何も物語が始まらない。そこに一歩踏み込んで、おせっかいをするところから動いていく、っていうところが面白いところだなと思いますが、おっしゃることは、もっともだと思います。
中村 これ、だからさっき言った男性と親密さのテーマが、もう一つあって、必ずしも、つがわなくてもいいし、最後男女が恋人にならなくてもいいし、って言うんだけど、割と強調的に対比的に描かれてるもんだから、そのラースの兄貴、その兄弟の親父は見えないし、それから兄も、とても常識的な人として描かれているし、最後は理解していったりするんだけど。だからフィギュアの男も、フィギュアの男だし、教会のおじいさんたちも、とても草の根保守主義みたいなタイプな人たちだし。
村本 いや、だからそういうことを言い出したら、この映画は成り立たなくってね。そもそもカリンだって、子どもを生むために仕事を辞めて家にいて、とってもいい奥さんじゃない。だから、それを言い始めると、これは。
中村 だから、いや、そういうことじゃなくて。そういうことは映画だからやむを得ない描き方なんだけど、男性にとってのケアする能力みたいなものがね、どういうふうに育まれていって、他者とともに、あるってことの感性なり、あるいはスキルなり、あるいは態度なり、行動なりが、どうあり得るかっていうね、そういうことを抜いたとしても、そういうこと是としたとしてもあるかなと。今、お聞きしながら、ね。
村本 で、その問題っていうのは、今の「草食系」とか言われるけれども、ナイスな男性のあり方、マッチョなあり方に対する嫌悪から、新しいモデルを探そうとする時に、ラースのように繊細で一歩引いていて、おせっかいはせずにって、そこになってしまうっていうのかな。
中村 そうですね。といっても、私はあんまり草食も肉食も好きではなくて、私は雑食性でいきたいなと思っているんですけどね。で、雑食性っていうのは、何を言いたいかっていうと、だからマスキュリティズ、複数の男性性、いろんな男性性があるなって、いうことを言いたくて。もっと幅が広いんじゃないかなってことですよね。ということを気づかせてくれた意見として今、聞いてたんですけどね。
そしたら、大体いろんなことが、もちろんこれ以外にもね、たくさんのテーマがありそうな気がして見ていました。来月は『トニー滝谷』。これ村上春樹さんの小さなエッセイ、短編なんですけど、それに触発されて、映画としては独自の世界をつくっている『トニー滝谷』。これも、男が一応描かれていますが、女たちの物語のような気がしますので、ぜひ、お越しください。
今日、多分後ろのほうに座ってた方は気づいているかもしれませんが、いわゆる映写機で回してましたので、ちょっと映写機の音が古いカラカラまわってる音がしていて、とても心地よかった。後ろで聞いていると。それで、このホールは映写機がなかったので今回入れて、画質が、時々フィルムの切れ目とか、パチッとか、ああいうのが見えて、フィルムとして、よかったなと思って見てましたけど。
そんなことで「ひとりだけど、ひとりじゃない」っていう冒頭申した、孤独と孤立の違い。人には大変大事な孤独、人にとっては私は大変大事な要素だと思っています、孤独というのは。孤立にならないように、あるいは巣ごもりだったり、自分の時間だったり、ちょっと放っといてよという。そういうのを大事なテーマと。その中で、やっぱり人間が単に時間を無為に過ごしているわけじゃなくて、再び、生き直したり、もう一回、やり直したりする、いろんな作業をしてるんだなってことが、心理臨床の部屋だけじゃなくてね、カウンセラーとの語りということじゃなくて、街の中にでてきたっていう、そういうとてもいい中で、見てるほうも、なんか心がラースの純粋さとともに洗われれていくような気がして上映させてもらった次第です。いろんなおしゃべりしましたけども、皆さんともまた後で、ちょっとあそこにコーヒー用意しましたので、ぜひ話がはずめばなあ、と思っています。この映画会は、こんな形で大事にしていきたいと思っています。秋は秋で、また企画をたくさんしますので、次回にはチラシを配布できるかなと思います。楽しみにしておいてください。じゃ、今日は本当にどうもありがとうございました。村本さんも、ありがとうございました。
Copyright © 立命館大学 All rights reserved.